公開日:2025.09.07 更新日:2025.08.04
家を売る流れ総合ガイド|基礎知識から手順・費用まで徹底解説
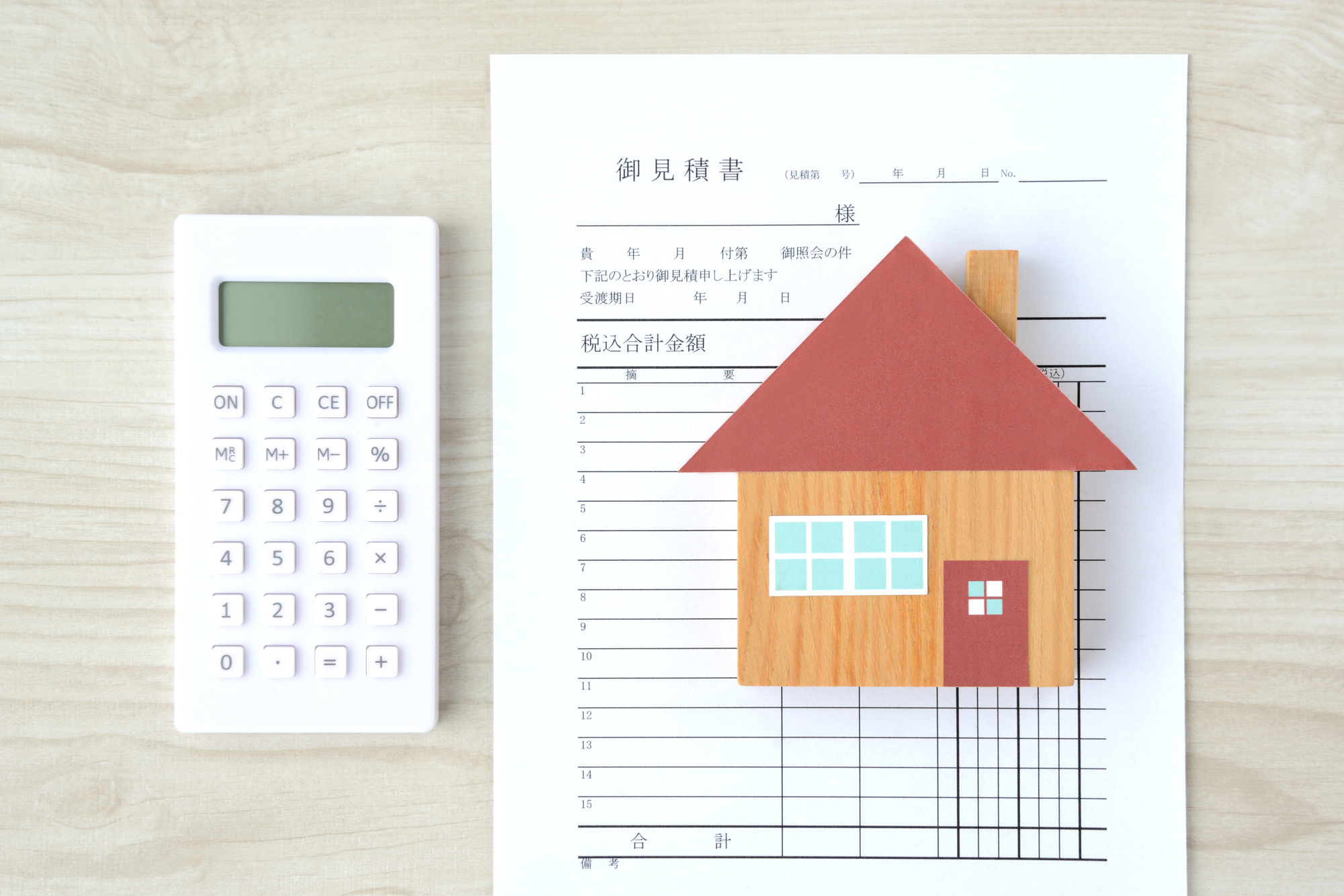
家を売りたいと思ったとき、多くの人はまず何から始めればよいか戸惑うと思います。家の売却は一生に何度も無いことなので分からなくて当然です。しかも、各ステップで多くの書類や費用が発生するので、手続き全体を把握するのはかなり難しいです。
そこでこの記事では、不動産の知識が無い人でも、家を売る全体の流れが分かるように、売却方法や費用、書類、注意点などを網羅的に分かりやすく解説していきます。
目次
家を売るための事前準備

家の売却は、実際に動き出す前の準備によって成果が大きく変わります。ここでは必ずやっておきたい事前準備事項を4つのポイントに絞って紹介します。
家を売る目的とゴールを明確にする
まずは家を売る目的をはっきりさせましょう。売却方法や価格、期限といった諸条件を決めるときに、目的が定まっていると明確な根拠に沿って設定できるようになります。
また、具体的な目標ラインが定まっていれば不動産会社との相談や買主との交渉でもメリハリのある判断ができるようになります。
基本的な売却方法を知る(仲介・買取・個人売買・リースバック)
住宅の売却には、大きく4つの方法があります。それぞれに特徴があるため、自身の状況や優先順位に合わせて選択しましょう。
- 仲介
不動産会社を通じて買主を探す方法。相場に近い価格で売れる可能性が高く、契約や交渉も任せられる。ただし、売却完了まで時間がかかることがある - 買取
不動産会社が直接買い取るため早期の現金化が可能。売却価格は仲介の70%程度が一般的 - 個人売買
仲介手数料が不要で柔軟な交渉が可能。ただし物件PRや契約書作成、トラブル対応などはすべて自分で行う必要がある - リースバック
売却後に賃貸契約を結び、引き続き住み続ける方法。高齢者や住宅ローンの返済が負担になっている人に適している
売却に適した時期や築年数を知る
売れやすいタイミングを見極めることも重要です。一般的に不動産市場は転居が多い2〜3月や、会社の異動がある9〜10月に活発になる傾向があるので、そのタイミングに売却活動ができるようにスケジュールを組むとよいでしょう。
また、築年数は浅いほど高評価されやすい傾向がありますが、リフォームやメンテナンス履歴があれば実際の築年数よりも高く評価される可能性があります。築年数だけにとらわれず、総合的な条件で市場価値を見極めましょう。
必要書類の事前準備
家を売るには、多くの書類が必要になります。必要な書類はのちほど詳しく解説しますが、複数の場所を巡る必要があったり、取り寄せるまで時間がかかったり、再発行が必要になったりと何かと手間がかかります。
不足していると、売買契約や引き渡しの手続きに遅れが生じる恐れもあります。できるだけ早めに準備しておきましょう。
家を売る一般的な手順・流れ

家の売却は、一般的に以下の7ステップで進めていきます。
- 1.売却価格の相場を調べる
- 2.不動産会社に査定を依頼する
- 3.不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 4.売り出しと内覧対応
- 5.条件交渉・売買契約の締結
- 6.決済と物件引き渡し
- 7.確定申告を行う
家の売却には売るための準備、売り出し中の対応、売却後の手続きなど、さまざまな付帯手続きがあります。どれも欠かせない手続きなので、ここで全体を把握しておきましょう。
STEP1:売却価格の相場を調べる
まずは不動産会社に相談する前に家の相場を知っておきましょう。相場を把握できていると、根拠に基づいて価格交渉や売り出し価格の設定ができるようになります。
相場を調べるには、不動産ポータルサイトや国土交通省Webサイトが便利です。これらのWebサイトでは、近隣の成約事例や地価公示データをチェックできます。
なお、同じ地域でも立地や建物の大きさや状態、築年数などで価格差が生じるので、複数のWebサイトをチェックし、なるべく自分の物件に近い条件を探しましょう。
STEP2:不動産会社に査定を依頼する
相場を理解できたら不動産会社に査定を依頼しましょう。査定方法には、書類から大まかな価格を出す「机上査定」と実際に物件を見て具体的な価格を出す「訪問査定」があります。
一般的には、机上査定で複数の見積もりを比較して不動産会社を絞り込み、訪問査定で具体的な価格交渉をするという流れで進めます。
このとき、机上査定はなるべく多くの会社から取得し、価格や対応の良さなどを比較しましょう。1社ずつ依頼するのは大変なので、まとめて依頼できる一括査定サービスを使うと便利です。
STEP3:不動産会社と媒介契約を結ぶ
査定結果に納得したら、媒介契約を締結します。契約形態には、複数社に依頼できる「一般媒介」と、1社に絞って依頼する「専任媒介」及び「専属専任媒介」があります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の主な違いは、自分で買主を探す「自己発見」ができるか否かです。専属専任は自己発見ができない、縛りが強い契約形態ですが、その分、不動産会社の責任も強くなるので積極的な営業活動が期待できます。
STEP4:売り出しと内覧対応
媒介契約を結んだら、不動産会社が物件情報を広告に掲載して買い手の募集を始めます。
あらかじめ物件を清掃しておき、いつ内覧希望者が来ても大丈夫なように準備しておきましょう。内覧での第一印象がその後の判断を左右することは多いです。
STEP5:条件交渉・売買契約の締結
購入希望者が見つかったら、売却価格や引き渡し時期、付帯設備の有無などを交渉し、条件が整ったら売買契約を締結します。
ここで気を付けたいのは、契約書の内容を細部まで確認することと、多少の交渉には対応することです。購入希望者は入居日や融資、ローンの返済計画などの都合で条件交渉をしてくる可能性があります。条件を譲歩した方が結果的に得をすることもあるので、交渉の余地は残しておきましょう。
STEP6:決済と物件引き渡し
契約後は買主から残代金を受け取り、所有権の移転登記と鍵の引き渡しを行います。このとき、物件に抵当権が設定されている場合は抹消手続きも必要になります。なお、決済は銀行振込で行うのが一般的です。
STEP7:確定申告を行う
売却額によって譲渡所得(利益)が発生した場合は、翌年の確定申告が必要です。申告しなかった場合や申告が遅れた場合は追徴課税が発生することがあるので、必ず期限前に終わらせましょう。
このとき、利益となる譲渡所得の金額は以下の式で求められます
利益(課税譲渡所得金) = 収入金額 -(取得費+譲渡費用)
なお「被相続人居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(空き家特例)」のような税額の特別控除が受けられる場合は、上記の計算式からさらにその額を差し引きます。
空き家特例は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ目を通しておいてください。
家を売るまでにかかる期間目安

家の売却にかかる期間は物件の種類や立地、価格設定、さらには市場の需要動向などによって大きく左右されます。そのため、幅を持たせて数か月から半年程度を目安にするとよいでしょう。
ただ、この期間はあくまで目安で、実際は都心部や人気エリアの物件が1か月以内に成約に至ることもあれば、地方にある古い物件が半年以上売れないこともあります。需要が低い物件ほど楽観視せず、時間がかかると考えて臨みましょう。
家を売る際にかかる費用・税金
家の売却では、その過程で以下のような費用が発生します。
- 仲介手数料
- 譲渡所得税
- 印紙税
- 登録免許税
- 司法書士報酬
- リフォーム費用
最終的に手元に残る金額は、これらを差し引いたものです。それぞれの概要と求め方を見ていきましょう。
仲介手数料
仲介手数料とは、媒介契約を結んだ不動産会社に支払う報酬のことです。報酬額は、宅地建物取引業法により、売却価格ごとに以下のように上限が定められています。
| 売却価格(税抜) | 仲介手数料の上限額 |
| 200万円以下 | 5%+消費税 |
| 200万円超~400万円以下 | (売却価格 × 4% + 2万円) + 消費税 |
| 400万円超 | (売却価格 × 3% + 6万円) + 消費税 |
たとえば2,000万円の物件なら、(2,000万 × 0.03 +6万)×1.1で、72.6万円となります。
なお、この費用は売買契約が成立した際に発生するため、売却代金から支払われる形になります。
譲渡所得税
売却によって譲渡所得(利益)が出た場合、その金額に対して以下の所得税と住民税が課されます。このとき、売却をした年の1月1日現在において、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」が適用されます。
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% |
なお、譲渡所得税には居住用財産の特例や3,000万円の特別控除などの減税制度があります。あらかじめ不動産会社や税理士に相談して適用されるか把握しておきましょう。
印紙税
印紙税は売買契約書を作成する際に、契約金額に応じた収入印紙を貼付して納めます。金額は1万円以下が200円(軽減税率期間は非課税)から、100億円超が60万円となっていますが、2027年3月31日までは軽減税率により200円から48万円となっています。
登録免許税
登録免許税は所有権移転登記の際に課される税金で、住宅用家屋の所有権移転登記は、原則として不動産の価額(固定資産税評価額)の2%が登録免許税として課されますが、個人が自己の居住用として取得する場合で一定の要件を満たすと、2027年3月31日まで0.3%に軽減されます(※特定の住宅用家屋の場合にはさらに低い税率が適用されることがあります)。
一方、土地の所有権移転登記は、原則として不動産の価額の2%が課されますが、売買によるものについては2026年3月31日まで1.5%に軽減されます。
また、抵当権を抹消する登記を行う場合には、不動産1個につき1,000円の登録免許税がかかります。抵当権を設定する場合(主に買主側の負担)は、債権額の0.4%が課されますが、住宅取得資金に関する借入で要件を満たす場合、2027年3月31日までの間は0.1%に軽減されます。
また、抵当権を設定する場合は債権額の0.4%が課せられます。こちらも軽減税率があり、2027年3月31日までは債権額の0.1%となっています。
司法書士報酬
登記手続きを司法書士に依頼する場合は、その報酬が必要です。金額は登記の種類や依頼内容によって異なりますが、おおよそ5〜15万円程度が目安です。
リフォーム費用
少しでも高く売るためにリフォームやハウスクリーニングを行う場合、その費用も売却経費に含まれます。リフォーム費用の相場は以下のとおりです。
| 施工部分・施工内容 | 費用相場 |
| 間仕切りの撤去 | 7~35万 |
| キッチン | 50~150万 |
| トイレ | 20~50万 |
| 浴室 | 50~150万 |
| 洗面所 | 15~50万 |
| リビング | 15~150万 |
| ダイニング | 90~120万 |
| フローリング/床 | 60~90万 |
| 壁付けクローゼット設置 | 10~50万 |
| 屋根 | 30~200万 |
| 外壁 | 25~200万 |
| 断熱 | 50~250万 |
なお、リフォームを実施する際には、工事費が売却価格に見合っているか、事前に不動産会社などと相談しておきましょう。
家を売るときに必要な書類一覧

家の売却に必要な書類は、登記や税金、契約などにそれぞれ多くの書類が必要となります。これらが不足していると、売却の進行が滞ったり、買主からの信頼を損ねる恐れもあるので早めに用意しておきましょう。
ここでは、査定時・契約時・引き渡し時の3つのタイミングに必要な書類を紹介します。
査定時に必要となる書類
不動産会社に査定を依頼する際は、建物の構造、床面積、築年数、所有者情報などが確認できる書類が必要です。主に以下の書類が挙げられます。
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 売買契約書(購入時のもの)
- 重要事項説明書
- 建築確認済証
- 検査済証
- 物件パンフレットや間取り図(マンションの場合)
など
売買契約時に必要となる書類
売買契約を締結する際に必要な書類は売主と買主で異なります。ここでは売却時に必要な主な書類を紹介します。
- 土地・建物の登記済証
- 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 住民票(登記上の住所と現住所が異なる場合。3カ月以内の物)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 固定資産税納税通知書
- 建築確認通知書
- 検査済証
- 土地・建物に関する図面
- 付帯設備表
- 権利書
など
基本的には身分の証明と物件の情報に関する書類が必要になります。取引ごとに必要書類が変わる部分もあるので、具体的な書類は不動産会社に確認しましょう。
引き渡し時に必要となる書類
物件の引き渡し時には、鍵や設備に関する資料をまとめて買主へ引き継ぎます。一般的には次のような書類や備品が求められます。
- 振込先となる銀行口座書類
- 抵当権の抹消に関する書類
- 住民票(登記上の住所と現住所が異なる場合)
- 物件の鍵一式(スペアも含む)
- 設備の取扱説明書・保証書
- 火災報知器・給湯器などの取り扱いマニュアル
など
これらの書類は買主が大切に保管しておく必要があるので、一冊のファイルにまとめて渡すのがおすすめです。
家を高く・早く売却するための成功ポイント

ここからは、家をより有利な条件で売却するためのポイントを3つ紹介します。少しの工夫で結果が大きく変わることもあるので、ぜひ実践してみてください。
需要の高まる季節を意識する
住宅の需要は、転居が多い春(1~3月)や、会社の異動がある秋(9~11月)に高くなる傾向にあります。需要が高いと早く売れる可能性があるだけでなく、長期間売れ残って値下げをするリスクも減らせます。
クリーニングやリフォームで印象をアップする
内覧時には、新生活を気持ちよく始められる物件だと思ってもらうために、クリーニングや費用対効果が見込めるのであれば、小規模なリフォームを行いましょう。
たとえば、壁紙や照明の新調や、リビングや水回りなどの清潔感が重視される場所のリフォームなどが考えられます。
査定価格にとらわれすぎない
不動産会社を選ぶ際には、査定価格にこだわりすぎずに、サービスの良さや対応の早さなどを含めた総合力をチェックしましょう。いくら査定額が高くても、売却活動が上手く進まないと、売却までに時間がかかったり、その結果値下げが必要になったりする可能性があります。
売却時に注意すべきトラブル・リスク

最後に、家を売る際に特に気を付けるべきトラブル・リスクを紹介します。大きなお金がかかることなので、よくある困りごとを事前に把握し、損をしないように手続きを進めましょう。
古い家や空き家を売る際の注意点
築年数の古い物件や長期間放置された空き家は、どこにマイナス要因が隠れているのか分からず、買い手は不安を抱きがちです。
このような場合はホームインスペクション(建物診断)を実施し、可能な限り現状を正しく伝えるよう努力しましょう。買い手がマイナス要因を正しく把握できれば、現状に納得したうえで購入してくれる可能性があります。
さらに、必要に応じて、簡易リフォームやクリーニングなどで印象を良くする工夫も効果的です。
住宅ローンや権利関係の確認不足によるリスク
家の所有権を買い手に変更する場合は、住宅ローンの返済状況や権利関係にも気を付けましょう。住宅ローンを完済していない家には「抵当権」という、家を住宅ローンの担保にする権利が付けられており、ローンの返済が滞った場合、家を売却してローンを返済することを求められる可能性があります。
そのため、住宅ローンが残っている家を売却する場合は、あらかじめローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。資金が不足する場合には、ローンの借り換えやつなぎ融資などを利用する方法もあります。
また、権利関係でもう一点気を付けるべきなのが、名義人が複数いるケースです。売却には全員の合意が必要なので、売却手続きを進めるタイミングには十分注意しましょう。
売却後の契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)
契約不適合責任とは、引き渡し後に建物の不具合が見つかった場合に、一定の条件下で売主が修繕費を負担する義務を負う責任のことです。雨漏りやシロアリ被害、配管の不具合といった重大な欠陥が見つかった場合、あとから高額な修繕費用を請求される可能性もあります。
こうしたリスクを避けるためにも、特に古い家の場合はホームインスペクションを行い、建物の状態を十分に確認しておきましょう。
まとめ・総括:家を売る流れを理解してスムーズに売却を実現しよう
今回紹介したボリュームからも分かるように、家の売却には数多くのステップとポイントがあり、これらを一度で理解するのは困難です。そのため、本記事で全体の流れと大まかなポイントを把握し、その後は専門家に相談しながら二人三脚で進めていきましょう。
特に長期間放置された空き家のように物件に不安がある場合は、アキサポのような、そのジャンルに特化した専門家が頼りになります。不動産会社を決める際には、その会社の得意分野と実績をしっかりリサーチしておきましょう。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。








