公開日:2025.10.24 更新日:2025.10.27
不動産譲渡時の所得税を徹底解説!計算方法から特例、確定申告まで

「不動産を売却したら、どれくらいの税金がかかるのだろう?」不動産の売却を検討する際、多くの方がまず思い浮かべる疑問の一つが「税金」ではないでしょうか?特に、不動産譲渡にかかる所得税は、所有期間や適用できる特例によって税額が大きく変動するため、複雑で計算が難しいと感じる方も少なくありません。
この記事では、不動産譲渡にかかる所得税の仕組みや計算方法、そして適用できる特例制度や確定申告の流れまでを、専門家としての視点を交えてわかりやすく解説します。不動産売却を成功させるために、税金の全体像をしっかりと把握しておきましょう。
目次
不動産売却でかかる税金の基本

不動産を譲渡した際に発生する所得税は、不動産を譲渡して得た利益である「課税譲渡所得金額」に対して課されます。この「課税譲渡所得金額」とは、売却して得た金額そのものではなく、そこから売却費用や取得費用などを差し引いた、純粋な利益のことをいいます。
課税譲渡所得金額の計算式
- 課税譲渡所得金額 = 収入金額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除額
この「課税譲渡所得金額」に対して、不動産の所有期間に応じて、以下の所得税率が適用されます。
- 長期譲渡所得の場合(所有期間が5年超):15%(所得税)+5%(住民税)
- =合計20%に復興特別所得税を加算
- 短期譲渡所得の場合(所有期間が5年以下):30%(所得税)+9%(住民税)
- =合計39%に復興特別所得税(2037年12月31日まで2.1%)を加算
また、不動産を譲渡した際には、所得税に併せて以下の住民税も課されます。
- 長期譲渡所得の場合(所有期間が5年超):5%
- 短期譲渡所得の場合(所有期間が5年以下):9%
なお、2037年(令和19年)12月31日までは、上記の所得税額に2.1%の復興特別所得税が加算されます。
収入金額・取得費・譲渡費用・特別控除額とは
課税譲渡所得金額を算出するために用いられる、収入金額・取得費・譲渡費用・特別控除額とは、それぞれ以下のようなものを指します。
- 収入金額
不動産を売却して実際に得た金額。売買契約に基づく売却代金が基本であり、たとえばマンションを4,000万円で売却した場合、その4,000万円が収入金額にあたる - 取得費
不動産を購入・取得するためにかかった費用。購入時の仲介手数料や登記費用などが含まれる - 譲渡費用
売却のために直接かかった費用。仲介手数料や測量費、建物解体費、契約書に貼付する印紙代など - 特別控除額
条件を満たす場合に差し引ける金額。マイホーム売却時の3,000万円特別控除や公共事業による収用に伴う5,000万円特別控除などがある
譲渡所得の対象になるもの
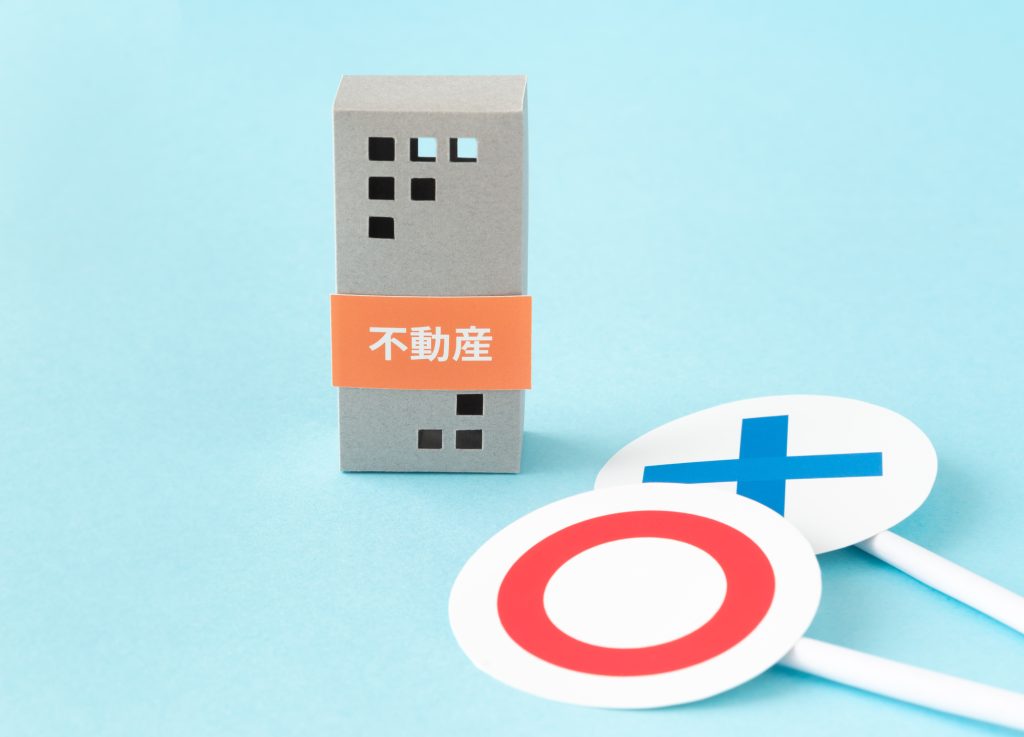
不動産の売却で得た譲渡所得の対象となる不動産と、不動産に関する権利は以下のとおりです。
- 土地
- 建物
- 借地権
基本的に、不動産の売却はすべてが対象になると考えてよいでしょう。売却の方法においても、通常の売却に加えて、交換や競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれるため、不動産を譲渡して対価を得た場合は、基本的に不動産譲渡にかかる所得税が発生すると考えましょう。
所得税の課税されない譲渡所得
不動産を譲渡した場合であっても、以下のような場合には所得税は課されません。
- 強制換価手続
国税徴収法に基づく滞納処分や、強制執行、担保権の実行(競売)、破産手続などにより資産が売却され、その代金が全額債務の弁済に充てられた場合 - 国や地方公共団体等への寄附
国・地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする法人に対する寄附で国税庁長官の承認を受けた場合 - 国等に重要文化財を譲渡した場合
文化財保護法で指定された重要文化財(土地を除く)を、国や独立行政法人国立文化財機構・国立美術館・国立科学博物館・地方公共団体などに譲渡した場合 - 相続税の物納に充てた場合
相続税を物納するために財産を譲渡した場合。ただし、物納の許可限度額を超える部分については課税対象 - 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合
中小企業の取締役等で、その法人の債務保証人となっている者が、同法人の事業用資産を令和7年3月31日までに債務処理計画に基づき贈与した場合には、一定の要件のもとで課税対象外となる
譲渡所得以外の所得として課税されるもの
不動産の譲渡に関連する所得の中には「譲渡所得」ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されるケースがあります。主な対象は次のとおりです。
- 不動産所得・山林所得・雑所得を生ずる業務を行っている場合
それらの業務に関して、棚卸資産に準ずる資産を譲渡した場合は雑所得として課税される - 山林を伐採して売却した場合や立木のまま売却した場合
山林所得として課税される。ただし、山林を取得してから5年以内に売却した場合は、事業所得または雑所得となる。なお、山林を土地付きで譲渡する場合には、土地部分は譲渡所得として扱われる
どちらも、主に事業を行っている場合に適用される条件です。自宅を売却するような個人的な譲渡の場合は基本的に該当しないと考えてかまいません。
特別控除の種類

自宅を売却する際や公共事業に関係する場合などには、不動産の譲渡によって得た譲渡所得から一定額を差し引ける「特別控除」が適用されます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
自宅売却時の3,000万円特別控除
自分や家族が住んでいた住宅を売却した場合に、最大で3,000万円の控除を受けられる制度です。居住していた住宅だけでなく、転居後3年目の年末までに売却した場合も対象になります。
たとえば、親が亡くなって空き家になった実家を売却する場合や、引っ越し後に空き家になった旧宅を売却するケースがこれに当たります。課税額をゼロにできることも多い強力な制度ですが、同一の居住用財産の譲渡については一度しか利用できない点に注意が必要です。
公共事業などに関する5,000万円の特別控除
土地収用法や、その他の法律で収用権が認められている公共事業のために不動産を売却した場合には、最大5,000万円の特別控除が受けられます。たとえば道路拡張に伴う立ち退きや、公共施設の建設による収用が該当します。
なお、本特別控除の対応には以下の2種類があります。
- 対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは、譲渡がなかったものとする特例(代替資産取得特例)
- 譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除を差し引く特例(5,000万円特別控除)
なお、公共事業による収用等の場合、これらの特例はどちらか一方のみを適用できます。それぞれ特例の効果が異なるうえに、適用するための条件も細かく指定されています。どちらを適用するか悩んだ場合は、公共事業の担当職員に確認しましょう。
特定土地区画整理事業などに関する2,000万円の特別控除
土地区画整理事業に関連して土地や建物を譲渡した場合は、最大2,000万円を控除できます。これは市街地の再整備や道路整備に伴う土地の提供などで利用されるもので、事業計画に基づいて譲渡することが条件です。通常の売買では適用されず、必ず「事業指定」があることが前提になります。
特定住宅地造成事業などに関する1,500万円の特別控除
都市再開発や宅地造成などの公共性の高い事業で土地を譲渡した場合は、最大1,500万円を控除できます。たとえば再開発区域の指定を受けたエリアの土地譲渡が典型的です。対象事業は限定されており、公告や指定を受けていない場合には適用できません。
平成21年及び平成22年に取得した土地に関する1,000万円の特別控除
平成21年または22年に取得した土地を一定期間保有し、その後に譲渡した場合には、最大1,000万円を控除できます。これは、リーマンショック後の不動産市場を活性化させるための時限的措置であり、対象者は限られます。譲渡の時期や保有期間に厳密な要件があり、適用できるかどうかは国税庁の情報で確認する必要があります。
農地保有の合理化などに関する800万円の特別控除
農地を農業委員会や農地中間管理機構のあっせんを通じて譲渡した場合、最大800万円を控除できます。これは農地の集約化や有効利用を目的とした制度で、買い手が農業従事者であることなどが条件です。譲渡先が親族や農業を営まない第三者の場合には対象にならないため、適用には事前の確認が欠かせません。
低未利用土地などに関する100万円の特別控除
都市計画区域内の市街化区域にある低未利用地(※)を活用目的で譲渡した場合には、最大100万円を控除できます。
適用される条件は、譲渡価格が500万円以下(場合によっては800万円以下)であることや所有期間が5年を超えていること、売り手と買い手が生計を共にする親族や内縁関係などの特別な関係にないことなどです。
※ 居住、事業、その他の用途に利用されていない状態で、利用の程度が周辺の地域における同一の用途やこれに類する用途に利用されている土地と比べて、著しく劣っている土地や、その土地の権利
不動産譲渡に関する所得税の特例制度

不動産譲渡に関する所得税には、特別控除の他にも、一定の条件を満たすことで税額を抑えられる特例が設けられています。控除と異なり、税率を下げたり課税を繰り延べしたりできる仕組みがあり、売却のタイミングや相続の有無によっては大きな効果を発揮します。
所有期間10年超の自宅を売却した場合の軽減税率
マイホームを10年以上所有し、一定の居住要件を満たした場合には、長期譲渡所得として扱われるだけでなく、さらに軽減された税率が適用されます。
税率は以下の式によって求められます。
| 課税長期譲渡所得金額 | 税額 |
| 6,000万円以下 | 課税長期譲渡所得金額 × 10% |
| 6,000万円超 | (課税長期譲渡所得金額 – 6,000万円)× 15% + 600万円 |
なお、課税長期譲渡所得金額は以下の式によって求められます。
- (不動産を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)- 特別控除額
なお、2037年までは、上記の税率に加えて2.1%の復興特別所得税が加算されます。
居住用財産の買い換え特例
マイホームを売却して新たに住宅を取得する場合には、課税を繰り延べできる「買い換え特例」が利用できます。この制度を使うと、売却益がすぐに課税されるのではなく、新居を将来売却する際まで先送りされるため、手元資金を確保しながら住み替えが可能になります。
譲渡後すぐに新居を購入または建築することが条件となり、適用期限や対象面積なども細かく定められているため、利用する際は必ず要件を確認しておきましょう。
相続税の取得費加算の特例
相続により取得した不動産を売却する場合には、相続時に支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度が利用できます。取得費を大きくできれば譲渡益が小さく計算されるため、結果として納税額を軽減できます。
特例を受ける条件は以下のとおりです。
- 相続や遺贈により財産を取得した者であること
- その財産を取得した人に相続税が課税されていること
- その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
また、取得費に加算できる額は下記の式によって求められます。
- その者の相続税額 × その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされた譲渡した財産の相続税評価額 / その者の取得財産の価額 + その者の相続時精算課税適用財産の価額 + その者の純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産の価額
また、適用を受けるには必要書類を整えて確定申告を行うことが必要になります。
不動産譲渡に関する所得税の計算方法

解説した各制度を踏まえて、実際に不動産を譲渡した場合の所得税を計算してみましょう。所得税の計算は以下の5ステップで行います。
- 1.収入金額・取得費・譲渡費用・特別控除額をまとめる
- 2.課税譲渡所得金額の算出
- 3.短期譲渡所得と長期譲渡所得の確認
- 4.特例措置の適用
- 5.税額の算出
1. 収入金額・取得費・譲渡費用・特別控除額をまとめる
まず、譲渡所得を求めるための数値を整理します。今回は自宅を売却した場合として、下記の条件を仮定しました。
- 収入金額:6,000万円
- 取得費:2,200万円(購入代金2,000万円、仲介手数料や登記費用200万円)
- 譲渡費用:200万円(仲介手数料、測量費、印紙代など)
- 特別控除額:3,000万円(自宅売却時の3,000万円の特別控除)
- 所有期間:25年
2. 課税譲渡所得金額の算出
次に、整理した数値を用いて「課税譲渡所得金額」を計算します。実際に計算する前に、計算式をおさらいしておきましょう。
- 課税譲渡所得金額 = 収入金額 −(取得費 + 譲渡費用) − 特別控除額
なお、取得費が不明な場合には、売却代金の5%を概算取得費として計算できます。
この式に先ほどまとめた金額を当てはめると以下のようになります。
- 課税譲渡所得金額 = 6,000万円 - (2,200万円 + 200万円)- 3,000万円 = 600万円
よって、この場合は600万円に対して所得税が課されることになります。
3. 短期譲渡所得と長期譲渡所得の確認
課税譲渡所得が出たら、所有期間が5年以下か5年を超えているかで「短期」か「長期」に区分します。
今回は所有期間が25年のため長期譲渡所得に該当し、譲渡税率は15%が適用されます。
4. 特例措置の適用
具体的な税額を算出する前に、特例措置が適用できるかを確認しましょう。今回は所有期間が25年の自宅を売却したため、所有期間10年超の自宅を売却した場合の軽減税率が適用できます。
この特例は課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下か、それを超えるかで区分されています。今回は6,000万円以下のため、下記の式が適用されます。
- 課税長期譲渡所得金額 × 10%
5. 税額の算出
最後に、譲渡所得税を算出する式に実際の数値をあてはめて計算を行います。今回は特例措置が適用されているため、下記の式が適用されます。
- 600万円 × 10% = 60万円
まとめ・総括
不動産譲渡に関する所得税は、売却益が出た場合に避けられない税金ですが、制度を知っているか否かで実際の負担が大きく変わってきます。特に短期譲渡と長期譲渡の違いは税率が大きく違うので、最初に把握しておきたいところです。
マイホームを売却する際の3,000万円特別控除や、相続時の取得費加算の特例を使えば、さらに課税額を抑えられる可能性があります。多額の税金が動く取引だからこそ、専門家に相談して最適な制度を選び、負担を最小限に抑える方法を探しましょう。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。








