公開日:2025.11.13 更新日:2025.10.29
古民家のリノベーション完全ガイド|費用・手順・注意点を徹底解説

古民家リノベーションは、伝統的な木造建築を活かしながら、快適で機能的な住まいへと再生する方法です。地方移住の広がりやサステナブルな暮らしへの関心が高まるなか、古民家の再生は「新しい暮らし方」として多くの人に選ばれています。
一方で、実際に取り組もうとすると「どんな手順で進めるのか」「費用はどのくらいかかるのか」「どんな準備が必要なのか」など、分からないことも多いもの。
そこで本記事では、古民家リノベーションの基礎知識から費用の目安、物件探しのコツ、補助金の活用方法までを解説。理想の古民家暮らしを実現するためのヒントをお届けします。
目次
古民家リノベーションとは?魅力と注目の背景

歴史を感じる佇まいと、木の温もりに包まれた空間。そんな古民家を自分らしい住まいへと再生する古民家リノベーションが、今、注目を集めています。
そこでまずは、古民家の定義から注目が集まる背景、リノベーションとリフォームの違いについて詳しく見ていきましょう。
古民家とは?住宅の定義と見分け方
古民家とは、一般的に築50年以上経過した木造住宅で、厳密な法的定義はありませんが、「古民家再生協会」の定義では昭和25年(1950年)以前の伝統構法によって建てられたものを指すことが多いです。太い梁や柱、土壁・漆喰壁、釘を使わずに木材を組む「木組み」など、職人の手仕事が活きる構造が特徴です。茅葺き屋根や瓦屋根、縁側、蔵付きの間取りなども見られます。
地域の風土に合わせた工夫が随所にあり、自然素材が持つ温かみも魅力のひとつ。中古住宅の中でも、こうした伝統建築技術が残る家屋が古民家リノベーションの対象になります。
なぜ今「古民家リノベーション」が注目されているのか
古民家リノベーションが脚光を浴びている背景には、暮らし方や価値観の変化があります。
まず、テレワークの普及により地方移住を選ぶ人が増え、自然と共に暮らす古民家生活への関心が高まりました。また、環境意識の向上です。新築よりも既存建物を活かすことで廃材を減らし、資源を有効に活用できるため、SDGsの観点からも評価されています。
さらに、地域活性化の起点となる点も見逃せません。空き家となった古民家をカフェや宿泊施設として再生することで、人と人とがつながる新たなコミュニティが生まれています。こうした多面的な価値が、古民家リノベーションブームの背景にあるのです。
リノベーションとリフォームの違い
リフォームは老朽化した部分を元に戻す修繕が中心で、畳の張り替えや壁紙の交換など比較的小規模な工事を指します。一方で、リノベーションは住まい全体を刷新し、新たな価値を生み出す大規模な改修のこと。
古民家の場合は、耐震補強や断熱改修を行いながら、現代的なキッチンやバスルームを導入するなど、快適に暮らせるよう性能を高めるケースが一般的です。文化的価値を継承しつつ、住まいとしての機能を再構築すること、それが古民家リノベーションの意義ともいえるでしょう。
古民家リノベーションのメリット・デメリット
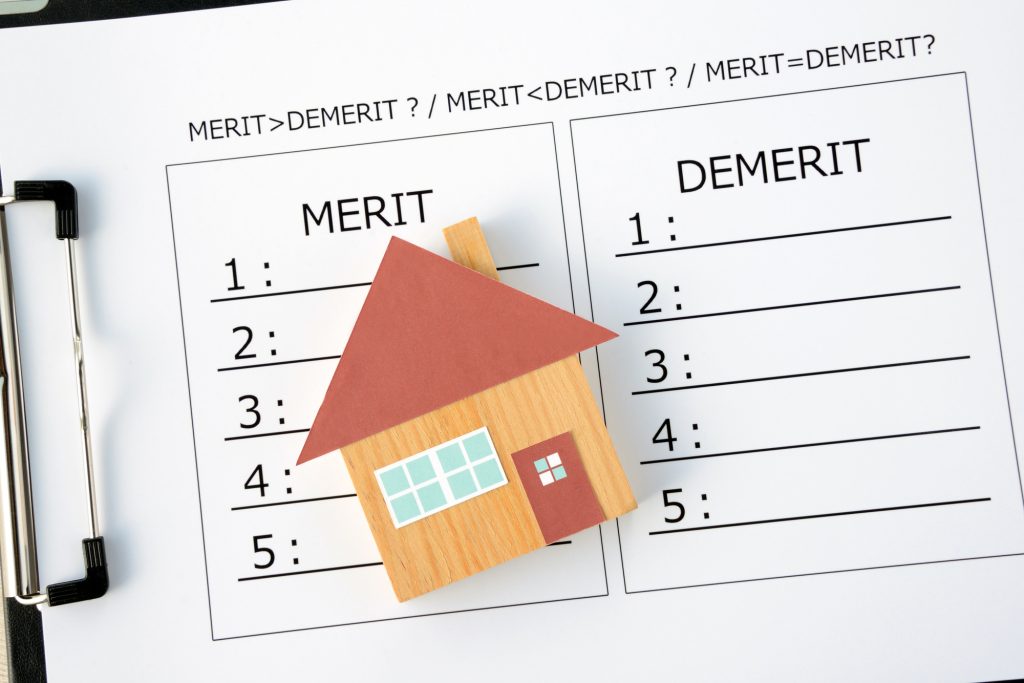
古民家リノベーションには、他にはない風情と温もりがある反面、住み心地や費用など、考慮すべき課題も少なくありません。憧れだけで進めるのではなく、メリットとデメリットの両面を理解し、自分の理想の暮らしに合うかを見極めることが重要です。
古民家の魅力とは?
古民家リノベーションの大きな魅力は、何といってもその“味わいのある佇まい”ではないでしょうか。
太く力強い梁や柱、年月を重ねて深みを増した木の色合い、手仕事による土壁の質感など、現代の建築では再現できない味わいが随所に見られます。伝統構法によって釘を使わずに組まれた木組みは、職人の技が光る構造美。柔軟性があり、地震の揺れを吸収する特性を持つともいわれています。
また、自然素材で建てられた古民家は、調湿性や通気性にも優れ、化学物質をほとんど使わない健康的な住環境を実現できます。さらに、広い土間や縁側、蔵など、昔ながらの空間を活かすことで、暮らし方の自由度がぐっと広がります。カフェやギャラリー、民泊として再生すれば、住まいを「暮らしと仕事の場」として活用することも可能です。
住み心地や耐震・断熱などの課題点
一方で、古民家は現代の住宅と比べると、快適性や安全性の面で改修が必要になることもあります。
特に注意すべきは耐震性能です。多くの古民家は現行の建築基準法が施行される前に建てられており、耐震診断の結果、補強が必要とされるケースが少なくありません。特に昭和56年(1981年)6月1日以前の建物は「旧耐震基準」のため、新耐震基準に適合させるための補強工事はほぼ必須といえるでしょう。
断熱性の低さも課題のひとつです。風通しを重視した造りのため、冬は冷え込みやすく、暖房効率が下がることがあります。快適に暮らすためには、断熱材の施工やサッシ交換などの性能向上が欠かせません。
加えて、水回りの老朽化やシロアリ被害、雨漏り、電気・配管設備の交換も必要になる場合があります。これらの修繕にはまとまった費用がかかるため、事前に見積もりを取り、しっかりと資金計画を立てることが大切です。さらに、伝統構法を理解した職人や地元工務店が減少しているという人材面での課題もあります。
メリット・デメリットを踏まえた判断のコツ
古民家リノベーションを成功させるには、メリットとデメリットを冷静に比較し、自分にとって何が優先事項かを明確にすることが大切です。
歴史ある建物に暮らす喜びや、地域に根ざした暮らしに魅力を感じる方にとって、古民家はかけがえのない存在になります。多少の不便さや費用を「味わい」や「価値」として受け入れられるかがポイントです。
また、リノベーションは新築より費用や時間がかかる傾向があります。想定外の修繕が発生することもあるため、余裕を持ったスケジュールと予算設定が欠かせません。自治体によっては補助金や移住支援制度が利用できる場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。
そしてもう一つ大切なのが、地域との関わり方です。古民家はその土地の歴史と文化に支えられてきた建物。地域の人々との関係を築きながら暮らす姿勢が、長く快適に過ごすための鍵となります。
リノベーションの流れと必要な手続き

古民家リノベーションを成功させるには、計画的なステップを踏むことが重要です。物件探しから施工完了まで、各段階で押さえておくべきポイントと必要な手続きについて解説します。
物件探しと現地調査のポイント
気になる古民家を見つけたら、まずは必ず現地調査を行いましょう。写真や資料だけでは分からない建物の劣化具合や構造的な問題を、実際に確認することが重要です。
チェックすべき点は、基礎や土台のひび割れ、柱や梁の腐食・シロアリ被害、床の傾きや建物の歪みなど。屋根や外壁、雨漏りの有無、給排水設備の老朽化も見逃せません。
加えて、敷地条件や日当たり、周辺環境、上下水道やガスの引き込み状況も確認しておくと安心です。こうした調査は、専門家による耐震診断を受けることで、より正確に現状を把握できます。
設計・プランニングの進め方
まずは「どの部分を残し、どこを新しくするか」を明確にしましょう。伝統的な梁や欄間など、古民家の個性を感じられる意匠はできるだけ残しつつ、耐震補強や断熱性の向上といった安全面にはしっかりと投資を。間取り変更は、伝統構法の構造を理解したうえで慎重に検討する必要があります。壁を取り払うと強度が落ちることもあるため、経験豊富な設計士や工務店に相談しましょう。
また、キッチンやバスルームなどの水回り、床暖房や空調などの設備計画もこの段階で検討しましょう。DIYを取り入れる場合は、どの範囲を自分で行うかを事前に業者とすり合わせておくとスムーズです。
補助金・助成金の活用で費用を抑える
古民家リノベーションでは、国や自治体が実施する補助金・助成金制度を利用できる場合があります。
代表的なものに「長期優良住宅化リフォーム推進事業」があり、耐震性・省エネ性の向上を伴う工事に対して最大で数百万円の補助を受けられることもあります。
また、地方移住や地域活性化を目的とした補助金も多く、空き家活用や古民家再生を支援する自治体の制度も増えています。民泊やカフェ、宿泊施設などの事業用途であれば、創業支援補助金が活用できるケースもあります。
ただし、補助金の多くは「工事着工前の申請」が条件です。事前に要件を確認し、設計段階から補助金活用を見据えた計画を立てることが大切です。(補助金・助成金の利用には、それぞれの要綱に定められた資格要件や申請期間、交付決定後の手続きなどが厳格に定められています。必ず各制度の公募要領を確認し、専門家にご相談ください。)
施工から完成までの期間と流れ
古民家リノベーションの工事期間は、規模や内容により異なりますが、一般的には4か月〜1年ほどが目安。部分的な改修なら数か月で終わることもありますが、耐震補強や断熱改修を含む全面リノベーションでは、半年〜1年を想定しておくと安心です。
① 解体・確認のステップ
まずは古い内装材や設備を撤去し、骨組みや基礎の状態を確認します。長年の使用による劣化やシロアリ被害が見つかることもあるため、予備費を確保しておくのがポイントです。
② 構造・設備工事のステップ
次に、耐震補強や基礎の補修など建物の安全性を高める工事を実施。続いて、断熱材の施工や配管・配線の交換、水回り設備の設置など、見えない部分の工事を進めます。
③ 仕上げ・検査のステップ
内装や建具の取り付け、照明・キッチン設備の設置などを行い、住まいとしての形が整います。工事中は定期的に現場を訪れ、色味や仕様を確認しましょう。完成後には法的検査や補助金の報告も必要です。
不安な点があれば、経験豊富な工務店や専門家に相談するのがおすすめです。
古民家リノベーションの費用相場と内訳

古民家リノベーションを検討する際、多くの方が最初に気になるのが費用の部分です。築年数や建物の構造、劣化の程度、どこまで改修するかによって金額は大きく変わります。ここでは、古民家リノベーションの一般的な費用相場と、工事内容ごとの費用内訳について解説します。
築年数・構造による費用の目安
古民家リノベーションの費用は、建物の状態や構造によって大きく変わります。一般的には坪単価30〜80万円前後、延床40坪なら約1,200〜3,200万円が目安です。
<築年数で見る費用の違い>
築50〜70年程度で構造がしっかりしている古民家は、比較的コストを抑えやすい傾向があります。一方、築100年以上経つ建物や、茅葺き屋根・蔵付き物件などは、修繕箇所が多く専門技術も必要なため、高額になりやすいです。
<構造による費用の違い>
柱や梁で支える在来工法の家は現代技術で対応しやすく、費用も安定します。対して、伝統構法による古民家は、専門職人の技が不可欠なため施工費が上がる傾向です。
ただし、伝統構法の建物は文化的価値が高く、丁寧に再生すれば長期的な資産価値として残せます。費用面だけでなく、将来的な資産価値や維持コストも含めて総合的に検討することが重要です。
費用を左右する主なポイント(耐震・断熱・間取り変更など)
古民家リノベーションの費用は、工事内容や改修範囲によって大きく変わります。なかでも特に影響が大きいのが、耐震補強・断熱改修・間取り変更です。
①耐震補強工事
安心して暮らすために欠かせない工事で、200万〜500万円ほどが目安です。基礎補修や金物の追加など、建物の骨格を強化する工事を優先的に検討しましょう。
②断熱改修工事
床・壁・天井への断熱材施工や窓の交換で、300万〜600万円ほどかかります。初期費用はかかりますが、冷暖房効率が上がり、長期的には光熱費の節約にもつながります。
③間取り変更工事
壁の撤去や水回りの移動を伴う場合は200万〜500万円ほど。一方で、既存の間取りや古材を活かせばコストを抑えられます。
予算別に見るリノベーションの実例イメージ
【1,500万円前後】
基本的な耐震補強と水回りの刷新、最低限の断熱工事を行い、内装は部分的に仕上げるケースが中心です。古材の味わいを活かしながら安全性を確保でき、DIYを取り入れることでコストを抑えつつ愛着のある住まいづくりが可能です。
【2,500万円前後】
耐震・断熱の両方をしっかり強化し、間取り変更や水回りの全面リニューアルも実施できるバランスの良い予算帯です。快適性とデザイン性を両立しつつ、古民家らしい趣を残した再生が叶います。多くの古民家リノベーションがこの価格帯で行われています。
【3,500万円以上】
伝統的な左官技術や木組み修復など、本格的な再生プロジェクトが可能な予算帯です。茅葺き屋根の葺き替えや蔵のリノベーションなど、文化財級の建物にも対応できます。古民家カフェ・宿泊施設としての活用も視野に入れられるほか、長期的な資産価値を高める投資としても魅力的です。
リノベーション向き古民家を探す方法

理想の古民家リノベーションを実現するための第一歩は、適切な物件探しから。古民家はどこで探せばよいのか、選ぶ際のポイントは何か、詳しく解説します。
古民家はどこで探す?|空き家バンク・専門サービスの活用
古民家を探す最も一般的な方法は、自治体が運営する空き家バンクを利用することです。地域の空き家情報が掲載されており、移住支援制度や補助金情報とあわせて確認できるのが特徴。現地見学ツアーや移住相談会などを通じて、地域の雰囲気を体感できる機会もあります。
また、一般の不動産ポータルサイトでも「古民家」「築古物件」などのキーワード検索で候補を見つけることが可能です。ただし、掲載情報だけでは建物の状態や周辺環境を把握しづらいため、現地確認は必須です。
古民家・空き家再生の専門サービスの活用もおすすめです。希望条件に合う物件紹介はもちろん、現地調査や補助金申請、施工会社の紹介までトータルでサポートしてくれます。地域密着のネットワークを活かし、空き家バンクには載っていない“掘り出し物件”に出会えることもあります。地元不動産会社や地域住民とのつながりを通じて、思いがけない物件情報が見つかることも少なくありません。
古民家選びのチェックポイント|構造・法規・文化的価値を確認
古民家を選ぶ際は、建物の状態を総合的に確認することが大切です。見た目だけで判断せず、以下のポイントをチェックしましょう。
□構造の状態
基礎や土台にひび割れや沈下がないか、柱や梁に腐食・シロアリ被害がないかを確認します。傾きがある場合は、修繕費が想定以上にかかることもあります。
□耐震性能
古民家は現行基準を満たしていないことが多いため、専門家による耐震診断を受けて補強の必要性を把握しましょう。診断結果によっては補助金対象になる場合もあります。
□外装・設備・法規
屋根や外壁の劣化、雨漏り跡、給排水設備の老朽化をチェック。さらに、建築基準法上の接道義務や特定行政庁による再建築可否など法的制限の確認も欠かせません。
□文化的価値
伝統構法や古材、欄間、格子戸など地域の意匠が残る家は、リノベーションによってより味わい深い住まいになります。
地域選びのポイント|暮らしやすさと地域との相性を見極める
古民家リノベーションでは、建物の魅力だけでなく、その地域で暮らすことを前提とした視点も大切です。
まず確認したいのが生活インフラ。スーパーや病院、学校、交通機関の利便性、上下水道やガス、通信環境など、生活基盤が整っているかをチェックしましょう。特にテレワークを想定する場合、インターネットの安定性は必須条件です。
気候や自然環境も見逃せません。豪雪地域では除雪作業や冬季光熱費が、沿岸部では台風や浸水リスクが生活に影響します。その一方で、四季の移ろいを間近に感じられる自然環境は古民家暮らしの大きな魅力でもあります。
地域コミュニティとの関係性も、暮らしの満足度を左右するポイントです。地域行事への参加が求められる場所もあれば、移住者を温かく受け入れる風土を持つ地域もあります。実際に現地を訪れ、地域の人々と会話をしてみると雰囲気がつかめるでしょう。
古民家をカフェや宿泊施設として活用する場合は、その地域の観光資源や集客力も事前にリサーチが必要です。町おこしに積極的な自治体では、補助金やビジネス支援が受けられるケースもあります。(カフェや宿泊施設として営業するには、食品衛生法、旅館業法などの許認可が必要になるため、事前に所管の行政機関にご相談ください。)
まとめ|理想の古民家暮らしをアキサポと実現しよう
古民家リノベーションは、ただの改修ではなく「過去と未来をつなぐ再生」です。伝統構法の美しさや自然素材の温もりを活かしながら、自分らしい暮らしを形にできます。
一方で、耐震補強や断熱改修など専門的な対応も必要です。補助金制度を上手に活用し、信頼できる専門家と計画的に進めましょう。
アキサポで理想の古民家リノベーションを実現
アキサポでは、空き家活用や古民家再生をワンストップでサポートしています。物件探しから補助金申請、専門家の紹介、リノベーション計画まで、あなたの理想を形にするための最適なプランをご提案します。地域の魅力を生かした新しい暮らし方を、専門チームと一緒に始めてみませんか?
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。








