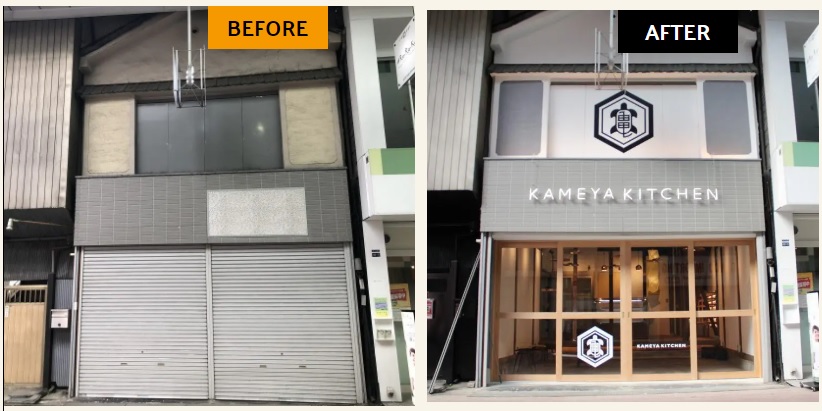公開日:2025.07.20 更新日:2025.09.16
【完全ガイド】家を建て替える流れ・費用・リフォーム比較を徹底解説

古くなった家を安全・快適にリニューアルする「建て替え」。関心はあるものの「どのように進めればよいかわからない…」という方のために、本記事では建て替えの基本を徹底解説します。新築やリフォームとの違いから、建て替えの流れや費用の内訳、失敗を避けるポイント、住宅ローンや仮住まいの手配まで、幅広くご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
家を建て替えるタイミングとリフォームとの違い

まずは建て替えと新築、リフォームの基本的な違いや、それぞれのメリット・デメリットを理解しておきましょう。
建て替えと新築、リフォームの定義
建て替えと新築、リフォームには、主に以下のような違いがあります。
| 建て替え | 既存の建物を解体して新たに家を建築すること |
| 新築 | 更地の状態から一から建物を建てること |
| リフォーム | 基礎や構造部分を残しながら部分的に改修を行い、住環境を向上させること |
それぞれに特徴や負担の大きさが異なるため、住宅の老朽化度合い、耐震性の確保、住宅環境の快適性などを踏まえ、多角的に検討するようにしましょう。
建て替えのメリット・デメリット
建て替えは、新築同様の性能・設備を導入できるため、耐震性や省エネ性を大きく向上しやすい点が最大のメリット。自由度の高い間取りやデザインを採用できるほか、将来の家族構成やライフスタイルを見据えた家づくりが可能になります。
一方で、解体費用や仮住まいへの引っ越し費用がかかるなど、リフォームに比べて初期コストが高額になりやすいというデメリットがあります。
リフォームのメリット・デメリット
リフォームのメリットは、費用を抑えられるところ。建物の基礎や骨組みを残しながら改修するため、解体工事や大規模な入れ替えが必要ありません。また、税金面での負担も比較的軽いうえ、住み替えも最小限にしながら施工できる可能性があります。
ただし、建物の構造的な制約が大きい場合や、築年数が相当経過している場合はリフォームが難しく、期待どおりの性能向上を得られないケースもあるため注意が必要です。
建て替え前に知っておきたい建築基準法と注意点

家を建て替える際には、建築基準法などの法令や各自治体の条例、既存の建物の状態を事前にしっかりと調べておくことが不可欠です。ここでは、主な注意点を2つご紹介します。
再建築不可物件や既存不適格建築物に要注意
古い家や法改正前に建てられた家の場合、現在の建築基準法を満たしていない可能性があります。特に建築基準法上の接道義務(建築基準法第43条)を満たしていない物件は再建築不可物件と判断されるケースが多く、そもそも建て替えが認められないこともあるため、注意が必要です。
既存不適格建築物の場合も、規模や仕様によっては改築が制限されるため、まずは専門家に調査を依頼し、可能かどうかを見極めるようにしましょう。
セットバックや斜線制限などの規制
狭い道路に面する土地の場合、セットバック(建築基準法第42条2項道路など)が必要となり、建物を道路境界から一定距離後退させなくてはなりません。また、周辺環境や景観を守るために、斜線制限や高さ制限がかけられている地域も存在します。
こうした規制は家のデザインや階数に影響を与えやすいため、早い段階で把握しておくことが重要です。
家を建て替える時期の目安

どのタイミングで家を建て替えるべきかは、主に「築年数」と「ライフスタイルの変化」を目安に判断されることが多いです。それぞれ具体的にどのように考慮すべきなのか、詳しく見ていきましょう。
築年数・耐用年数から考える
耐用年数は、一般的に木造住宅は30年前後、鉄骨造やRC造の場合は40年以上が目安。耐用年数を過ぎてもメンテナンス状況によっては使い続けられる場合がありますが、床や屋根、配管などが老朽化してトラブルを引き起こすリスクが高まるため、建て替えを検討する良いタイミングといえます。
さらに、不動産の資産価値の観点でも、住宅ローンの残債や固定資産税、今後発生するであろう修繕費を総合的に比較し、建て替えで得られるメリットが上回るのかを検討することも重要です。
家族構成やライフスタイルの変化
子供が独立することで部屋数が余る、親との同居でバリアフリー設計の家が必要になるなど、住まい方はライフステージによって大きく変化するものです。このようなタイミングで、間取りや設備を一新することは、長期的に見てコストパフォーマンスが高い選択肢となり得ます。
家を建て替える全体の流れ

建て替えには大まかに7つのステップがあります。計画段階から竣工後の手続きまで、一通りの流れをチェックしておきましょう。
1. 資金計画と住宅メーカーの検討
家を建て替えるときに最初に行うのが、予算の確認と資金計画の立案です。自己資金だけでは足りない場合、住宅ローンやつなぎ融資を検討し、毎月の返済額や返済期間をシミュレーションします。
そのうえで複数のハウスメーカーや工務店から話を聞き、建築実績や提案内容を見比べて最終的な依頼先を決定するのがおすすめ。住宅メーカーによって対応範囲や得意分野が異なるため、じっくり比較・検討してから選ぶことで、満足のいく建て替えにつながりやすくなります。
2. 敷地調査と設計プランの打ち合わせ
次に行うのは、敷地の形状や高低差、法規制の確認などです。隣家との境界線や接道条件などの確認をきちんと行い、希望する間取りや外観デザインに支障が出ないかをチェックします。家族構成や生活スタイルに合わせたプランを提出してもらいながら、耐震性能や使い勝手を十分に考慮した設計を詰めていくようにしましょう。
3. 見積もり比較と建築請負契約の締結
設計案をもとに複数社から見積もりをとり、工事費や付帯工事の内容、保証制度の差を確認します。金額だけでなく、アフターサービスや保証期間、そのメーカー独自の技術などの確認も忘れずに。もっとも納得できる条件の候補先を選定したら、計画内容を再確認しつつ建築請負契約を正式に結びます。
4. 仮住まいへの引っ越し
建て替え工事の間はもとの家に住めないため、仮住まいの確保が必要です。賃貸物件を借りるのか、それとも実家や親戚宅に一時的に居住できるのかを早めに検討するようにしましょう。
引っ越し費用や荷物の保管場所など、思いのほか出費が増えることがあるので、当初の予算に組み込んでおくこともポイントです。
5. 解体工事・地盤調査
家屋を取り壊す際には、近隣に騒音や振動の影響が及ぶため、トラブル防止のためにも着工前にあいさつ回りをしておくのがおすすめ。
解体作業が終わったら地盤調査を行い、必要に応じて地盤改良を施すかどうかを判断します。地盤の弱い土地では、改良工事に追加費用がかかる場合もあるので、見積もり段階でしっかりと確認しておきましょう。
6. 新築工事の着工と進捗管理
基礎工事が始まったら、施主も定期的に現場を見に行って工程を確認しましょう。雨天や資材の手配など、工期に影響を及ぼす要因もあるため、問題があれば早めに担当者に連絡し、軌道修正しておくことが大切です。
7. 竣工・引き渡しと登記手続き
建物が完成したら、施主検査で仕上がりを確認し、不具合や修正点があればをまとめて改善を依頼。すべてに納得がいったら正式に引き渡されます。
そして、完成後に必ず行っておかなければならないのが、登記手続きです。建物の表題登記、所有権保存登記、住宅ローン利用時の抵当権設定登記などは早めに行いましょう。また、固定資産税の課税対象や不動産取得税など、税金に関わる部分の変更や、火災保険・地震保険の再契約なども、怠ると後々のトラブルにつながるため、手続きは必須です。
家を建て替える費用の内訳

解体作業費から新築工事費、各種手続きに伴う手数料まで、多岐に渡る建て替え費用。具体的にどのような費用が発生するのか、主な内訳をご紹介します。
解体費用
解体費用は建物構造や立地条件、延床面積などによって異なりますが、一般的には1坪あたり2〜5万円程度が目安。アスベストや特殊な材料を含む建物は追加工事費がかかる可能性があるため、調査の段階でどのような追加費用が発生するか、ある程度の目安を把握しておくと安心です。
また、工期が長引くと人件費もかさんでしまうため、解体業者としっかり打ち合わせしたうえで効率的なスケジュールを組むようにしましょう。
新築工事費用
新築工事費用は、建物の構造(木造、鉄骨造、RC造など)や間取りのほか、デザイン性の高い設備や素材の使用、高性能な断熱材や太陽光発電システムといったオプションの導入など、設備のグレードによっても差が出ます。
これらは初期費用が大きい反面、長期的には光熱費の節約や家の資産価値向上に寄与する面もあるため、どこまでこだわるかは予算を考慮しながら検討することが大切です。
諸費用(税金・ローン諸費用など)
建て替えでは工事費だけでなく、各種手続きにかかる費用も考慮しておかなくてはなりません。
<主な費用例>
- 建物の表示登記、所有権保存登記費用
- 住宅ローンの事務手数料
- 火災保険料
- 地震保険料
- 不動産取得税
- 印紙税
- 登録免許税
- その他、各種専門家への報酬(司法書士、土地家屋調査士、税理士など)
建て替えの際は、工事費以外の費用も検討した上で予算を立てておくことで、想定外の出費によるトラブルを防ぐことができるでしょう。
家を建て替える費用を抑えるためのポイント

高額な費用がかかる建て替えですが、計画の立て方や工事の内容次第でコストを抑えることが可能です。建て替え費用の節約ポイントを4つご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
ハウスメーカー選びと複数社比較
建て替えの費用を抑えるには、まず複数のハウスメーカーや工務店を比較し、それぞれの強みや価格帯を見極めることが基本です。メーカーごとに費用構成や採用する建材、デザインや施工品質などは異なるため、複数の見積もりを取り寄せ、比較・検討してみましょう。アフターサービスの有無や保証期間の長さも含めて、総合的にコストパフォーマンスを検討すると失敗を減らせます。
シンプルな設計と無駄のない間取り
建物の形状が複雑になればなるほど、施工工程や材料費は増えがちに。例えば、平屋や総2階など、四角形に近いシンプルなプランを採用することで、材料の切り出しロスを減らせるうえ、施工期間の短縮にもつながります。
将来的なライフスタイルの変化も考えつつ、できるだけ汎用性の高い空間づくりにすることが、運用コストを含めた節約を実現しやすくなるでしょう。
補助金・助成金の活用
耐震性向上や省エネルギー性能の高い家は、国や自治体から補助金や助成金の対象になることがあります。「地域型住宅グリーン化事業」「こどもエコすまい支援事業」などの省エネ住宅ポイントや各種補助制度は、年度や地域によって内容が異なるため、最新情報を早めに収集しておきましょう。
リフォームとの比較検討
老朽化が進んでいない部分や構造体に問題がない場合は、大規模リフォームで対応できることもあります。「建て替えが本当に必要か」を社外や第三者の専門家に相談すれば、客観的なアドバイスを得やすいでしょう。リフォームと建て替えのメリットや費用感を整理し、現状に対して最も効果的な選択をすることが理想的です。
建て替え工事中の仮住まい手配と住宅ローン

建て替え期間中は仮住まいが必要になるケースが大半です。また住宅ローンの借り方や保険の契約についても、新築より複雑になることがあります。このような、建て替えならではのケースにどのような対応を取るべきなのか、詳しく見ていきましょう。
仮住まい探しのポイントと注意点
建て替え工事に着手すると、解体から完成までの間は本来の家に住むことができません。賃貸物件やウィークリーマンションなど一時的な居住先を確保する必要がありますが、引っ越し代や二重の家賃が発生するため、当初の予算に組み込んでおくことが重要です。
また、工期延長などで仮住まいの期間が伸びるリスクもあるため、契約期間に余裕をもたせておくと安心できます。
つなぎ融資と親子リレーローン
住宅ローンの面では、つなぎ融資や分割融資など、新築のローンと比べて複雑な手続きが発生する場合があります。特に、親との共同名義などで親子リレーローンを利用する場合、世代を超えて資産を活用できるというメリットがある一方、手数料や金利が異なることも。
建物の完成時期がずれると融資のタイミングにも影響が出るため、複数の金融機関で比較検討のうえ十分な話し合いを重ね、返済計画を綿密に確認・検討することをおすすめします。
火災保険・地震保険の再契約
火災保険や地震保険は、解体時に一旦解約し、新築工事完了後に改めて契約を結ぶのが一般的。ただし、工事中の災害や事故など、建築段階でのリスクが心配な場合は、工事保険(建設工事保険など)や施工会社の保険に加入するケースも見られます。
各保険料は契約内容や補償範囲によって異なるので、保険会社や施工会社とよく相談しながら決定するようにしましょう。
建て替えでよくある失敗例と対策
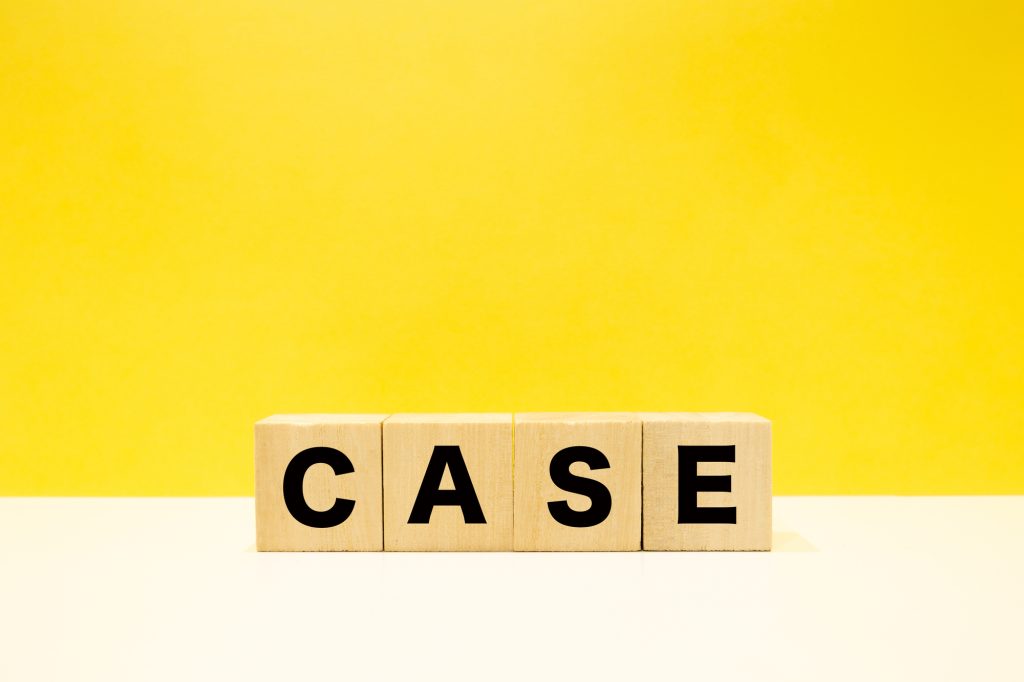
せっかく建て替えを行うなら、想定外の費用や工期の遅れ、完成後の不満などは避けたいもの。よくある失敗例をご紹介するので、ぜひ参考にして事前に対策を打っておきましょう。
スケジュールのずれによる追加費用
天候不良や設計変更、資材不足などが重なって工期が延びると、その分だけ仮住まいの家賃やローンの利息などの負担が増えます。特に引っ越し業者や解体業者とのスケジュール調整にミスがあると、追加料金を支払う事態になりかねません。
こうしたトラブルを防ぐためには、まずは施主と施工会社、設計士の三者がコミュニケーションを密に取り合うことが必須。さらに、地盤調査や配管の老朽化など潜在的なリスクを事前に洗い出し、余裕のある予算設定を行っておくことも重要です。
また、施工期間中は定期的に現場を確認することもポイント。違和感や疑問点があれば早めに共有・相談することで、大きなトラブルを回避し軽微な修正で済ませやすくなります。
収納不足・導線の悪さ
建物の基本設計において、収納スペースや生活動線が十分に検討されていないと、住み始めてからストレスを感じてしまうことも。特にファミリー世帯など複数人で暮らす場合、荷物の置き場所や部屋間の移動ルートが効率的かどうかは快適性に大きく関わります。仮住まいや完成見学会などで他の住宅を見学し、使い勝手を事前にシミュレーションしておくとよいでしょう。
よくある質問FAQ

建て替えを検討する際によく挙がる質問を、3つピックアップしてご紹介します。
Q1: 住宅ローンはいつ・どのように借りる?
建築請負契約を結んだタイミングや工事の進み具合に合わせて、分割融資を受けるケースが一般的です。つなぎ融資は初期の解体費用や着工時の支払いなどに充てられるため、工事期間中の資金ギャップを埋める役目を果たします。ローンの種類や返済プランによって条件が異なるため、早めに金融機関と相談してシミュレーションしておくとよいでしょう。
Q3: 設計変更は契約後も可能?
契約後でも設計変更は可能です。ただし、大幅なプラン変更や仕様追加があると、追加費用や工期延長が生じることがあります。極力変更がないよう契約前に細かく確認しておくことが前提ですが、万が一間取り変更などが発生した場合はすぐに担当者に連絡し、費用やスケジュールの見直しを行うようにしましょう。
Q4: 火災保険の選び方は?
建て替えの火災保険料は、建物の構造や立地条件によって決まります。柱や壁の素材、耐火性能の高さ次第で割安になる場合もあるため、複数の保険会社を比較検討するのがおすすめ。地震保険の付帯も含めて検討し、万が一の災害時に十分な補償を受けられるようにしておきましょう。
まとめ
家の建て替えはリフォームよりも大きな負担と時間がかかりますが、長期的な安心と快適さを得られるのが魅力。必要な情報を十分に収集したうえで、工期の見通しや近隣とのコミュニケーション、住宅ローンの計画まで多角的に準備を進め、理想のマイホームをスムーズに手に入れましょう。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。