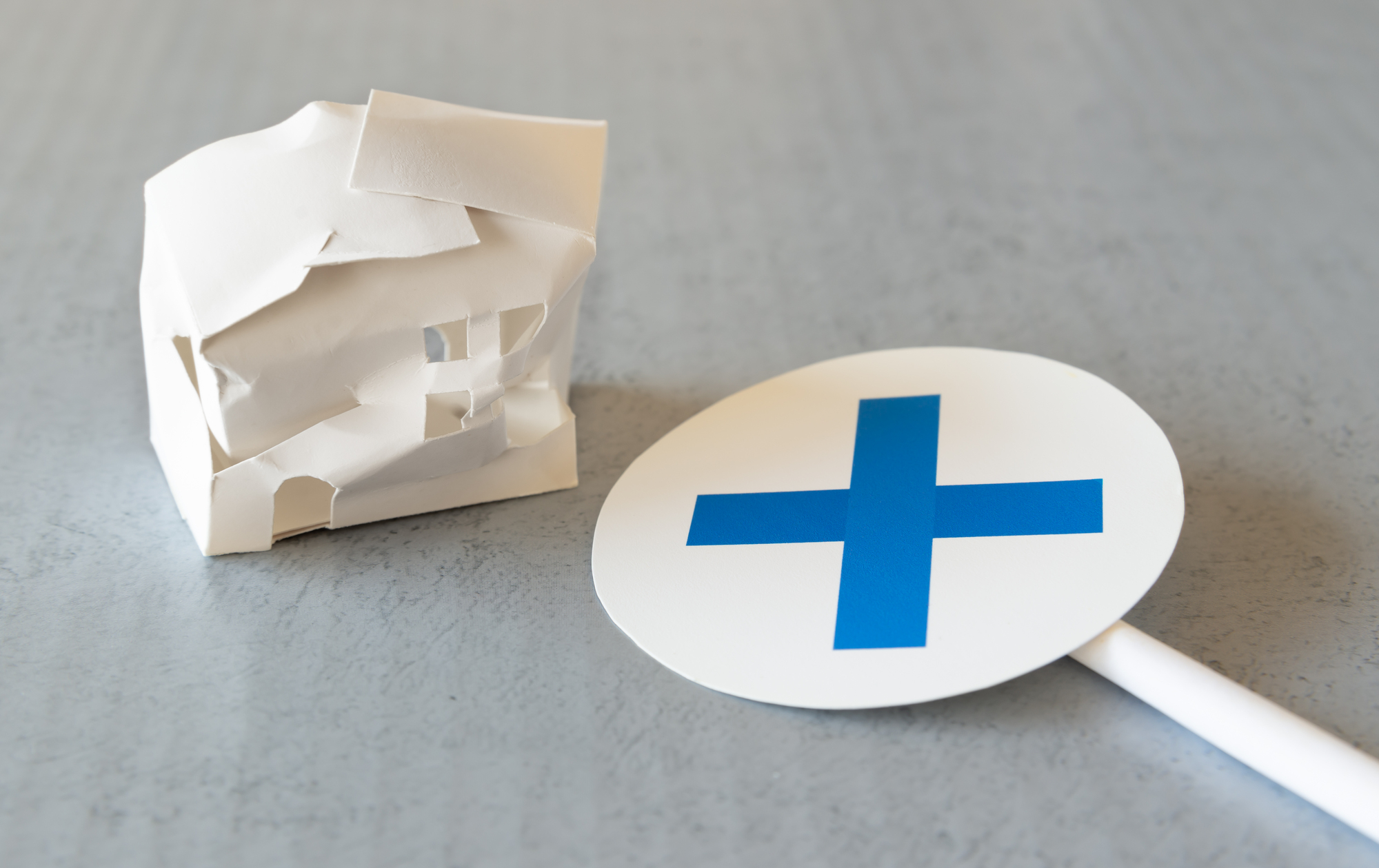公開日:2025.08.06 更新日:2025.09.16
空き家の活用方法|放置リスクを防いで収益化・地域貢献も可能に【相談無料】

空き家を放置すると、「特定空家等」に指定されて固定資産税の負担が増えるリスクがあります。しかし、空き家を賃貸やシェアオフィスとして活用すれば、収益化や地域活性化につながる可能性もあります。この記事では、賃貸活用や民泊、店舗利用からリノベーションまで、補助金制度も活用しながら空き家再生を実現する方法をご紹介。空き家管理でお悩みの方、必見です。
目次
空き家を活用しないとどうなる?放置リスクを先に確認しよう

相続した実家や転居後のご自宅。そのうち何とかしようと先延ばしにしていませんか?空き家の活用は確かに手間もコストもかかりますが、放置し続けることで発生するリスクは想像以上に深刻です。まずは空き家を放置した場合の具体的なリスクを整理しましょう。
倒壊・火災・不法侵入などの物理的リスク
空き家は人の目が届かないため、さまざまなリスクを抱えています。
まず建物の劣化が急速に進み、屋根や外壁の損傷から雨漏りが発生し、木材の腐食やシロアリ被害が拡大します。台風や地震などの自然災害時には倒壊の危険性も高まり、近隣トラブルを招く可能性があります。さらに、施錠が甘くなりがちな空き家は不法侵入されやすく、不審者が住み着いたり犯罪の温床となったりするケースも。電気系統の老朽化による火災リスクや、雑草の繁茂による景観悪化も問題です。
空き家の放置により事故や被害が発生した場合、所有者は民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)に基づき損害賠償責任などの法的責任を問われることもあるため、定期的な点検と適切な管理が不可欠です。
固定資産税の増加・特定空き家指定のデメリット
空き家をそのまま放置していると、市区町村から「特定空家等」に指定されることがあります。この指定を受けると、これまで住宅用地として受けていた固定資産税の軽減措置が解除され、税負担が最大6倍まで跳ね上がってしまいます。
さらに、行政から空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて改善命令が出されます。これに従わない場合、特定空家等にかかる固定資産税の特例措置(住宅用地特例)の対象外になり、最終的には行政代執行により強制的に解体され、その費用が所有者に請求されます。
解体費用は一般的な住宅でも100万円以上かかることが多く、突然の高額出費となる恐れが。また、特定空き家指定は近隣住民にも周知されるため、所有者のイメージダウンも避けられません。
金銭的にも精神的にも大きな負担となるため、早めの対策が重要です。
近隣トラブル・資産価値下落などの社会的リスク
管理されていない空き家は、景観悪化や害虫発生、不審者の出入りなど、近隣住民にとって大きな迷惑となります。特に庭木の越境は民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)、悪臭発生は民法第709条(不法行為)による損害賠償請求の対象となり得ます。こうした問題が続くと地域全体の治安や景観が悪化し、周辺の不動産価値まで下げてしまいます。
結果として「地域の迷惑物件」として認識され、将来売却する際も買い手がつかなかったり、相場を大幅に下回る価格でしか売れなくなる可能性があります。地域コミュニティからの信頼を失うことで、所有者や家族の社会的立場にも長期的な影響を与えかねません。
空き家活用方法の種類と特徴|収益化・地域貢献・自用型まで

空き家活用を考える際、どんな使い道があるのかわからない、収益を上げたいけれど難しそうと悩む方は少なくありません。実は空き家には、収益化はもちろん、地域貢献や自分らしい暮らしの実現にもつながる多彩な活用方法があります。
賃貸住宅としての空き家活用(戸建賃貸・サブリース)
空き家を戸建て賃貸として貸し出すのは、最も一般的で安定した収益が期待できる活用方法です。アパートやマンションより競合が少なく、個人や家族に長期入居してもらいやすいのがメリット。賃料は立地や築年数にもよりますが、月5万円から15万円程度が相場となります。
自主管理が難しい場合は、不動産会社が一括借り上げするサブリース契約を利用すれば、空室リスクや管理の手間を大幅に軽減できます。リフォーム費用は50万円から200万円程度必要ですが、たとえ老朽化が進んでいても再生可能で、比較的参入しやすい選択肢です。長期的な資産運用として収益性を重視する方には、まず検討したい空き家活用法といえるでしょう。
店舗・シェアオフィス・民泊などへのコンバージョン
駅近や観光地周辺など立地条件が良い空き家なら、住宅以外の用途へのコンバージョンで高収益を狙える可能性があります。たとえば、カフェや雑貨店、フリーランス向けシェアオフィス、民泊などが代表。民泊なら1泊5,000円から15,000円の収入が見込め、稼働率次第では賃貸住宅を上回る収益も可能です。
リノベーションで個性を出せる点も魅力で、地域にないサービスや雰囲気を提供する拠点になり得ます。ただし、用途変更に伴う建築基準法、都市計画法、消防法への適合、さらに旅館業法や食品衛生法などの各種営業許可の取得が必要で、初期投資は100万円から500万円と高額になりがちです。
空き家の住宅以外のコンバージョンは、集客や運営ノウハウも求められるため、事業経験がある方や専門業者との連携が成功の鍵となるでしょう。
地域交流拠点・NPO貸与・趣味スペースとしての非収益活用
空き家を収益化せずに活用する方法として挙げられるのが、たとえば地域住民の集いの場やNPOの活動スペース、子育て支援施設として開放すること。人の出入りがあることで、建物の劣化や防犯面の問題も解決できるメリットもあります。また、陶芸や音楽などの趣味のアトリエや週末の拠点として使うセカンドプレイス型も人気です。
固定資産税などで年間20〜50万円程度の維持費用が必要ですが、それでも地域からの感謝や社会貢献への充実感、趣味を通じた生きがいなど、お金では買えない価値を得られるはず。自治体の補助金制度を活用できる場合もあるので、地域貢献や自己実現を重視する方には魅力的な選択肢といえるでしょう。
空き家活用に使える補助金・制度支援をチェック

空き家活用を検討しているものの、お金がかかりそう、手続きが面倒と感じている方に向けて、国や自治体による手厚い補助金制度が用意されています。うまく活用すれば空き家活用・改修・耐震・賃貸化などにかかる費用の不安を軽減できるかもしれません。ここでは利用可能な支援制度を整理してご紹介します。
国の「空き家対策総合支援事業」概要と対象要件
国土交通省の「空き家対策総合支援事業」は、空き家の除却、改修、調査、活用を包括的に支援する制度です。市町村が策定する「空家等対策計画」に基づき、空き家バンクに登録された築20年以上の戸建住宅が対象となります。
補助内容は事業費の2分の1以内(除却の場合は1戸当たり上限80万円、活用の場合は上限100万円)となっています。地域コミュニティ維持やモデル事例に該当する場合、設計・改修工事費の補助比率は、国2/5・自治体2/5・所有者1/5となるなど、事業主体により多様な支援形態が用意されています。
対象要件として、適切な管理が行われていない状態の空き家で、地域の居住環境改善に資する取り組みであることが必要です。この事業は市町村を通じて実施されるため、まずは居住地の自治体で同制度を採用しているか確認をしましょう。
自治体独自の改修・耐震・賃貸活用支援制度
多くの自治体では、国の制度に加えて独自の住宅支援制度を設けています。耐震診断・リフォーム工事、断熱改修に対する工事費の一部支給が代表的で、補助率3分の2以上、上限200万円という手厚い支援を行う自治体もあります。
空き家活用では、東京都が最大500万円、横浜市が最大100万円の改修費補助を実施しているほか、空き家バンクへの登録を条件とした仲介手数料補助や税制優遇措置も用意されています。
また、新婚世帯向けリノベーション支援や地域貢献型スペース改修への支援など、多様なニーズに対応した制度があります。低所得者向けには月額最大4万円の家賃補助と改修支援(最大100万円)を組み合わせた制度も全国で展開されています。制度内容は自治体により大きく異なるため、各自治体の担当窓口での詳細確認が重要です。
申請時の注意点と支給タイミング
補助金申請では事前相談・計画提出・着工前の承認が必須で、工事開始後の申請は原則受け付けられません。申請書類は建物の現況写真、工事見積書、登記簿謄本、税務関係書類など多岐にわたり、不備があると審査が遅れるため正確に準備しましょう。
審査期間は通常1〜3ヶ月程度を要し、補助金の支給は工事完了後の実績報告書提出後となるため、工事費用は一旦全額自己負担する必要があります。また、多くの自治体では予算が年度内に限定され、募集の早期終了も珍しくないため、早めの相談と申請が不可欠です。
国の支援事業ではモデル事業として採択される必要がある場合もあり、地元の相談窓口や専門家との連携が重要になります。さらに、補助金を受けた物件には一定期間の利用制限が課される場合があり、転売や用途変更に制約が生じることも、事前に理解しておく必要があります。
空き家活用を始めるためのステップと注意点

空き家活用を成功させるためには、建物の状態や権利関係の確認、改修費用の見積もり、そして周辺環境や法的制限の調査が欠かせません。これらのポイントを順序立てて進めることで、リスクを避けながら収益源や地域貢献につながる有効な資産運用となるでしょう。
建物状態・権利関係の確認から始めよう
空き家活用の第一歩は、建物の現状把握と権利関係の整理から。まずは、構造の安全性、水回りや電気設備の状況、雨漏りやシロアリ被害の有無を専門家に診断してもらいましょう。特に築年数が古い場合は、建築基準法に基づく耐震基準への適合状況も確認が必要です。
同時に、法務局で登記簿謄本を取得し、土地・建物の名義や抵当権の設定状況をチェックし、相続が関わる場合は民法および不動産登記法に基づき相続登記を完了させておきます。
共有名義の場合は、民法第251条(共有物の変更)に基づき、他の共有者全員の同意が活用の前提となるため、早めに話し合いを進めることが重要です。
これらの基本的な確認を怠ると、後になって「使えない」「売れない」と判明し、大きなトラブルの原因となります。曖昧にせず、最初にしっかりと現状を把握しておきましょう。
用途に合った改修・修繕の必要性と費用感
空き家の状態と活用目的が明確になったら、必要な改修工事を検討しましょう。改修内容と費用は活用方法によって大きく異なります。
賃貸住宅として空き家を活用するなら、水回りの更新や断熱性能の改善が中心となり、100万円から300万円程度が目安です。民泊やシェアハウスでは消防設備の設置や間取り変更が必要となり、400万円から600万円の投資が見込まれます。
カフェなどの店舗や事務所への用途変更では、消防法やバリアフリー対応を含む大規模な改修が必要で、1,000万円を超えるケースも珍しくありません。改修工事を始める前には、複数の業者に見積もりを依頼して費用を比較し、期待できる収入と改修にかかる費用をしっかりと見比べて判断しましょう。
周辺環境・法的制限(用途地域・再建築可否)の確認
空き家活用を成功させるには、立地条件と法的制限を確認することが大切です。都市計画法に基づき用途地域によって建物の使い道が決められているため、たとえば住宅地域では店舗経営に制約があったり、商業地域でも住宅以外の用途には一定の条件があったりします。
また、建築基準法第43条(接道義務)を満たしていない土地では「再建築不可」となり、大規模な改修工事も難しくなる場合があります。市街化調整区域では都市計画法に基づく開発許可が必要で、空き家を活用できる方法が限られてしまいます。交通の便や近くの商業施設、騒音や治安といった周辺環境も、実際の収益に大きく影響します。
まずは自治体の都市計画課で用途地域を調べ、現地で周辺の様子もチェックしてみましょう。法的な問題がないか、そして採算が取れそうかを慎重に見極めることで、空き家を有効活用できるでしょう。
アキサポなら空き家の活用もワンストップでサポート可能です

活用したい気持ちはあるけど、何から手をつければいいのか迷ってしまう…そんなお悩みを抱える方にこそ、空き家の可能性を一緒に見つけてくれるパートナーが必要です。アキサポなら、活用方法の検討から実行支援までを一括対応。活かせる空き家に変えるお手伝いをします。
活用相談から企画提案・事業者連携まで対応
アキサポでは空き家活用のアイデア提案から事業化までトータルでサポート。カフェやシェアハウス、賃貸住宅など、物件の特性や地域性をふまえたうえで、適切な事業者とのマッチングも行います。
補助金申請や改修の手配もトータル支援
空き家を活かすには、改修費用や手続き面での壁がつきもの。アキサポなら、リノベーションに使える補助金の調査・申請サポートから、施工会社の手配、工事進行の管理までワンストップで対応。手間や不安を減らして、活用への一歩を後押しします。
無料現地調査・収支シミュレーションも実施(CTA)
どのくらい収益が出る?改修した分、回収できる?そんな不安には、無料の現地調査と収支シミュレーションでお応えします。初期費用から将来の収入見込みまで、専門スタッフが数字で可視化。納得して始められる活用プランをご提案します。
まとめ|空き家の活用は放置より「価値を生む」選択へ

空き家を「いずれ使うかも」「思い出があるから」と手をつけずにいると、建物の劣化や維持費が重くのしかかってきます。手放すことだけが解決策ではなく、空き家活用で新しい価値が生まれるかもしれません。
空き家活用の可能性を見極めて最適な形を選ぼう
空き家活用の可能性は、その建物の築年数・立地条件・間取りなどによって大きく異なります。賃貸、リノベーション、売却など、多様な選択肢があるからこそ、まずは物件の現状を正確に把握し、活用できる方向性を見極めることが大切です。
アキサポなら初めてでも安心の空き家活用サポート
初めての空き家活用は、不安や迷いがつきものです。アキサポでは、現地調査から空き家活用の提案、補助金の申請支援、事業者とのマッチングまでを一括で対応。何をすればいいのか分からないという段階からでも、専門家と一緒にスムーズに進められる環境が整っています。
この記事の監修者

岡崎 千尋 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
都市計画コンサルタントとしてまちづくりを経験後、アキサポでは不動産の活用から売買まで幅広く担当してきました。
お客様のお悩みに寄り添い、所有者様・入居者様・地域の皆様にとって「三方良し」となる解決策を追及いたします。