公開日:2025.08.18 更新日:2025.08.04
【2025年最新】管理不全空き家とは?定義・リスク・対策を総合解説

空き家問題は年々深刻化しており、特に老朽化や管理不足による地域環境への影響が懸念されています。所有者が高齢化し、維持管理が難しくなる事例も増えています。2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「空家等対策特別措置法」)に加えて、2023年の改正法で新たに「管理不全空き家」という区分が導入され、一層早期の対策を促す仕組みが整えられています。
本記事では、管理不全空き家の定義や特定空き家との違いを分かりやすく解説するとともに、固定資産税の優遇措置解除リスクや行政からの指導・勧告の流れについて詳しく紹介します。実際に管理不全空き家に指定された事例や、近隣住民とのトラブル事例もあわせて解説し、空き家所有者が取るべき対応を具体的にイメージできるようにまとめました。
さらに、管理不全空き家に指定されないようにするための具体的な対策や、専門家への相談の重要性についても取り上げます。修繕や定期的な見回りなど、日頃の管理を怠らないことがリスク軽減につながります。空き家管理でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。将来的な相続や売却を視野に入れた計画的な対応も重要です。
目次
管理不全空き家が注目される背景と法改正の概要
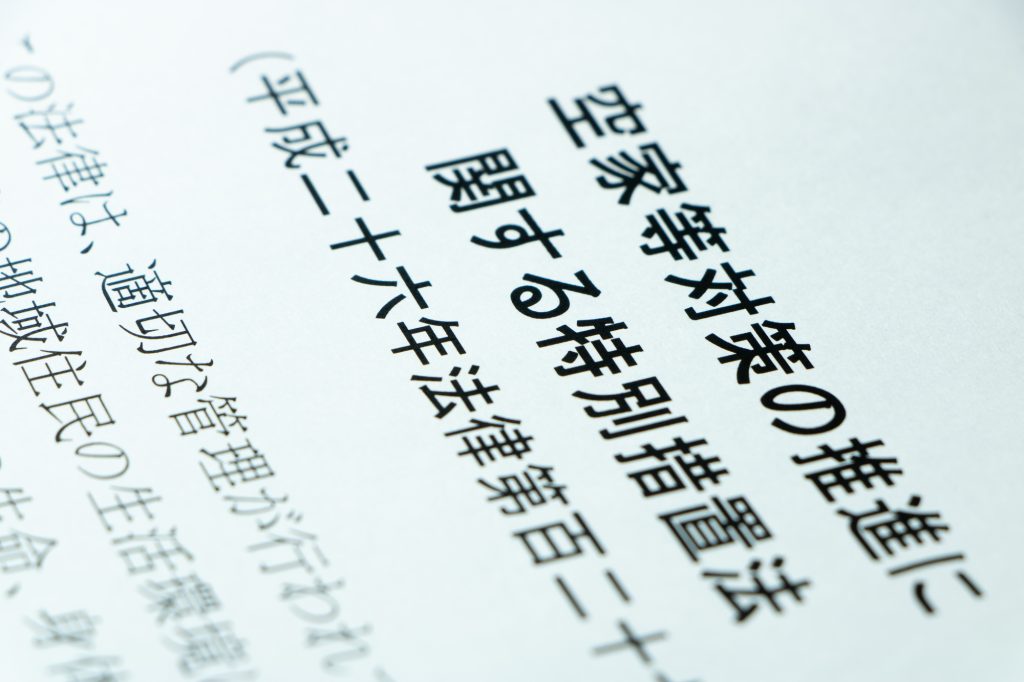
2015年に施行された空家等対策特別措置法が背景にあり、空き家問題への法的枠組みが整備されてきました。2023年の法改正で管理不全空き家が新たに定義されました。これにより、特定空き家に至る前の段階から早期に対策が取られるようになっています。
近年、人口減少や高齢化の進行に伴い、空き家の増加が深刻な社会問題化しています。このような背景には、相続による所有者不明や維持管理の負担増大があり、住宅の老朽化や倒壊リスク、景観の悪化といった問題も顕在化しています。自治体でも対応が追いつかないケースが少なくありません。そこで、2015年に施行された空家等対策特別措置法では、特定空き家に対する指導や勧告、さらには行政代執行といった措置が整備されました。
しかし、特定空き家に認定される以前の段階にある空き家は、法的措置の対象になりにくく、劣化が進んでも放置されがちな課題がありました。これらの空き家が地域コミュニティや近隣住民に悪影響を及ぼす事例が増えています。そこで2023年の改正法により「管理不全空き家」という区分が新設され、特定空き家予備軍を早期に把握し、自治体が必要な警告や改善指導を実施しやすくなったのが大きな特徴です。この改正は、空き家の段階的な管理を可能にし、将来的な危険を未然に防ぐことを目的としています。
特定空き家と管理不全空き家の違い

管理不全空き家と特定空き家は、空き家が抱える問題やリスクへの対処段階が異なるため、認定条件や税制の扱いも変わってきます。所有者としては、それぞれの違いを理解し、適切な管理体制を整えることが重要です。
特定空き家とは、建物の老朽化や倒壊の危険など周囲に重大な被害を及ぼす恐れがある空き家を指すのに対し、管理不全空き家は特定空き家になる前段階の物件にあたります。この区分により、放置による被害が拡大する前に修繕や管理の措置を取りやすくすることが可能となりました。また、管理不全空き家のうちは指導や勧告の対象であり、特定空き家ほど強制力は強くない一方で、早期対応を怠ると次の段階へ移行するリスクが高まります。特に固定資産税の優遇措置解除や罰則の発動が現実味を帯びてくるため注意が必要です。
管理基準および認定条件の違い
管理不全空き家は、適切な管理が継続的に行われておらず、建物の老朽化や周囲への衛生上の影響が懸念される場合に該当するとされています。敷地の雑草や廃棄物の放置、外壁の劣化などが確認されることが多く、自治体が現地調査を行い認定するケースも増加傾向にあります。具体的には、自治体が写真や立入調査をもとに状態を確認し、所有者に対して改善指導を行う流れが一般的です。一方、特定空き家は建物の崩壊リスクが高いなど、より深刻な状態であり、周辺環境への被害が一層懸念される物件を指します。
固定資産税や罰則の違い
管理不全空き家と特定空き家の最大の相違点は、固定資産税や行政代執行の適用段階にあります。管理不全空き家であれば、まずは自治体からの指導や助言が行われ、ただちに高額な固定資産税が課されるわけではありません。この段階で対応することで、特例の解除や罰則を回避できる余地があります。しかし、改善が見られず特定空き家に移行すれば、優遇措置の解除や行政代執行による解体費用が請求される場合もあるため、早期対応が重要です。こうしたリスクを踏まえ、所有者は専門家への相談や修繕計画の立案を検討することが望ましいでしょう。
空家等対策特別措置法で定められるポイント

「空家等対策特別措置法」では、自治体が管理不全空き家や特定空き家に対して行える助言、指導、勧告、命令、代執行などの手段を定めており、安全な地域環境を維持しながら空き家問題の早期解決を促しています。
この法律の目的は、所有者が空き家を適正に管理できるよう促し、周辺住民の安全や衛生を確保することにあります。自治体は、空き家や空き地の状態を確認したうえで、助言や指導を通じて問題の改善を促し、それでも改善が見られなければ勧告や命令を出すことが可能です。勧告に従わなかった場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が数倍に増加するリスクがあります。さらに、崩壊の危険が非常に高いといった緊急性がある物件の場合には行政代執行が行われ、解体費用は所有者の負担となるケースも想定されます。
2023年の法改正によって管理不全空き家が新たに導入されたことで、特定空き家に至る前の段階から自治体が積極的に介入しやすい体制が整いました。この区分は空き家問題の未然防止を目的としており、放置を続けると短期間で特定空き家に移行するリスクが高まります。物件所有者としては、日頃の管理を怠らず、行政からの通知には迅速かつ適切に対応することが空き家トラブルを回避する大切なポイントとなります。必要に応じて、専門家や自治体の相談窓口を活用し、早めに計画を立てることが重要です。
管理不全空き家に指定されるとどうなる?

管理不全空き家に指定されると、自治体からの指導や勧告を受けるとともに、固定資産税の優遇が解除されるリスクが高まります。指定を受けると、所有者としての管理責任が改めて問われることになり、計画的な対応が求められます。
まず、管理不全空き家と判断されると、所有者には修繕や清掃などの改善措置が要求される場合があります。それでも対応が不十分とみなされると、勧告へと移行し、特定空き家に認定される可能性が高くなります。特定空き家への移行は、行政代執行など強制力のある措置が用いられるリスクも含んでおり、より深刻な問題として取り扱われる点に注意が必要です。特に自治体の公的記録に指定履歴が残るため、今後の管理や売却にも影響する場合があります。
また、管理不全空き家に指定された段階で、固定資産税の軽減措置が見直されやすくなることも懸念材料です。特に住宅用地としての優遇措置を失った場合、土地の固定資産税がこれまでの数倍に跳ね上がることも考えられます。この負担増は、経済的理由で放置せざるを得ない所有者にとって深刻な問題です。こうしたデメリットを避けるためにも、早期の対策や専門家への相談を検討することが大切です。
指導・勧告を受けた場合の流れ
指導・勧告のプロセスでは、まず自治体から改善の助言や要請が行われ、それに応じない場合や改善が見られない場合に勧告へと進む仕組みです。勧告を無視し続けると「特定空き家等」として指定され、固定資産税の優遇措置が解除されたり、命令や最終的には行政代執行の可能性も高まります。命令段階では履行期限が明示され、期限までに改善しない場合は強制執行となります。自治体が段階的に措置を講じる背景には、所有者の早期対応を促すと同時に、地域住民の安全や美観を守る目的があります。
固定資産税が最大6倍になるリスクとは?
住宅用地であれば、通常は固定資産税に住宅用地の特例による軽減措置が適用されていることが多いですが、管理不全空き家や特定空き家に認定されると、これらの優遇措置が取り消される場合があります。これにより固定資産税が最大6倍に増加する事例もあり、所有者にとっては大きな負担となるでしょう。税額が急増すると資金繰りが厳しくなり、結果的に空き家問題をさらに深刻化させる恐れもあります。税負担が急上昇すると、解体や売却をする余裕がなくなり、さらに放置を招く悪循環に陥る可能性もあるため、早めの対応が肝心です。早期に専門家へ相談し、現実的な対応策を検討することが重要です。
管理不全空き家を回避するための具体的対策

管理不全空き家に指定されないためには、適切な管理や活用策を講じることが重要です。空き家を「放置しない」という意識を持ち、計画的に対応することがリスクを最小化する第一歩になります。
日常的な巡回・清掃や定期的な建物の点検を行うだけでも、空き家の状態を良好に保つことができます。屋根や外壁の傷みを早期に発見し、簡易補修を行うだけで老朽化の進行を大きく抑えられる場合があります。長期的に使わない物件であれば、売却やリフォーム、賃貸活用なども検討し、管理の手間や費用を抑えるのも一つの方法です。相続問題などで所有者が複数にわたる場合には、権利関係を明確にし、適切な話し合いを行うことで管理や処分に関する方針を決めておくことも大切になります。これにより、意思決定が停滞するリスクを軽減できます。
売却や解体を含む有効活用策
管理不全空き家を放置するよりも、劣化が進む前に売却を検討することで建物の価値が目減りする前に資産化することが可能です。リフォームして賃貸として活用する方法もありますが、修繕費用や運用の手間を見積もった上でメリット・デメリットを考慮する必要があります。最近では空き家専門の買取業者に相談し、スピーディーに現金化するケースも増えています。もし老朽化が深刻な場合には解体し、更地として活用する選択肢もあり、負担となる固定資産税を抑えやすくなるというメリットがあります。更地にすることで近隣住民への影響を最小限に抑える効果も期待できます。
行政・専門家への相談窓口の活用
空き家バンクや自治体が運営する相談窓口、不動産会社やNPO法人など、専門家のサポートを受けることで、適切な管理や売却が進めやすくなります。相続や登記の問題が絡む場合には司法書士や弁護士といった専門家の意見が不可欠なこともあるため、早めに相談するのが賢明です。行政の補助金制度や解体支援策を活用できるケースもあるため、最新情報を確認しましょう。行政や民間のサポートを活用しながら、空き家を有効利用する手立てを探ることで、管理不全空き家への指定リスクを低減させることができるでしょう。定期的な相談と情報収集が、最適な対応策を選ぶ鍵となります。
まとめ・総括

空き家が増え続ける中、新たに設けられた管理不全空き家の概念は、早期の適切管理を促すうえで大きな意味を持ちます。所有者の責任が明確化されたことで、これまで以上に計画的な対応が求められるようになりました。法改正のポイントを把握し、リスクを回避するための対策を早めに取ることが重要です。
空家等対策特別措置法の改正によって、特定空き家に至る手前の段階である管理不全空き家が明確に定義されたことは、所有者にとって早期行動の重要性を再認識させるものと言えます。放置すれば固定資産税の優遇が解除され、大幅な税負担を強いられる可能性があるだけでなく、周辺住民に深刻な影響を与えるリスクも高まるでしょう。行政からの勧告や命令を受けることで、対応の自由度が制限される恐れもあります。
一方で、売却や解体、あるいはリノベーションによる活用など、空き家を有効に再生するチャンスも存在しています。積極的に専門家への相談を行い、適切な対策を取ることで、地域の環境を守りながら自らの資産を守ることにもつながるはずです。空き家バンクや自治体の支援制度を利用するなど、情報収集と行動を組み合わせることが効果的です。管理不全空き家を回避するために、法改正の内容を理解し、早めのアクションを起こすことを心掛けてください。小さな管理の積み重ねが、大きなトラブルを防ぐ最善の手段となります。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。










