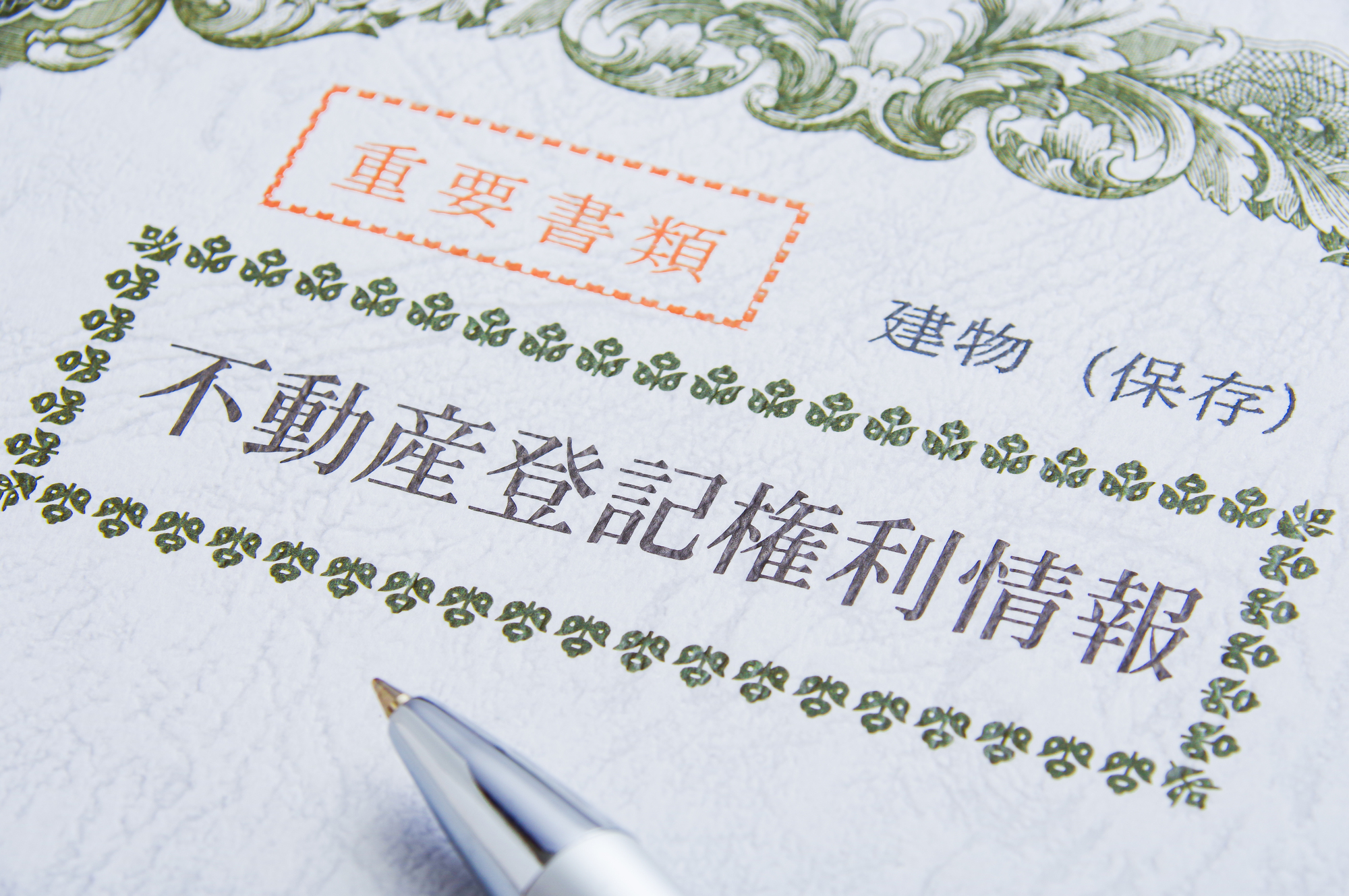公開日:2025.08.21 更新日:2025.08.04
共有名義の相続を徹底解説|流れ・リスク・解消までわかる完全ガイド

共有名義の不動産を相続する際に知っておきたい基本事項や留意点について解説します。
共有名義ならではのメリットやリスク、手続きの流れ、さらに解消方法までをわかりやすくまとめました。
目次
共有名義で相続するとは?基本の考え方
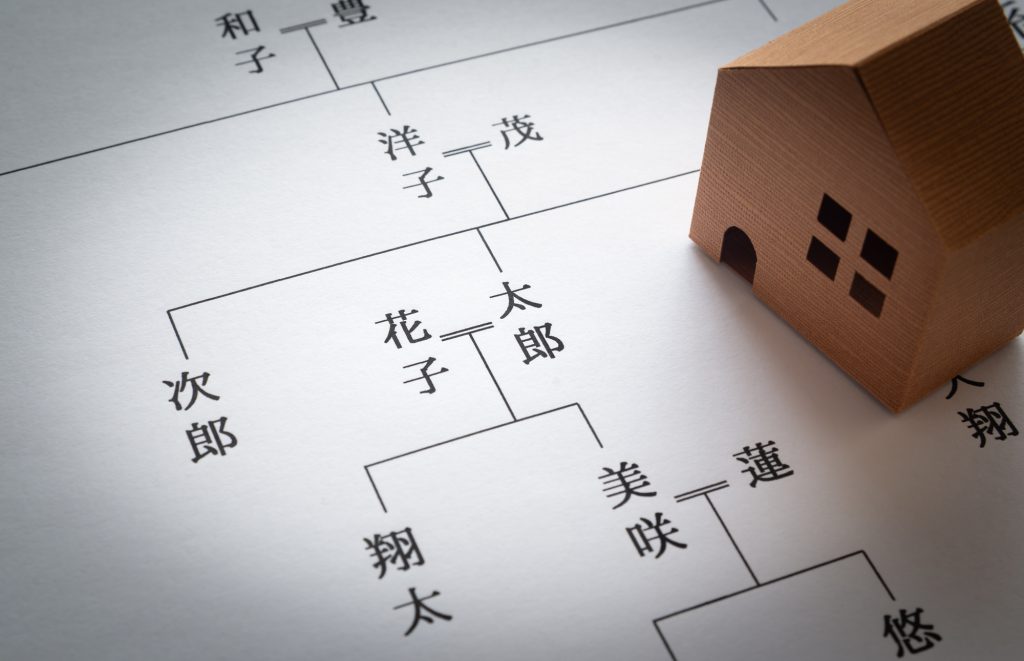
共有名義で相続する場合、それぞれの相続人が不動産を持分割合で共同所有します。
通常、相続が発生すると不動産の所有権は法定相続人全員に法定相続分の割合で共有されることになります。共有名義では相続人ごとに共有持分が割り当てられ、それぞれが独立した物権的権利を保有します。持分割合の計算は遺産分割協議による合意、または民法に定められた法定相続分に基づき決定されます。
共有名義は一見公平感がありますが、調整が必要な場面が多い点に注意が必要です。売却や担保設定などの意思決定において、すべての共有者の同意が必要となり、意見がまとまらないと資産活用が困難になる場合があります。
2024年以降、相続登記は義務化され、期限内に手続きを行わない場合には過料などの罰則が科されることがあります。そのため、特に共有名義の場合は関係者全員が早期に話し合い、手続きをスムーズに進めることが大切です。
共有持分と法定相続人の仕組み
法定相続人は民法により定められ、配偶者は常に相続人に含まれます。そのうえで子、親、兄弟姉妹の順番で相続の優先順位が決まります。たとえば夫婦で共有名義の不動産を所有し、一方が亡くなった場合は、残った配偶者だけでなく子どもがいれば子どもも相続人となります。
各相続人の持分割合は法律または協議によって決めることができます。遺言書がある場合は、その内容に基づいて持分が割り振られるため、法定割合にこだわらない調整も可能です。ただし、遺言がないときは遺産分割協議を経て持分を確定する必要があり、共有者同士の話し合いが重要になります。
相続登記が必要になる理由
不動産の権利関係を対外的に証明するものが登記です。被相続人の所有権をそのままにしておくと、誰が実際の名義人なのか不明確になり、売却や担保設定、相続手続きが滞る恐れがあります。特に共有名義で相続した場合、複数人が登記に関わるため権利関係の管理がより複雑になります。
2024年4月1日からの不動産登記法改正によって相続登記が義務化され、期限内に手続きを行わないと過料が科される可能性が出てきました。共有名義の相続では手続きや書類の数も増えるため、早めの準備が必要です。
ケース別に見る共有名義相続のポイント

共有状態の背景や家族構成によって相続の進め方が変わります。
共有名義の相続は、夫婦や親子などの近い関係であっても、将来的に共有者の数が増えるきっかけになる可能性があります。たとえば親子の共有名義を子が相続すると、さらに孫の世代で共有者が増えることもあるのです。
また同じ家族であっても、住宅ローンの残債やライフスタイルの変化により、意見が合わなくなることがあります。住宅の賃貸や売却を検討する際に、共有者全員の同意が必要になるため、調整が難航するリスクが高まります。
ケースごとの特徴やリスクを知っておくことで、相続時にスムーズに協議を進められます。ここでは代表的なパターンを取り上げ、対策のヒントを紹介していきます。
夫婦間で共有していた不動産を相続する場合
夫婦で共有名義の不動産を所有している場合、配偶者は法定相続人として常に優先的に相続権を持ちます。例えば、夫婦で2分の1ずつ所有していたところ、一方が亡くなると、残された配偶者の共有持分が増える一方で、子がいれば子との共有関係が生じることになります。
住宅ローンが残っている不動産の場合、ローン契約者が死亡すると団体信用生命保険(団信)によって残債が完済されることが多いです。しかし、完済後も共有名義は変わらず、相続によって子どもの共有持分も発生します。
親子で共有していた不動産を相続する場合
親子で共有していた不動産を相続すると、次の世代で共有者がさらに増える場合があります。親が亡くなり、子どもだけが名義を持つことになっても、子どもがさらに結婚や出産によって新たな家族が増えれば、将来的に相続人が増加する可能性は否定できません。
特に将来の相続人が多い家庭では、共有者同士の意思決定が難しくなる点を意識する必要があります。不動産の管理や処分に時間と手間がかかるようになる前に、事前の話し合いや遺言書の作成、専門家に相談することが最善策です。
兄弟・親族同士で共有していた不動産を相続する場合
兄弟や親族同士で共有していた不動産を相続するとき、もともと共有者の数が多いほど意見調整が大変になる傾向があります。将来にわたって関係者がさらに増えると、合意形成に多くの時間と労力を要するでしょう。
なかには遠方に住んでいる親族も含まれるため、物理的な事情で協議が進まず、固定資産税の負担や管理責任を巡るトラブルが起きやすくなります。兄弟・親族間で対立が深刻化する前に、遺産分割協議で持分調整をしたり、換価分割による解消を検討することが重要です。
共有名義のメリット・デメリット

共有名義の持つ利点と注意すべき問題点を整理します。
共有名義にする意味合いをよく理解しておくことは大切です。相続税対策や財産分与を公平に行うなど、メリットがある反面、管理や処分での合意形成が難しいというデメリットもあります。
共有者同士の関係が良好であれば問題は大きくなりませんが、状況は時間とともに変化します。新たに家族が増えたり、共有者が亡くなって新しい相続人が参加することで、意思決定がさらに複雑になっていくのです。
ここではメリットとデメリットの両面を把握し、将来的なリスクや負担の増大を踏まえて最適な選択をするためのポイントを整理しておきます。
共有名義の相続を選択するメリット
第一に、相続税の観点から共有の方が有利になるケースがあります。相続税評価額を持分ごとに分散させることで、納税額の圧縮を図れる場合があるのです。また兄弟間などで財産分与の公平性を保ちたいときは、一つの不動産を複数名義にしておくことで平等感を得られるという側面もあります。
第二に、当事者間で不動産全体を分割する手間が省けるため、急いで売却をしたり、無理に不動産を分筆したりする必要がない場合もあります。ただし、これらのメリットを最大限に生かすには、共有者同士のコミュニケーションと合意形成が円滑に行われることが前提です。
共有名義に関連するリスク・デメリット
共有名義で最も大きなリスクとなるのが、処分や管理における意見対立です。売却をするにも、リフォームを施すにも、共有者全員の同意が必要となります。意見がまとまらないとき、話し合いが長引くだけでなく、物件価値が下がるリスクもあります。
また、将来的に相続人が増えると、固定資産税や管理費の分担など、責任の所在が曖昧になることが多いです。どの共有者がどのタイミングで支払うのか、居住実績の有無によって負担感が異なるなど、感情的な対立が生じるケースも珍しくありません。こうしたデメリットを回避するためには、早い段階で共有の解消方法を検討しておくことが重要です。
共有名義の相続手続きの流れ
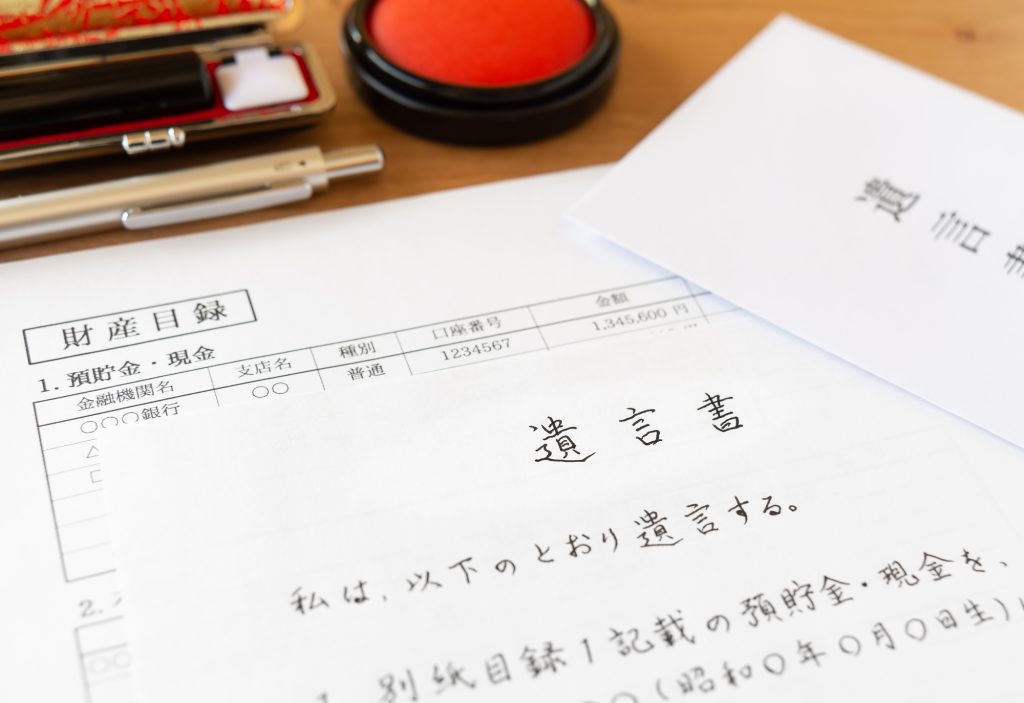
具体的な相続手続きのステップを確認しながら、大事なポイントを押さえましょう。
共有名義の相続では、まず相続人や持分を確定させるプロセスから始まります。戸籍謄本の取得や相続人全員の合意形成は、共有者が多いほど時間を要するので注意が必要です。
その後、遺産分割協議書を作成し、共有名義で相続する場合の持分割合を明確に記載します。協議書が完成したら、法定手続きに従って相続登記や相続税の申告・納付に進みます。
2024年からは相続登記の義務化により、一定期間中に登記をしない場合に過料が科される可能性もあります。共有者全員が協力して手続きを早めに進めることで、トラブルや複雑化を避けられるでしょう。
遺言書の確認と相続人の確定
相続の第一歩は遺言書の有無の確認です。遺言書があればその内容に従って持分の分配が行われるため、話し合いを簡略化できます。一方、遺言書がなければ相続人全員が参加して遺産分割協議を行うことになります。
また、相続人を確定するためには被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、全員の関係を洗い出す必要があります。共有名義の場合は共有者全員を正確に把握しなければならず、見落としがあると後々トラブルの原因となります。
遺産分割協議と共有名義の相続登記
共有名義での相続が決まったら、遺産分割協議書を作成します。この協議書には不動産の持分割合を明示し、すべての相続人が署名・押印することで法的効力が生まれます。持分がどのように割り振られるのか明確にしておくことで、後の紛争を防ぐことができます。
協議書が整ったら、司法書士などの専門家に依頼して相続登記を進めるのが一般的です。2024年以降は相続登記が義務化され、共有名義の不動産も例外ではありません。期限内に登記を行い、全員の協力のもとでスムーズに手続きを終えることが重要です。
相続税の申告・納付の注意点
共有名義の場合でも、相続税評価額は個々の持分に応じて計算されます。それぞれの相続人が取得する持分によって納税額が変わり、申告の手続きもやや複雑になることがあります。相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10か月以内と定められているため、早めに計画を立てておく必要があります。
共有不動産の評価方法は一括で計算したうえで、各自の持分を割り出していきます。税理士などに相談すれば、減税特例やその他の控除要件に詳しく、効率的に申告を進めることが可能です。複数の相続人がいる場合は、連絡を密にし、納税負担の公平性について慎重に話し合うことが大切です。
共有名義の解消方法と具体的な手段

共有を解消して単独名義にする方法や、複数人でのトラブルを防ぐ手段を紹介します。
共有名義を長期間維持することは、相続人間のコミュニケーションが難しくなったり、意思決定が滞ったりする原因となります。共有者が多いほど問題は深刻化するため、早めに解消策を検討することが大事です。
共有不動産の解消には売却や分筆など複数の方法があり、ケースによって最適解は異なります。経済的な負担や相続人同士の合意状況を踏まえ、どの解消方法がベストなのかを検討する必要があります。
換価分割・代償分割で単独所有にする
換価分割は、不動産を売却して得た代金を相続人で分配し、共有状態を解消する方法です。共有者全員で売却に合意できればスムーズに進みやすい一方、不動産の市場価値や売却時期によっては望ましい金額にならない可能性があります。
一方、代償分割は、一人の相続人が不動産を単独で相続し、他の相続人には代償金を支払う手段です。不動産を単独名義にしやすい一方、資金を用意する必要があるため、相続人の経済状況を十分に考えたうえで決定することが求められます。
持分売却・持分放棄による解消
共有者の一部が自分の持分をほかの共有者に売却または放棄することで、共有状態を整理する方法です。とくに親族間の信頼関係があり、買い取りたい人や持分を放棄したい人がはっきりしている場合に適しています。ただし、持分を放棄する際には贈与税が発生する可能性もあるため、税務上のリスクを含めて検討してください。
第三者への持分売却は理論上可能ですが、ほかの共有者の同意が得られないと売却先が見つからない場合が多いのも事実です。いずれの方法を選ぶにしても、全員が納得できる合意形成を目指して慎重に話し合うのが望ましいでしょう。
トラブルを避けるための事前対策

共有名義にせざるを得ない場合でも、将来のトラブルを最小限に抑える工夫が大切です。
共有名義が避けられないとしても、事前にトラブル予防の策を考えておけば、後々の管理や処分が円滑化します。具体的には、遺言書の作成や専門家への相談など、対立を未然に防ぐ仕組みづくりが重要になります。
相続人間のコミュニケーションが保たれているうちに、不動産の管理方法や費用負担、将来的な売却方針について話し合っておきましょう。こうした合意形成は、将来の病気や死亡など予測不能な事態に備えたリスクマネジメントでもあります。
遺言書による明確な分割指定
元気なうちに遺言書を作成しておくことで、相続時の混乱を大幅に減らすことができます。たとえば不動産を誰がどのくらいの持分で相続するかを明示しておけば、遺産分割協議を簡略化し、共有者同士の対立を回避しやすくなります。
また、遺言書があれば法定相続分にとらわれない柔軟な分割が可能になるため、家族構成や資産状況に合わせた最適な相続プランを作りやすくなります。意思表示をはっきり示すことが、お互いのトラブルを防ぐ第一歩となるのです。
専門家へ早めに相談する重要性
共有名義における相続登記や相続税の申告手続きは、法改正によってより複雑化する傾向にあります。戸籍収集から協議書の作成、税金の算定まで、複数のステップが絡むため、知識の浅いまま進めると見落としが生じやすいです。
司法書士や税理士、弁護士などの専門家へ早期に相談すれば、豊富な経験やノウハウから最適なアドバイスを得られます。結果的に時間と費用を節約でき、家族間の紛争を最小限に抑えることにもつながるでしょう。
共有名義の相続に関するよくある質問

よくある疑問や不安について、Q&A形式でわかりやすくまとめます。
共有名義をめぐる疑問は、相続放棄した場合の扱いや、共有者の死亡後の手続きなど多岐にわたります。法改正の影響もあり、以前のルールと異なる点があるため、最新の情報を押さえておくことが重要です。
ここでは多くの方が直面しがちな質問を取り上げ、簡潔にポイントを確認してみましょう。問題を事前に知っておけば、実際に相続が発生したときに慌てず対応できます。
Q. 共有名義の不動産を相続放棄するとどうなる?
相続放棄とは、法定相続人としての立場自体を放棄する手続きであり、共有名義の不動産に限らず、被相続人の財産も負債も一切相続しないことを意味します。共有名義の物件については、放棄した人の持分は民法の規定により他の相続人に法定相続分の割合で帰属するか、または遺産分割協議を経て決定される場合があります。
ただし、相続放棄には家庭裁判所への申述が必要であり、相続の開始を知った時から3ヶ月以内という熟慮期間の期限もあるため慎重な検討が必要です。放棄した後に財産を得ることは原則できなくなるため、デメリットも含めて判断しなければなりません。
Q. 共有者が亡くなり相続人がいない場合の対応は?
共有者が亡くなり、相続人がいない状態を「相続人不存在」といい、共有名義の一部が宙に浮いたような状態になります。この場合、民法に定められた手続きに基づき家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てるなどの手続きが必要となり、共有者全体での意思決定が一時的に滞る可能性があります。
もし他の共有者がその持分を取得したい場合、特別縁故者に対する財産分与などの制度を利用できるケースもありますが、手続きは一般的に複雑です。早めに専門家へ相談し、余分な手間や費用が発生しないよう計画的に進めることが大切です。
Q. 共有名義の相続登記にかかる登録免許税はどれくらい?
相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率をかけて算出されます。通常の相続登記の場合は評価額の0.4%が基本税率です。ただし、申告期限内に手続きを行わなかったり、手続きが遅れたりすると、別途費用が追加でかかる可能性があります。
共有名義の場合も同様に、各人の持分割合に応じて税金が発生します。複数の持分登記を同時に行う場合は、書類の準備がやや複雑になるため、早めに進めておくことをおすすめします。
まとめ|共有名義相続は早めの相談でスムーズに解決を

共有名義という選択肢は、さまざまなリスクを伴うため、専門家への早期相談が大切です。
共有名義による相続は、一時的に公平性を保つ方法として機能する反面、将来的に共有者が増えると管理や処分が難しくなるリスクを抱えています。各種手続きや相続税の計算、権利調整の場面では、想定以上に多くの時間とコストを要することがあるため、注意が必要です。
特に2024年の相続登記義務化によって、相続人が多い共有名義の不動産はさらに複雑化することが見込まれます。早めに専門家へ相談し、解消方法や相続プランを検討することで、将来のトラブルを避けやすくなります。共有名義を選択するかどうかは十分に検討し、必要であれば家族や専門家と連携しながら、スムーズな相続を目指しましょう。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。