公開日:2025.08.22 更新日:2025.08.04
住んでいない家の売却でかかる税金を徹底解説!計算方法から特例まで網羅

住んでいない家を売却する際には、想定外の税金負担が発生することがあります。とくに譲渡所得税や印紙税などの経費を理解していないと、売却時の手取りが大幅に減る可能性もあるため要注意です。
本記事では、住んでいない家の売却で必ず知っておきたい税金や特例制度、所有期間による税率の違いなどを具体的に解説します。相続した空き家や親の家を売却する際に使える控除制度も取り上げています。
正しい知識をもとに計画を立てれば、想定外の負担を避けるだけでなく、お得に売却できる可能性が広がります。ぜひ最後まで目を通し、最適な判断の参考にしてみてください。
目次
住んでいない家の売却に税金がかかる理由

住んでいない家を売却すると、居住用不動産のような特例適用が難しい場合があり、その結果として課税対象が増える可能性があります。
居住実績のない家でも、不動産を売却すれば譲渡所得が発生しうるため、所得税法上の課税対象となります。多くの人がマイホーム感覚で税金が軽減されると誤解しがちですが、実際には居住実績がないと特例の恩恵を受けにくいのが現状です。
また、住んでいない家は投資用物件やセカンドハウスとみなされるケースもあり、所有期間や利用状況で適用税制が変わります。短期保有の不動産は税率が高くなる点も意識する必要があります。
こうした税金は売却後の手取り額に大きく影響し、事前にシミュレーションを行わないと計画に狂いが生じることもあります。制度を正しく理解しておくことで不要な負担を避けられるでしょう。
売却時に課される主な税金一覧
住んでいない家を売却するときに課される主な税金として、譲渡所得税、印紙税、登録免許税が挙げられます。譲渡所得税は売却で発生した利益にかかる税金で、所有期間によって税率が変わるのが特徴です。印紙税は売買契約書に貼付する印紙で納め、契約金額に応じて金額が決まります。さらに売却に伴う登記変更には登録免許税も必要です。
居住用財産との違い
居住用財産として住んでいた家を売却する場合は、多くの特例や控除が適用される可能性があります。しかし、住んでいない家はマイホームの要件を満たさず、一部または全ての特例が使えないことも多いです。特に3,000万円の特別控除は住居としての使用実績が必要で、適用が難しいため、事前に利用できる制度を確認することが大切です。
住んでいない家の売却で必ずかかる税金|種類と費用目安

居住実績のない物件を売却する際に押さえるべき税金や費用には、いくつかの項目があります。
一般的に、不動産の売却には譲渡所得税、印紙税、登録免許税が基本的に関わってきます。さらに、ケースによっては消費税が発生する可能性もあるため、自分の売却形態を確認することが重要です。
費用を誤って見積もると、手残りが想定より少なくなり、ライフプランに影響が出ることもあります。税金や費用の種類と相場を理解しておくことで、支払いが発生したときも慌てずに対処できるでしょう。
あらかじめ税理士や不動産会社に相談し、どの程度の費用がかかるかシミュレーションするのがおすすめです。印紙税や登録免許税は契約金額や登記の状況で変わるため、見積もりに含めておきましょう。
譲渡所得税
譲渡所得税は、売却で生じた利益に課される税金です。短期譲渡と長期譲渡で税率が大きく異なるため、売却時期や所有期間を意識して計画を立てる必要があります。具体的には、短期譲渡は約39%、長期譲渡は約20%前後となることが多く、売却後に残る金額に大きな差が出ます。
印紙税
印紙税は、不動産売買契約書に貼付する印紙に課税される税金です。契約金額が大きいほど印紙税も高くなり、数万円以上になることもあります。一定期間は税率が軽減される特例措置がある場合もありますが、基本的に契約締結時に必要となるコストと考えましょう。
登録免許税
売却に伴う所有権移転登記などに課されるのが登録免許税です。登記をしなければ不動産の名義変更は完了しないため、実務上避けて通れない費用です。通常は物件評価額の一定割合が課税ベースとなるため、物件の価値が高いほど負担額も大きくなります。
消費税・住民税・復興特別所得税の扱い
不動産の売却では、課税事業者が売り主の場合のみ、売却額に消費税がかかるケースがあります。また、譲渡所得が発生すれば住民税や復興特別所得税も課税されます。これらも考慮したうえでシミュレーションし、最終的な負担額を把握することが大切です。
譲渡所得税の計算と注意点|流れと経費のポイント

譲渡所得税は基本の計算式を知っておくと、大まかな納税額を把握しやすくなります。
譲渡所得の計算では、まず売却で得た収入額から取得費と譲渡費用を差し引き、その残りに税率をかけます。この際、取得額に計上できる費用や、譲渡費用として認められる経費を正しく把握することが重要です。
計算の流れを理解すれば、不要な課税に気付いたり、控除をきちんと受けたりしやすくなります。特にリフォーム費用や改装費用の扱いは確認しておくべきポイントです。
また、取得費が不明な場合は概算取得費を使う方法もありますが、実際の取得費より大きくなることはなく、課税額が増えるリスクもあるため、できる限り正確な数字を準備しましょう。
譲渡所得とは?具体的な計算式を解説
譲渡所得の計算式は「収入金額−(取得費+譲渡費用)」で求められます。収入金額は不動産の売却額や受け取った手付金などを含む合計です。一方、取得費には物件購入額や仲介手数料を含め、譲渡費用には売却時に要した仲介手数料や測量費などが含まれるため、もれなく整理することが欠かせません。
取得費・譲渡費用に含まれるもの
取得費には、物件購入時の仲介手数料や不動産取得税、改良費などが含まれることがあります。また、譲渡費用には売却時の仲介手数料や契約書の印紙代、リフォーム費用などが含まれる場合があるため、領収書を保管して正確に申告する必要があります。特に過去の改築費用は忘れがちなので、書類をしっかり確認しましょう。
短期譲渡と長期譲渡の税率の違い

譲渡所得税の税率は、物件をどのくらいの期間所有したかで大きく変わります。
短期譲渡とは、不動産を売却した年の1月1日時点において、所有期間が5年以下の物件を売却した場合を指します。この場合、所得税法に定められた課税率は長期譲渡よりも高くなるため、売却額から差し引かれる税金がかなり大きくなります。購入後すぐに売却する事情がある場合でも、税率差を考慮してスケジュールを組むことが大切です。
一方、5年超保有の長期譲渡は税率がおよそ短期譲渡の半分程度になり、結果的に手元に残る金額が増える傾向があります。長期保有を見据えることで節税効果が得られるケースも少なくありません。
ただし、長期譲渡でも物件の取得日を起算日に注意する必要があります。登記や契約書の日付などが基準となるため、どの時点を所有期間の起算とするか把握しておきましょう。
5年以下か5年超かで変わる課税体系
短期譲渡は所有期間5年以下の売却に適用され、税率が高めに設定されています。税制上、不動産の短期売買を投機的とみなし、課税を強化している背景があります。予想以上に税金がかさむケースがあるため、所有期間のカウントを事前に確認しておくことが賢明です。
所有期間によって大きく変わる税率
短期譲渡では所得税や住民税を合わせて約39%の税金が課される一方、長期譲渡は約20%程度にとどまるケースがあります。同じ不動産を売却するのに、所有期間でこれほど差が出るため、売却タイミングを見極めることが重要です。
親が存命中の家を売却する際に使える特例

親名義の家を売却する際も、一定の条件を満たせば税金を軽減する手段があります。
親が高齢になって介護施設に入居したり、別の場所で生活を始めて長く住んでいない家を売却するケースでは、租税特別措置法に定められた一定の条件を満たせば「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が適用できる場合があります。ただし、実際に親が居住用財産として使用していた実績が重要となるため、住民票や光熱費の支払い状況などを確認しておくとスムーズです。
また、親名義の不動産でも、所有期間が10年を超えていれば軽減税率の特例が使えることがあります。売却や贈与を検討する前に、どの税率が適用されるかを確認するのが望ましいでしょう。
特例の区分や適用条件は複雑で、誤解すると余分な税金を支払うリスクもあります。専門家の意見を取り入れながら、最適な方法を選ぶことが大切です。
3,000万円特別控除の特例の要件
親がマイホームとして使用していた物件で、一定期間内に売却することが主な要件です。親が住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があるなど、複数の要件があります。実態として暮らしていたかを示す資料や住民票が求められることが多いです。要件を満たすかは早めに確認しましょう。
10年超所有の軽減税率の特例
所有期間が10年を超える場合は、譲渡所得税をさらに低い税率で計算できる特例があります。親の名義で長く保有していた物件なら、短期譲渡と比べて税負担を抑えられるため、節税の観点からも検討する価値があります。
相続した空き家を売却する際に使える特例

相続で取得した空き家を売却する場合は、一般の売却と異なる特例が用意されています。
被相続人が住んでいた家を相続し、自分は住んでいない状態で放置しているケースでは、固定資産税や維持費が発生し続けます。そうした負担を解消するために早期売却を検討する方も多いでしょう。
相続空き家には、通常の3,000万円特別控除に加え、特定条件を満たせば「被相続人の居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除」が適用可能です。被相続人がひとり暮らしだった事実や、旧耐震基準の建物の場合の耐震改修の実施など、租税特別措置法に定められた複数の要件があるため、一度専門家に確認しておくと安心です。
さらに、相続時に発生した相続税を取得費に加算できる特例もあり、実質的な譲渡所得を下げて税負担を軽減できます。ただし適用条件や必要書類は多岐にわたるため、漏れなく準備することが大切です。
相続空き家の3,000万円特別控除の適用条件
被相続人がひとり暮らしだった実績や、売却が死亡後3年以内に行われることが主な条件です。また、相続した不動産が旧耐震基準の建物の場合、耐震リフォームの実施など要件を満たすための対応が必要になるケースもあります。
取得費加算の特例とは?
相続時に支払った相続税の一部を、譲渡所得を計算する際の取得費に加算できる制度です。これにより、譲渡所得を実質的に圧縮し、課税対象額を低く抑えることが可能です。相続税が高額な場合ほど加算額も大きくなるため、活用すると税負担を大幅に軽減できる可能性があります。本特例の適用には相続税申告書など、租税特別措置法に定められた必要書類が多いため、保管書類を早めに整理しましょう。
特例の併用可否と適用時の注意点
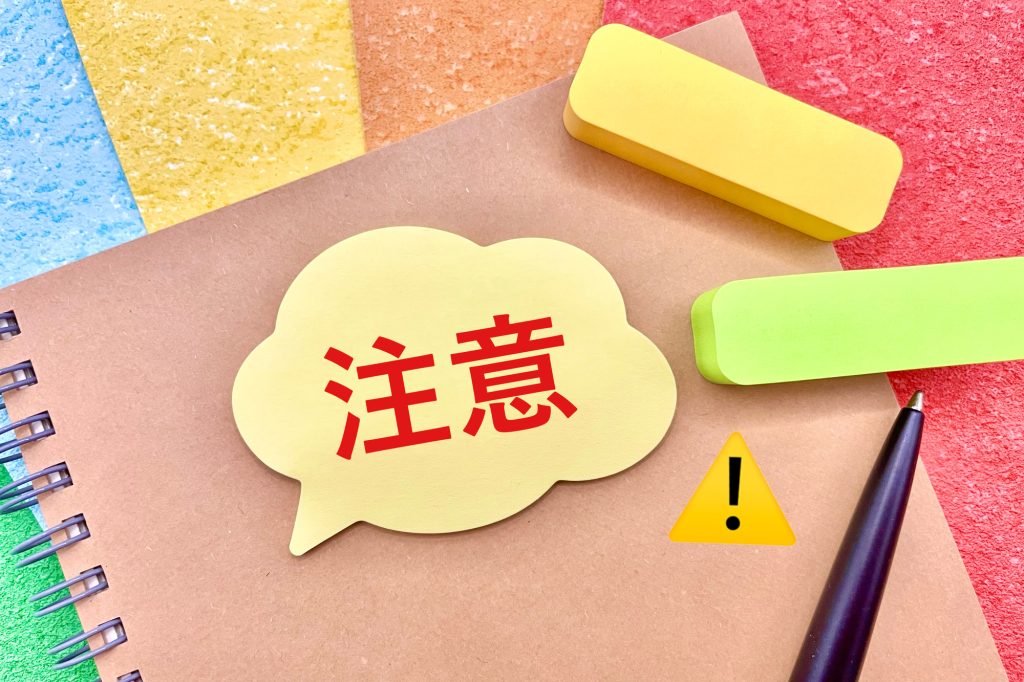
複数の特例制度をどこまで組み合わせられるかは、税制上の大きなポイントです。
多くの特例が存在する一方で、同時に適用できるものとできないものがあります。たとえば3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、要件を満たせば併用できる場合もありますが、相続空き家の特例とほかの制度は併用が難しいこともあります。
併用可否を誤ると後から税務署に否認されるリスクがあり、確定申告の段階でしっかり確認が必要です。誤申告は追徴課税の対象にもなるため、注意が必要です。
必要書類も特例ごとに異なります。売買契約書や住民票など基本書類に加え、相続書類も早めに準備しておくとスムーズです。特に相続や親子間の特例は関係書類が多いので、年度末に探すのではなく、手続き開始時からそろえるようにしましょう。
併用可能な特例の組み合わせ
3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、一定の要件を満たせば併用が認められ、課税所得を大きく減らせます。所有期間10年超が前提となるなど条件がありますが、売却時期や用途を確認すれば節税効果を高めることが可能です。
特例申請時の確定申告に必要な書類
確定申告では住所変更の有無を示す住民票、売買契約書の写し、相続が関係する場合は被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要です。特例ごとに必要書類が増えるため、国税庁サイトや税理士事務所を参考に、期限内に整えましょう。
税金のシミュレーション例|特例を使った場合と使わない場合

売却後の手取り額を把握するには、具体的なシミュレーションが重要です。
たとえば、売却価格が2,000万円、取得費が1,200万円、譲渡費用が50万円の場合、譲渡所得は750万円になります。特例を何も使わなければ、短期譲渡で約39%課税される一方、長期譲渡では約20%に軽減されるなど、大きな差が生じます。
3,000万円特別控除を適用すれば、譲渡所得がゼロや低額になる場合もあり、税金が実質的にほとんどかからない可能性もあります。同じ売却条件でも特例の有無で手元資金が数百万円単位で変わる点に留意が必要です。
所有期間や相続状況など細かな要件を満たす必要があるため、机上の計算だけでなく現実の書類や法的条件を照らし合わせて確認することが大切です。売却前に仮の計算を行っておくと、資金計画を立てやすくなります。
実際の譲渡所得計算例
たとえば売却価格2,000万円、取得費1,000万円、譲渡費用100万円、所有期間5年超の場合、単純計算で譲渡所得は900万円となります。ここに長期譲渡所得税率約20%をかけると、実質的に180万円ほどが納税額となります。特例が使えれば控除が働き、税額を大幅に抑えられます。
所有期間による税負担の比較
所有期間が5年以下の場合、同じ譲渡所得でも約39%前後の課税率となり、納税額はさらに高額になります。売却時期を少し延ばすだけで負担が大きく変わることがあるため、急ぎの事情がない場合は長期譲渡への切り替えも検討してみましょう。
住んでいない家を放置するリスク|費用・トラブルなど

使わない家をそのままにしておくと、維持管理コストだけでなくさまざまなリスクに直面します。
誰も住まない家は、固定資産税の負担が続くうえ、庭木の手入れや建物の点検など維持費も発生します。これらのコストは小さく見えがちですが、放置が長いほど負担が大きくなる可能性があります。
また、老朽化が進んだ家を放置した結果、近隣や通行人に危険を及ぼす状態になるケースもあります。倒壊や屋根の飛散が起こると、所有者に責任が及び、修繕費や賠償費用が発生するリスクも無視できません。
さらに市区町村から特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇が外れ、追加の出費を招くこともあります。活用予定がない家を持ち続けるより、早めに売却や活用を検討するほうが合理的です。
固定資産税・維持管理費の負担
住まない家でも、法律上は所有しているかぎり固定資産税が課されます。さらに、屋根や外壁のメンテナンス、雑草対策など定期的に管理しないと急速に老朽化が進むため、トータルコストは想像以上に大きくなることがあります。
特定空き家指定による追加課税リスク
管理不十分な空き家は「特定空家等」に指定されると、住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍に、都市計画税が最大で3倍になる可能性があります。自治体から改善命令を受ける場合もあり、放置が長引くほど経済的リスクが高まります。
住んでいない家を売却する方法とポイント

空き家の売却には、不動産仲介と不動産会社買取の2種類の方法があり、それぞれメリットとデメリットがあります。
不動産仲介は、市場価格に近い水準での売却が期待できる一方、売却までに時間がかかることや仲介手数料が発生する点がデメリットです。ただし、交渉を進めることで高値売却を狙いやすいのがメリットです。
不動産会社買取は、短期間で売却できる反面、価格は相場より低くなる傾向があり、資金を早期に回収したいのか高く売りたいのかで選択が分かれます。急ぎ資金が必要な場合には買取が向いています。
さらに、家を解体して更地にするか、古家付きで売却するかの判断も必要です。解体費がかさむ場合もありますが、更地のほうが売りやすい場合もあるため、総合的にどちらが有利かを検討しましょう。
不動産仲介で売却するメリット・デメリット
仲介を介することで多くの買い手と出会え、売却価格を市場相場に近づけられる利点があります。反面、仲介手数料が発生し、完了まで数か月を要することもあるため、時間的余裕がどの程度あるかを見極める必要があります。
不動産会社に買取を依頼するメリット・デメリット
買取では、短期間かつ手続きがスムーズですが、買取額は相場より10〜20%ほど低くなるのが一般的です。住宅ローンを早期に完済したい場合や急に資金が必要なとき、スピードを優先する選択肢となります。
古家付きか更地か?解体費用と売却価格の比較
古家を解体して更地で売ると、買主が利用計画を立てやすくなるため、比較的スムーズに売却できる場合があります。ただし解体費用も高額になりやすいので、家屋の状態と地域ニーズを踏まえ、どちらが得策か見積もりを取って検討することが重要です。
売却後の確定申告と必要書類

住んでいない家を売却して利益が出た場合、確定申告の手続きは避けて通れません。
売却で譲渡所得がプラスになったときは、原則として所得税や住民税が課税されるため、確定申告が必要です。特例や控除を利用する場合も申告で申請を行うため、誤りのない手続きを心がけることが重要です。
申告期限は毎年3月15日頃(年度により若干の変動あり)までで、この期限を過ぎるとペナルティが科される場合があります。売却した年の翌年に必ず手続きを済ませましょう。
まずは書類の不備をなくすことが大切で、特例を利用する場合は追加書類を準備する必要があります。漏れがあると控除が適用されないだけでなく、追徴課税のリスクも高まるため注意が必要です。
確定申告の手続きと期限
申告の期限は原則3月15日前後で、それまでに必要書類を整え、所轄税務署に提出する必要があります。譲渡所得の計算明細や、取得費・譲渡費用を証明する領収書、特例適用に関する書類を揃えておくと申告がスムーズです。
申告漏れ・控除漏れを防ぐ方法
譲渡所得税の申告は手続きが複雑で、控除の要件や書類も多岐にわたります。誤りを防ぐには、チェックリストを作成し、税理士に相談する、国税庁のサイトを活用するなどの対策が有効です。特に初めての不動産売却では、専門家に確認してもらうのも賢明でしょう。
まとめ・総括

住んでいない家の売却では、多種多様な税金や特例制度、リスクを総合的に考慮する必要があります。
最大のポイントは、譲渡所得税に代表される税負担をいかに抑えるかです。特例をうまく活用できるかどうかで、最終的に手元に残る金額が大きく変わってきます。
短期譲渡と長期譲渡、相続空き家の特別控除や3,000万円特別控除など、さまざまな制度があるため、自身のケースがどれに該当するかを検証することが重要です。書類の準備や申告期限など、実務面の手続きにも注意が必要です。
空き家を持て余しているなら、固定資産税や管理費の負担を続けるより、早めに売却や活用方法を検討するのも有効な手です。正しい情報と計画をもとに行動すれば、後悔のない売却がしやすくなるでしょう。
この記事の監修者

山下 航平 アキサポ 空き家プランナー
宅建士/二級建築士
ハウスメーカーにて戸建住宅の新築やリフォームの営業・施工管理を経験後、アキサポでは不動産の売買や空き家再生事業を担当してきました。
現在は、地方の空き家問題という社会課題の解決に向けて、日々尽力しております。








