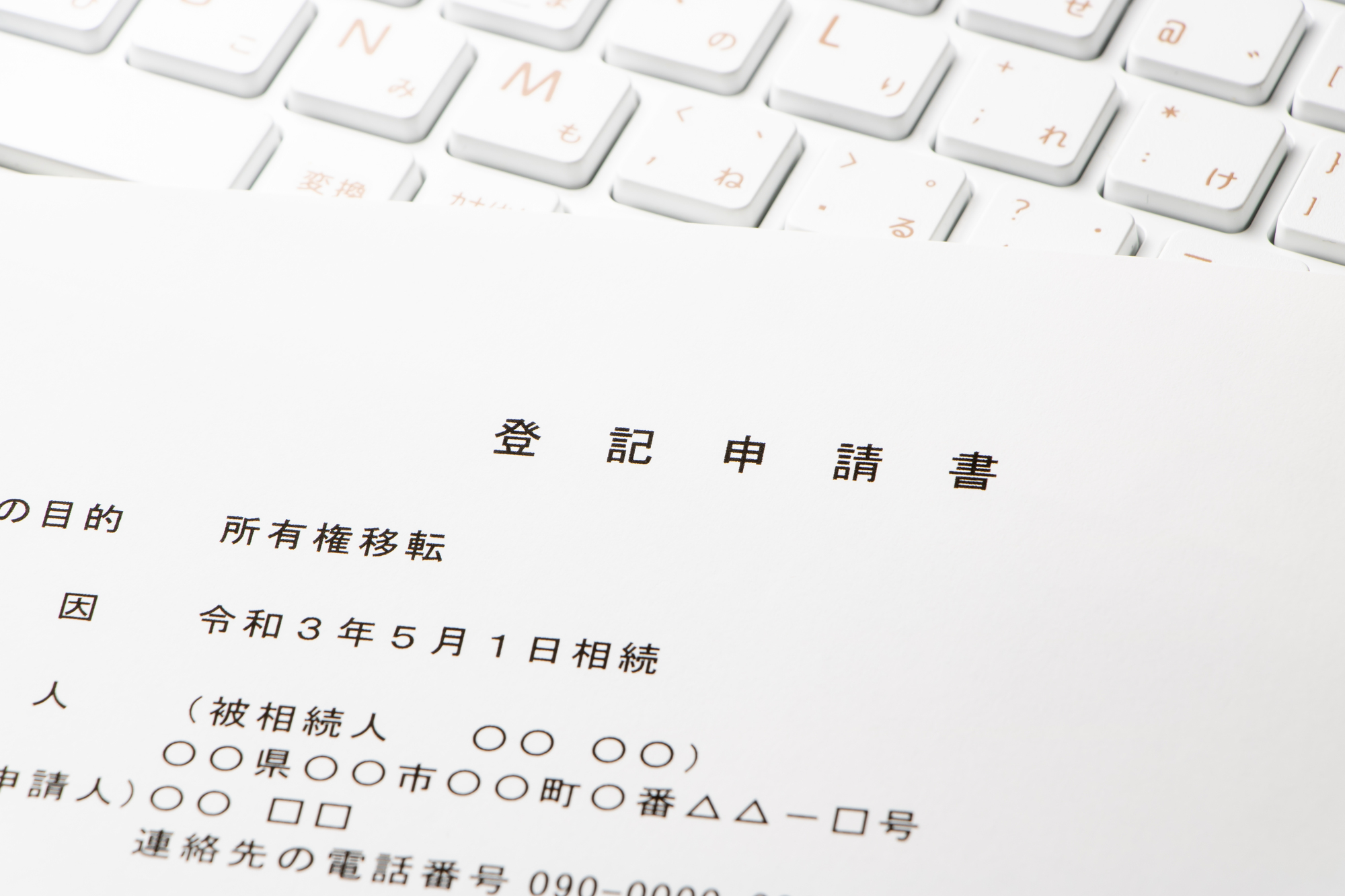公開日:2025.09.17 更新日:2025.08.04
【墓じまい費用】相場から内訳、払えない時の対処法まで徹底解説

墓じまいとは、お墓を撤去し、遺骨を別の場所に移す『改葬(かいそう)』などの手続き全体を指します。少子化やライフスタイルの変化により、後継者不在や維持管理の負担を理由として検討する方が増えています。本記事では、墓じまいに関する費用の相場や内訳、手続きの流れ、費用の分担方法、さらに経済的に困難な場合の選択肢まで幅広く解説します。
墓じまいを円滑に進めるためには、事前の準備や親族間での話し合いが重要となります。この記事を通じて、費用を含む実施方法や注意点を具体的に理解し、今後の検討に役立てましょう。
目次
墓じまいとは?基本的な概要と実施する理由

まずは墓じまいの意味と、その背景としてなぜ増えているのかを整理します。
墓じまいとは、お墓を解体・撤去し、埋葬されている遺骨を別の場所へ移す「改葬(かいそう)」を行うための一連の手続きを指します。本来は先祖代々受け継いできたお墓を守るのが一般的でしたが、少子化や後継者不足により管理が難しくなり、墓じまいに踏み切る方も増えています。供養の在り方が多様化する現代において、精神的・経済的負担を減らしつつも、丁寧に供養を行う手段として注目されています。
経済的な理由も大きな動機の一つです。遠方にあるお墓に定期的に通う交通費や、掃除・管理にかかる手間などが負担になり、やむを得ずお墓を畳むというケースも少なくありません。こうした維持管理の負担を軽減する目的で、遺骨を納骨堂や永代供養墓、樹木葬などへ移す動きが全国的に広がっています
また、ライフスタイルの変化に伴い、従来のお墓を持つことが必ずしも最適とは言えないケースもあります。親族や周囲と十分に話し合い、将来的な負担を見据えたうえで判断することが、後悔や相続時のトラブルを防ぐ重要なポイントとなります。
墓じまいの費用相場はどのくらい?
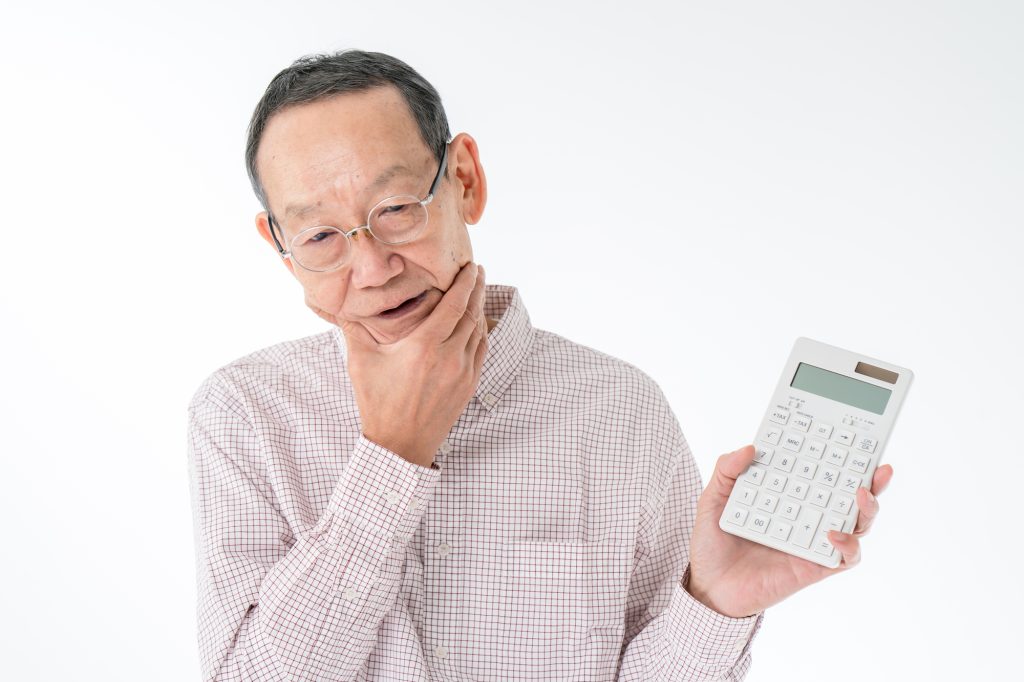
墓じまいを検討する上で、最も気になるのが全体的な費用相場ではないでしょうか。ここでは一般的な相場感とその背景を解説します。
墓じまいの費用相場は、全国的な実績データを基にするとおおよそ30万円から300万円程度と幅があるのが実情です。これは新たな納骨先の選定や墓石の状態、地域差など、さまざまな要因が影響します。また、改葬にあたっては「改葬許可申請書」の提出が必要となるため、行政手続きの準備も含めた費用計画が必要です。余裕をもった予算を組むとともに、どの要素が費用を押し上げるのかを理解しておくことが大切です。
石材店の解体費用や寺院へのお布施、新しい納骨スタイルへの移行費用などが主な内訳になります。合祀墓や納骨堂など、どの供養方法を選ぶかでも費用が大きく変わるため、事前に複数の候補を比較検討しましょう。最近では、民間業者によるパッケージ型の墓じまいプランも増えており、相見積もりを取ることでコストを抑えることが可能です。支払うタイミングや分割払いの可否など、経済的負担を考慮した選択が重要です。
また、親族間で費用を分担するかどうかによっても必要な金額は異なります。費用の負担割合について明確に合意しておくことで、後になって揉め事を防ぐためにも、早めに話し合って意見をすり合わせることが求められます。
地域差や墓地の規模・状態による費用の違い
解体費用は、墓地の立地条件や石材店までの距離、さらにはお墓の大きさや老朽化の度合いでも変わります。都市部の方が労務費や公的手数料が高くなる傾向にあり、逆に地方では作業費が抑えられるケースもあります。加えて、重機搬入の可否や作業スペースの有無によっても施工費に差が生じます。実際に見積もりを取って確認し、相場と比較することで大きな金額差を防ぐことができるでしょう。
閉眼供養・離檀料など宗教儀式関連の費用目安
閉眼供養というのは、お墓から魂を抜くための読経などの宗教儀式です。僧侶へのお布施の金額は3万円から10万円程度が一般的ですが、宗派や地域によって異なります。法要の内容(読経の有無や戒名の取り扱い)により増減する場合もあります。また、寺院の檀家を離れる際にかかる離檀料は、5万円から20万円程度と言われます。
ただし、離檀料は宗教上・法律上の支払い義務はなく、あくまで寺院への感謝の気持ちとして支払う任意の謝礼とされています。そのため、金額や支払いの要否は必ず事前に確認しましょう。場合によっては高額になるケースもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
墓じまいにかかる主な費用の内訳

墓じまいの費用は複数の項目で構成されます。主に発生する費用項目とそのポイントを見ていきましょう。
墓じまいの合計費用は、「墓石の解体撤去」「改葬手続き」「遺骨の移送」「新たな供養施設の契約料」などから成り立っています。それぞれの項目を把握しておくことで、どのくらいの予算を確保すべきか明確にできます。
中でも解体工事費用は、基本的に石材店が行う専門作業なので比較的高額になりがちです。逆に行政手続きに関わる費用は数百円から数千円と安価ではありますが、申請書の記載不備や提出期限を過ぎた場合は再手続きが必要になることもあります。スムーズな改葬のためにも、どの手続きがいつ必要かを事前にチェックしておきましょう。
遺骨を新たな場所へ移す際には、永代供養や納骨先の契約料といった費用も発生します。費用総額を事前に把握しておくことで、予期せぬ出費やスケジュール遅延を防ぐことができます。
お墓の解体・撤去工事費用
石材店に依頼し、墓石や外柵を撤去する工事を行います。費用は1㎡あたり10万円程度が相場とされ、墓地の立地条件や重機の搬入可否、基礎の深さなどによっても金額が上下します。複数の石材店を比較して、工事内容やアフターケアの有無を確認することが大切です。
行政手続き(改葬許可)や公的書類発行費用
墓じまいに伴う改葬には、市区町村役場へ「改葬許可申請書」の提出が必要です(墓埋法第5条)。この手続きにかかる手数料は300円から2000円ほどが一般的です。申請には旧墓地の管理者と、新しい納骨先の受入証明書が必要となるため、事前の確認が重要です。期限内に正確な書類をそろえるために、余裕を持ったスケジュールを組んでおきましょう。
遺骨の改葬・永代供養にかかる費用
遺骨を移す際には、新たに永代供養墓や納骨堂、樹木葬などへ契約するときの費用がかかります。合祀墓の場合は10万円程度から、個別区画型だと数十万円以上になることもあるので、希望する供養形態に合った予算を検討しましょう。また、施設によっては契約時に一括で支払う「永代使用料」に加え、年間の管理費が必要になる場合があります。供養形態によって管理費や定期的な維持費が発生する場合もあるため、長期的な視点で判断することが大切です。
費用は誰が支払う?負担の考え方と分担方法

墓じまいでは、第一にお墓を管理する責任のある人が費用を負担するイメージを持たれがちです。しかし、実際には遺骨が納められている先祖を共有する家族全体での問題と捉えられることが多いでしょう。特に兄弟やいとこなど、血縁関係が複数関わるケースでは早めに話し合いを始めることが肝心です。
墓じまいの費用負担には法律上の明確な義務規定はなく、あくまで家族間の合意によって決まるのが実情です。費用負担の決定は、家族構成や親族間の経済状況によって大きく異なります。法的な強制力がないため、あくまで当事者間の合意形成が重要となります。故人がどのような意向をもっていたか、あるいは誰が実際に管理行為を行っていたかなどを考慮し、公平感のある取り決めを行うのが一般的です。
また、費用負担を巡って意見がまとまらない場合は、地域の役所の相談窓口や、司法書士・行政書士などの専門家へ相談することも一つの方法です。客観的なアドバイスを得ることで、不要なトラブルを最小限に抑えることができます。
お墓の承継者と血縁者の負担割合
お墓の正式な承継者が全額負担するという考え方もありますが、現実には兄弟や親族で費用を分担することが多いです。たとえば、兄弟が複数人いれば、それぞれが同等に負担したり、生活状況に応じて柔軟に割合を調整することもあります。何よりも大切なのは、後のトラブルを防ぐために事前によく話し合うことです。
生前に支払うメリット・デメリット
生前に墓じまいを行うと、まだ体力と気力のあるうちに手続きを完了できるためスムーズです。費用の内容や支払い方法を落ち着いて検討できる反面、将来的に状況が変わった場合、すでに手続きを進めてしまっているため見直しが難しくなる可能性があります。また、生前に行う場合でも家族の同意を得ておくことが望ましく、手続きや費用について文書で残しておくと後の混乱を防げます。
どの時期に取りかかるかは、家族構成やライフプランを踏まえて慎重に決めることをおすすめします。
墓じまい費用が払えない時の対処法

経済的な理由で負担が難しい場合には、いくつかの選択肢が考えられます。
墓じまいには一定の費用がかかるため、一括で支払うのが難しい方も少なくありません。こうした場合に備えて、利用できる支援策や工夫を知っておくと、負担を軽減できる可能性があります。具体的には、各自治体の助成制度やローンの利用、解体工事のプラン見直しなど、複数の手段が存在します。
ただし、ローンや分割払いを利用する場合は、金利や返済計画について十分に把握しておく必要があります。親族間で話し合い、共同で支払いを検討するのも一案です。
前もって情報収集を行い、公的機関に補助金や相談窓口があるかどうかを確認してみるとよいでしょう。特に条件次第で利用できる制度がある自治体もありますので、自身の住んでいる地域での選択肢を整理しておくことが大切です。
自治体の補助金やメモリアルローンの活用
自治体によっては、一定の条件を満たせば墓じまいに関する補助金や助成金を受けられる場合があります。ただし、これらは地域によって実施の有無が異なるため、事前に自治体の公式サイトや窓口で確認が必要です。
また、銀行や信販会社が提供するメモリアルローンを利用して、費用を月々に分割して支払うことも一つの方法です。利子や審査条件は各金融機関で異なるため、複数を比較検討の上で選択することが望ましいでしょう。
費用を抑える業者選定と改葬プランの見直し
墓じまいの費用をできるだけ抑えるためには、複数の石材店や葬儀社から見積もりを取って比較することが基本です。業者によっては、行政書士との連携で改葬許可申請までサポートしてくれる場合もあります。
同じ工事でも、作業内容やアフターフォローの有無で費用に差が出ることがあります。さらに改葬先である納骨堂や永代供養墓も、その形態や場所によって費用が大きく変わるため、現実的な範囲で複数の選択肢を検討するのがおすすめです。
墓じまいの具体的な手順と注意点

墓じまいの流れを把握しておけば、スムーズに進行できます。あらかじめ知っておくべき手続きや注意点をまとめます。
手続きとしては、まず改葬先を確保し、現在のお墓で閉眼供養を行い、その後に墓石の撤去を進めるのが一般的な流れです。この手続きと並行して、自治体に改葬許可を申請する必要があり、書類の不備や期限切れには注意が必要です。各ステップを事前に整理し、確定したスケジュールに沿って抜け漏れのないように進めていくことが重要となります。
寺院と離檀する場合は、住職に事前連絡の上、離檀式や離檀料の支払いなどを行います。スムーズな手続きのためにも、早めの相談と準備が欠かせません。特にお盆や年末年始などの混雑期には、僧侶のスケジュール確保が難しくなることもあるので要注意です。
石材店との契約に関しては、解体工事の見積もりから契約内容まできちんと確認しましょう。作業の範囲や撤去後の清掃対応、万一のトラブル時の責任区分、石材の処分方法など、細かい点まで把握しておくことで、余計な心配を減らすことができます。
改葬許可申請や寺院への離檀手続きの流れ
まずは改葬先を決定し、必要書類を準備して自治体へ許可申請を行います。改葬許可証の交付には、現在の墓地管理者の「埋葬証明書(または収蔵証明書)」や、新たな受け入れ先の「受入証明書」が必要です。許可証が発行された後に、お寺で閉眼供養や離檀の手続きを進めるとスムーズです。
離檀料をめぐるトラブルが発生しやすいため、事前に住職や寺院との話し合いを徹底しましょう。寺院によっては、離檀を拒否されるケースもあるため、宗教法人との交渉には慎重な姿勢が求められます。
石材店との工事契約・トラブル回避のポイント
石材店を選定するときは、複数社の見積もりを取り、内容と費用のバランスを見極めることが大切です。また、工事日程や撤去後の清掃、廃材の処分方法まで確認しておきましょう。
見積書や契約書には、作業範囲・日程・追加費用の有無などを明記してもらうことで、後々のトラブルを防ぐことができます。業者によっては改葬許可書類のサポートを行う場合もあるため、サービス内容も比較検討しましょう。
今あるお墓を維持する場合との費用比較

お墓をそのまま維持する場合の費用との比較は、判断材料として重要です。
墓じまいは初期費用がかかる一方、今あるお墓を維持する場合は年単位で管理料や清掃費、法事のたびのお布施など継続的かつ累積的な支出が発生します。長期的に見ると、どちらのコストが負担を減らせるかは人それぞれ異なるため、金銭面だけでなく将来的な状況も見据えた総合的な視点が必要です。
特にお墓が遠方にある場合は、定期的に足を運ぶ交通費も考慮しなければなりません。高齢化や住環境の変化が進む現代においては、維持費の総額と管理の手間を天秤にかけることで、墓じまいに踏み切るかどうかの判断材料にできます。
費用だけでなく、将来的に誰が面倒を見るのかといった承継問題も含めて検討することが大切です。お墓を移すべきか、それとも維持すべきかという決断は、経済的な合理性と精神的な安心感の両面から考えてみましょう。
お墓の維持管理費と墓じまい費用どちらが得か?
お墓を維持する場合の管理費は数千円から数万円、年間法要のお布施などを含めるとさらに高額になることがあります。一方で墓じまいにはまとまった初期費用が必要ですが、その後の定期的な管理費を気にしなくて良いというメリットがあります。
費用比較の際には、改葬先(納骨堂・永代供養墓など)にかかる費用や今後の生活設計との整合性も重要です。自分や家族のライフステージに合致する形で、どちらにより価値を感じるかを判断することが大切です。
早めの検討で費用・トラブルを最小限に抑える
お墓に対する考え方は家族や親族の意向にも大きく左右されます。早めに話し合いを行うことで、費用の負担をどのように配分するか、あるいはどの時期に墓じまいを行うのかといった具体的な計画を立てやすくなります。
また、墓地管理者や寺院との調整が必要な場合も多いため、事前準備が結果的に時間とコストの節約になります。結果として、経済面・精神面の両方でトラブルを避け、納得のいく選択をしやすくなるでしょう。
まとめ|墓じまいを円滑に進めるための重要ポイント
今までの内容を振り返り、墓じまいを円滑に進めるための重要なポイントを再確認します。
墓じまいには、解体費用や閉眼供養のお布施、離檀料のほか、新たな納骨先の契約料など複数項目にわたる出費が発生します。相場は30万円から300万円程度と幅広く、地域差やお墓の規模、供養方法によって大きな価格変動がある点が特徴です。
費用を誰が負担するかは、承継者だけでなく兄弟や親族全体で話し合い、納得のいく分担方法を決めることが大切です。経済的に困難な場合には、自治体の補助金制度やローンの活用も選択肢に入れると良いでしょう。自治体によっては所得条件や申請期限が設けられているため、事前に確認することが重要です。
また、今あるお墓を維持する場合との費用比較を行うことで、長期的な負担を見据えた判断ができます。
最終的には、家族や親族の意思を尊重しながら、費用面と精神的満足度のバランスをとった選択を見つけることが、安心して先祖を供養するための大切なプロセスとなるのです。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。