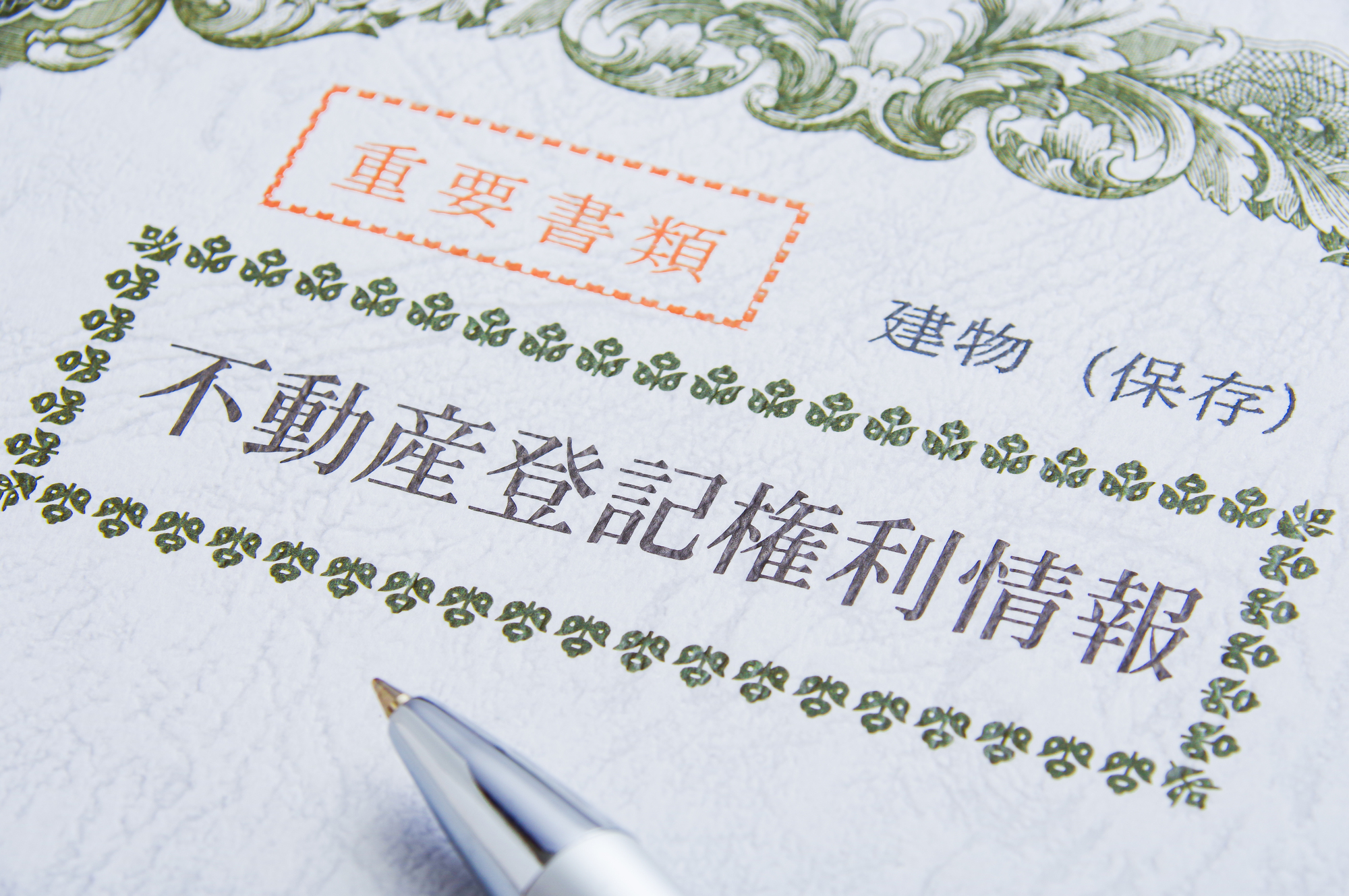公開日:2025.08.01 更新日:2025.07.29
登録免許税の免除・軽減措置を徹底解説~相続登記や住宅購入の場合など~

登録免許税は、不動産の売買や相続などで登記を行う際に課される税金です。住宅の取得や相続登記などを行う際には必ず発生するので、できる限り負担を抑えたいと考える方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、登録免許税の基本的な仕組みから、計算方法や免税、軽減措置の具体例、手続きの流れや注意点までをわかりやすく紹介します。制度の内容をしっかり把握し、必要な書類やスケジュールを整えることで、余計な出費を防ぎつつスムーズに登記を進められるはずです。
目次
登録免許税とは?基本概念と課税対象
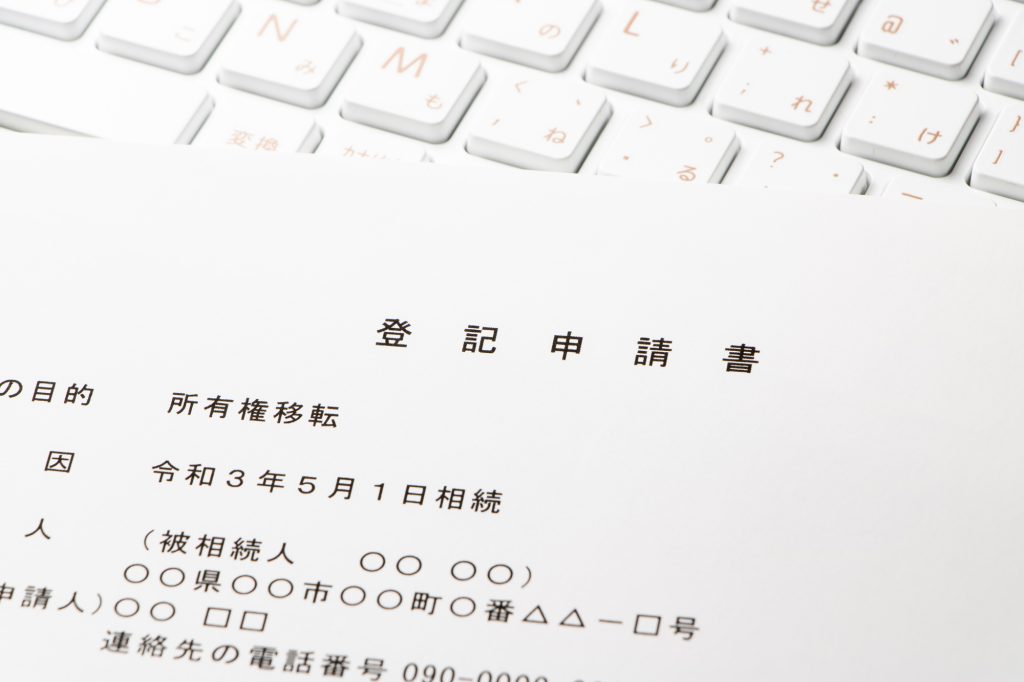
登録免許税は、不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録を行う際にかかる税金です。空き家や土地に関しては、所有権を登記するときや、ローンが残っている場合に抵当権を削除するとき、すでに登記されている情報を修正するときなどにかかります。
税金を納める人は原則として登記を申請する人となっています。たとえば不動産を購入または相続した人が自ら登記を行う場合は、本人が納めることになりますし、司法書士に依頼した場合は、本人に代わって司法書士が納付手続きを行うのが一般的です。ただし、納税義務そのものはあくまで依頼者本人にあります。
税額は登記の種類や対象となる不動産の評価額に応じて異なり、数千円程度のものから、内容によっては十万円を超えることもあります。
登録免許税の計算方法と税率

登録免許税は、「固定資産税評価額 × 税率」で計算されます。不動産登記では、土地と建物それぞれの評価額に応じて課税されるのが一般的です。
税率は登記の種類によって異なり、以下のように定められています。
土地に関する主な登記の税率(所有権移転登記)
- 売買による場合:2.0%(2026年3月31日までに登記を受ける場合は1.5%)
- 相続による場合:0.4%
- その他(贈与・交換・収用・競売など)による場合:2.0%
建物に関する主な登記の税率
- 新築時の所有権の保存:0.4%
- 売買または競売による所有権の移転:2.0%
- 相続による所有権の移転:0.4%
- その他(贈与・交換・収用・競売など)による所有権の移転:2.0%
土地の評価額による計算例
たとえば、評価額が1,000万円の土地を取得して所有権移転登記を行う場合、登録免許税は以下のように計算されます。
売買による場合(2.0%)
1,000万円 × 2.0% = 20万円
相続に寄る場合(0.4%)
1,000万円 × 0.4% = 4万円
建物の評価額による計算例
たとえば、評価額が1,500万円の新築住宅について、所有権の移転登記を行う場合の税額は次の通りです。
- 売買による場合(2.0%)
1,500万円 × 2.0% = 30万円 - 相続による場合(0.4%)
1,500万円 × 0.4% = 6万円
相続登記の登録免許税が免税されるケース

相続によって不動産を取得した場合でも登録免許税はかかりますが、以下のような場合は免税される可能性があります。
- 相続登記が完了する前に相続人が死亡してしまった
- 不動産の価額が100万円以下
具体的にどのような場合に免税されるのか、詳細な条件を見ていきましょう。
相続登記を行わずに死亡した場合
相続による登記が完了する前に相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生する「2次相続」が発生した場合は、すでに死亡した1次相続に関する登録免許税は免除されます。これは租税特別措置法に基づいて適用され、2027年の3月31日までの期限付き制度として運用されています。
たとえば、被相続人AからBへの相続が発生したものの、所有権の移転が完了する前にBが死亡し、さらにBからCへの相続が発生した場合、AからB、BからCと2回の登記が必要になり、それぞれに登録免許税がかかります。しかしこの制度を使えば、AからBへの登記に必要な登録免許税が免除されます。
不動産の評価額が100万円以下の土地の場合
不動産の価額が100万円以下の土地を相続により取得した場合は、土地の所有権の保存登記と所有権の移転登記にかかる登録免許税が免除されます。こちらも2027年の3月31日までの期限付き制度です。
適用されるかを判断するには、不動産の価額となる、固定資産税の評価額を確認しましょう。固定資産税課税台帳に価格が掲載されている場合はその価格が、ない場合は登記官が認定した価額が適用されます。登記官が認定した価額を確認するには土地を管轄する登記所に問い合わせてください。
住宅用家屋に関する軽減措置が適用されるケース

住宅の取得にあたっては、一定の要件を満たす住宅用家屋について、登録免許税の軽減税率が適用される特例があります。これは、自己の居住を目的とした住宅取得に対して国が支援を行うもので、登記時の税負担を大幅に減らすことができます。
新築・中古両方に適用される軽減措置
- 住宅ローン等に伴う抵当権設定登記:通常0.4% → 軽減後0.1%
新築住宅で軽減措置が適用される行為
- 住宅用家屋の所有権の保存登記
- 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記
- 認定低炭素住宅の所有権の保存登記
中古住宅やリノベーション住宅で軽減措置が適用される行為
- 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記
ここでは、新築住宅に適用される軽減措置と中古住宅やリノベーション住宅に適用される軽減措置を詳しく見ていきましょう。
新築住宅に適用される軽減措置
新築住宅を取得し、所有権の保存登記を行う場合は、登録免許税の税率が0.4%から0.15%に引き下げられます。さらに、長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合は、0.1%まで軽減されます。
- 住宅用家屋の所有権の保存登記:通常0.4% → 軽減後0.15%
- 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記:通常0.4% → 軽減後0.1%
- 認定低炭素住宅の所有権の保存登記:通常0.4% → 軽減後0.1%
適用要件
- 床面積が50㎡以上であること、新築または取得後1年以内の登記であることなど
- 1の条件に加えて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号イに掲げる住宅に該当する住宅用家屋であること
- 1の条件に加えて都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当する住宅用家屋であること
適用期限
- 2027年3月31日まで
中古住宅やリノベーション住宅への軽減措置
中古住宅を取得する際には、特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅に該当する場合と、さらに特定の増改築が行われた場合に軽減措置が適用されます。
- 特定認定長期優良住宅の所有権移転登記:通常2.0%→0.2%
- 認定低炭素住宅の所有権移転登記:通常2.0%→0.1%
- 買取再販で特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記:通常2.0%→0.1%
適用要件
- 床面積が50㎡以上であること、新築または取得後1年以内の登記であること、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号イに掲げる住宅に該当する住宅用家屋であることなど
- 床面積が50㎡以上であること、新築または取得後1年以内の登記であること、市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当する住宅用家屋であることなど
- 宅地建物取引業者が中古住宅を買い取り、耐震改修工事やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事など特定の増改築を行った住宅用家屋であること
適用期限
- 2027年3月31日まで
登録免許税軽減措置の申請方法と必要書類

登録免許税の軽減措置を受けるための手続きと必要書類は、適用される区分によって異なるため、それぞれよく確認する必要があります。特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅においては、それぞれの認定を受けた書類が必要になるので、認定を受けた書類は大切に保管しておいてください。
各区分の具体的な手続きは国税庁のウェブサイトをチェックしたうえで、不動産会社や司法書士に相談しながら進める必要があります。
ここでは、それぞれの区分で共通している大まかな手続きの流れや必要書類の一部を紹介します。
手続きの流れ
登録免許税の軽減措置を受けるための大まかな流れは以下のとおりです。
- 各種証明書の準備
- 住宅用家屋証明書の発行
- 1、2の書類を添付して登記申請を行う
軽減措置を受けるには、まず特定認定長期優良住宅や特定の増改築などを行ったことを証する書類の準備が必要です。これらが準備出来たら、住宅が立地している市区町村で住宅用家屋証明書を発行してもらいましょう。
必要書類をそろえたら、登記申請書を作成し、法務局の窓口で提出します。不備がなければ、軽減後の税率が適用され、所定の税額を納付すれば登記が完了します。
申請時に必要となる書類一覧
軽減措置の申請に必要な書類は、本来の登記申請に必要な書類に加えて、軽減措置を受けることができる家屋であることを証明する書類が必要になります。
たとえば、住宅を新築した場合の軽減措置を受けるためには以下のような書類が必要になります。
- 住宅用家屋証明申請書
- 次の1~3のいずれか
- 1.当該家屋の登記事項証明書
- 2.当該家屋の登記完了証
- 3.当該家屋の確認済証及び検査済証
- 住民票
など
さらに、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅による軽減措置を受けたい場合は、それぞれの認定申請書や認定通知書が必要になります。
申請書類は受ける軽減措置によって変わってくるので、具体的な内容は法務局の窓口で確認しましょう。
軽減措置の適用外となるケースと注意点

登録免許税の軽減措置で特に気を付けたいのは以下の2つのケースです。
- 住宅用家屋以外の建築物には適用されない
- 贈与を原因とした登記には適用されない
登録免許税の軽減措置は、あくまで個人が住む住宅を対象とした制度です。そのため、住宅用家屋証明が取得できない、事業用の建築物のようなものには適用されません。
また、所有権移転登記をする際には、その原因が売買および競落に限定されています。住宅用家屋を登記する場合でも、贈与によって得たものは対象外です。
そして、軽減措置の手続きにはそれぞれ申請期限が設けられています。制度が延長されるか分からないので、必ず期限内に対応してください。
まとめ
ここまで、登録免許税の基本的な仕組みから、活用できる軽減措置までを解説してきました。不動産登記を行うにあたって避けて通れないものなので、制度をよく理解して可能な限り節約を心がけましょう。
特に住宅の取得や相続に関しては、免税・軽減措置をうまく使うことで、経済的な負担を大きく減らすことができます。制度には申請期限があるので、物件を取得する時期や準備期間をあらかじめ考慮して手続きすることをおすすめします。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。