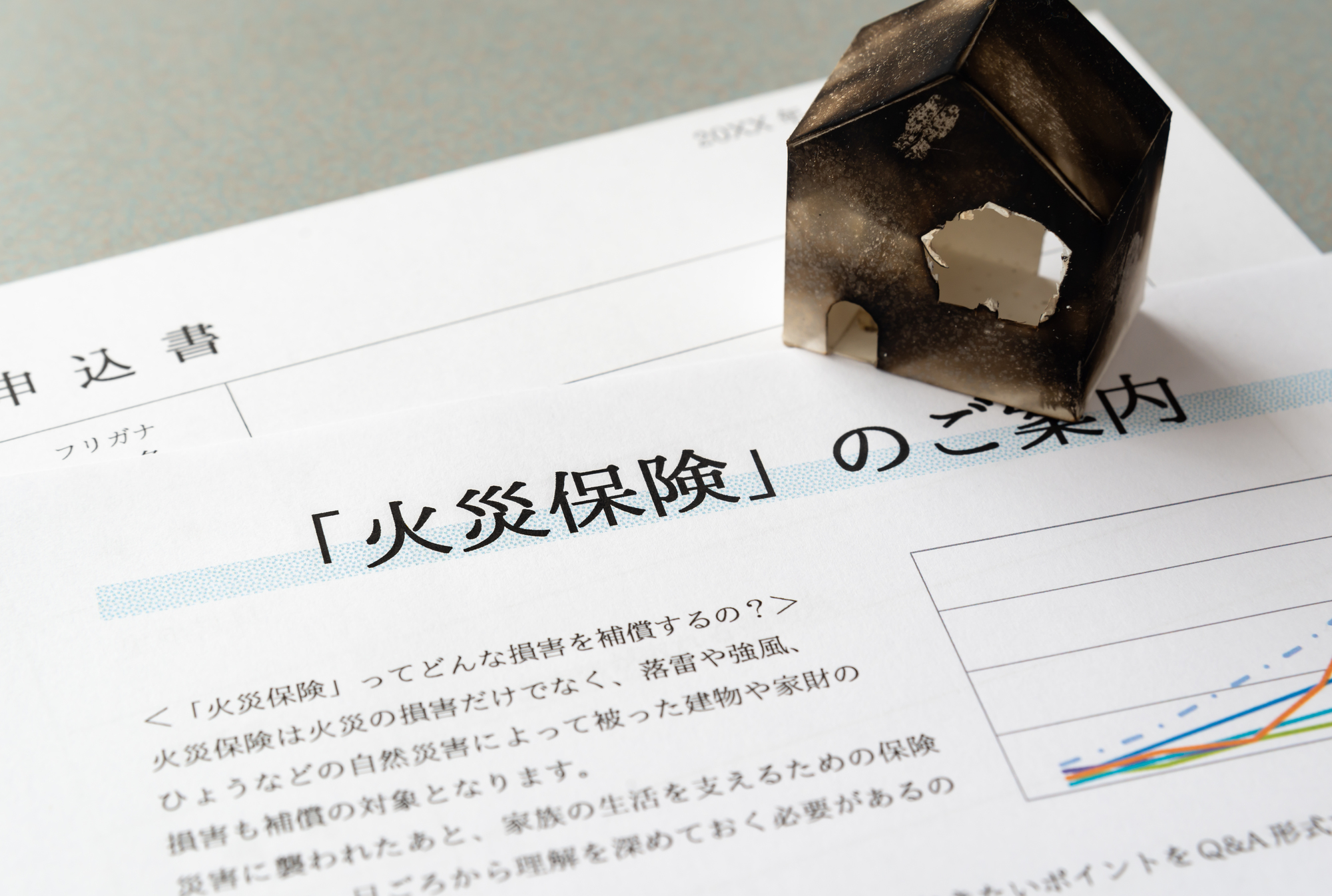公開日:2025.08.02 更新日:2025.09.16
空き家に火災保険は必要?リスクと補償内容を徹底解説
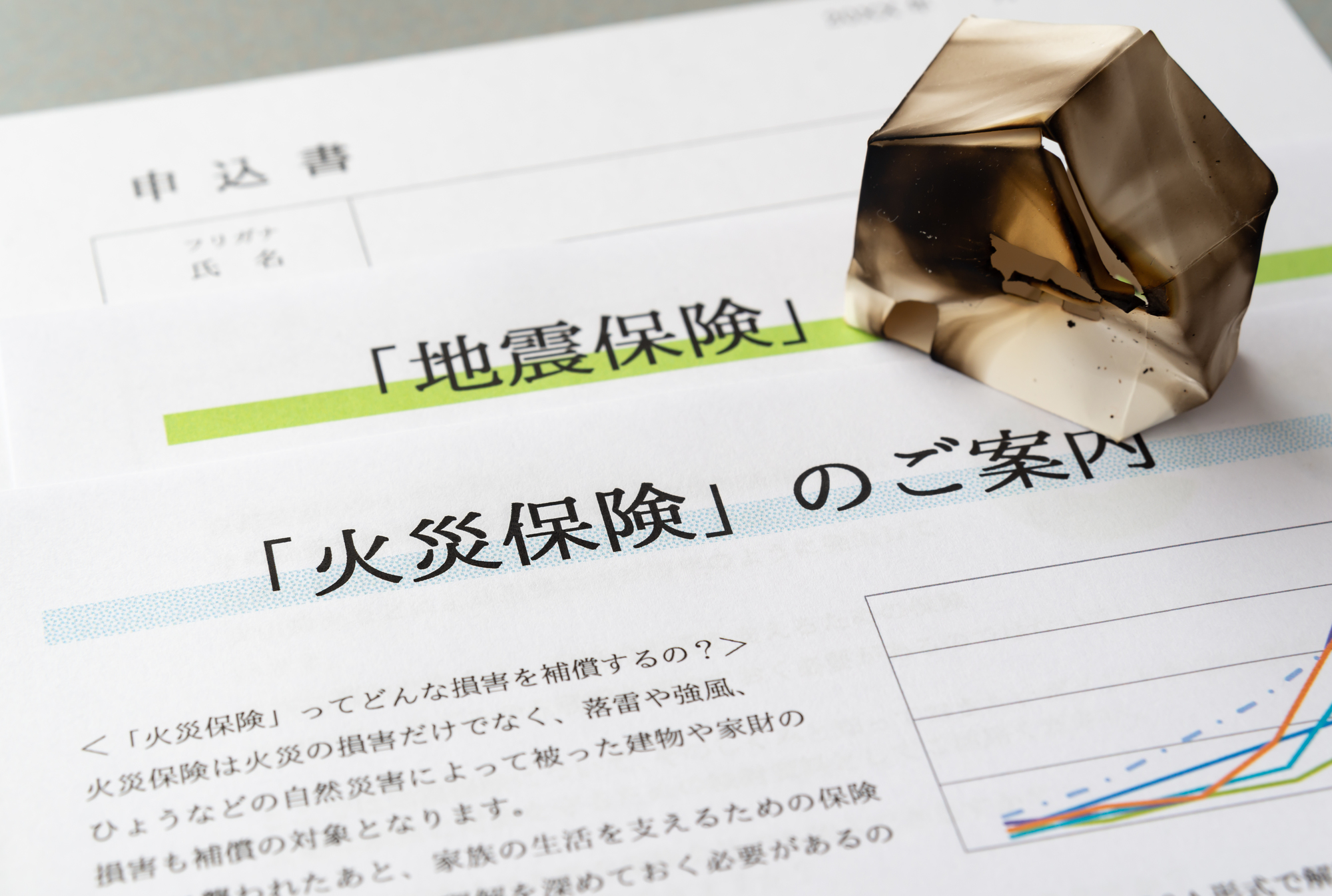
近年、空き家の増加に伴い、防犯や災害対策の必要性が高まっています。住んでいないからといってリスクがないわけではなく、放火、漏電、隣家からのもらい火など、常に火災リスクにさらされている点には注意が必要です。実際に火災が発生した場合、建物の修繕費や廃材処分費など多額の費用負担が発生する可能性があり、適切な保険加入による備えが重要となります。
本記事では、空き家が抱える火災や自然災害のリスク、火災保険の保険引き受け条件、さらに賠償責任リスクをカバーする方法まで、火災保険を検討する際に押さえておくべきポイントを解説します。単なる保険料比較ではなく、使用目的や建物状態に応じた補償選定が、空き家管理の第一歩です。
目次
空き家が抱えるリスクと火災保険の必要性

空き家は人が常時いないため、防犯や建物管理が手薄になりがちです。こうした空き家特有のリスクを理解し、保険などで適切に備えることが重要となります。
なかでも大きなリスクは火災です。住人がいないことから小さな異変に気付くのが遅れ、被害拡大や発見の遅れにつながりやすいのが特徴です。放火や老朽化した配線からの出火のほか、隣地からの飛び火による火災も想定しておかなければなりません。同時に、空き家の多くは建物自体が古いケースもあるため、定期的に点検を実施しリスクを軽減することが重要です。
さらに、火災発生後には焼却の後始末や近隣住民への補償など、思わぬ出費につながる場合があります。特に空き家の場合、損傷が甚大になるまで気づきにくいことも多く、多額の修繕費を要する事例も報告されています。こうした費用負担を最小限に抑えるためにも、建物の状況に応じた火災保険契約を結び、十分な補償を確保しておくことは不可欠です。
放火や漏電などによる火災リスク
空き家は人の出入りがほとんどないことから、放火の標的になる可能性が高いといわれています。加えて、電気設備が老朽化している場合には漏電のリスクも否めません。一度火が出ると発見が遅れるため、建物全体に燃え広がってしまうケースも多いのが特徴です。火災保険によって、修繕費や解体費などの経済的負担を軽減できる場合があるため、万が一の備えとして検討する価値があります。
自然災害による損壊と補償
台風や豪雨、豪雪による建物の損壊は、住んでいない空き家であっても容赦なく発生します。屋根や外壁へのダメージが重なると、雨漏りや構造劣化につながる可能性が高まります。火災保険には、風災や水災等を補償範囲に含む商品も多く存在します。自然災害による損壊に備えるには、補償内容を確認したうえでの保険選定が重要です。
空き家所有者が負う賠償責任リスク
空き家で火災が起きて近隣を巻き込んだ場合、民法第709条の不法行為責任等に基づき、状況によっては所有者に損害賠償責任が生じる可能性があります。
損害の範囲が大きければ、個人での対応が困難になるケースも考えられます。 火災保険に特約として個人賠償責任補償や類似の補償を付帯すれば、近隣への被害や見舞金などにも対応できるため、加入を検討する価値は高いでしょう。近隣への被害や見舞金対応まで視野に入れた保険設計を行うことが推奨されます。
空き家向け火災保険の基礎|住宅物件と一般物件の違い

空き家は住居として使用していないため、通常の火災保険ではなく「一般物件」扱いと判断されることがあるため、その違いを理解した上での加入がポイントです。
一般的に、火災保険は住宅物件として機能している建物を対象とします。ところが、空き家となると人が常時住んでいない状態が続くため、ビルや店舗などと同様に非住宅用途として「一般物件」扱いされ、保険料が高めに設定されることがあります。契約を結ぶ際は、建物の用途区分がどのように扱われるか、具体的に保険会社の約款や重要事項説明書を事前によく確認しましょう。
空き家であっても、将来的に居住を再開する予定があれば、住宅物件として認められるかどうかを相談することが大切です。契約時の申告内容や、住民票の移転といった居住実態を示す客観的な状況によっては、住宅物件扱いとなって保険料を抑えられる場合があります。ただし、空き家の実態を正確に保険会社へ伝えておかないと、告知義務違反などにより、いざというときに保険金が支払われない可能性や、契約が解除される可能性があるため注意が必要です。
空き家が「住宅物件」として認められる条件
空き家でも定期的に人が滞在している実態があれば、住宅物件として認められる可能性があります。例えば、週末だけ利用するセカンドハウスに近い状態であれば、住宅用物件としての取り扱いが可能となるケースもあります。ただし、保険会社ごとに基準が異なるため、具体的な滞在頻度や、それに伴う保険会社への申告手続きについては、契約前に書面等で確認し記録を残しておくとよいでしょう。
地震保険は空き家でも加入できる?
地震保険は火災保険とのセット契約が基本ですが、一般物件扱いの場合でも付帯できるかどうかは保険会社の規定により異なります。空き家では火災や風水害だけでなく、地震による倒壊や破損リスクも見逃せません。事前に保険会社の規定をよく確認し、必要に応じて地震保険の検討も行うことがリスク管理上有効です。
空き家の火災保険料はいくら?相場と保険料を抑えるコツ

空き家の火災保険料は、建物の築年数や構造などさまざまな要素で決まります。保険料を少しでも抑えるテクニックを押さえておきましょう。
保険料は建物の構造、立地条件、築年数などによって大きく変動します。空き家は「管理が不十分」と判断される傾向があるため、火災リスクが高いと見なされ、保険料が割高になるケースが多い点を認識しておきましょう。特に住宅物件ではなく一般物件扱いとなる場合、保険料はさらに上昇する可能性があります。また、木造か鉄骨造かといった構造の違いも保険料に影響するため、複数の保険会社から見積もりを取り、比較検討することが重要です。
保険料は自然災害リスクの上昇や再保険コストの増加などの影響で、年々上昇傾向にあります。こうした背景を踏まえ、長期契約によって保険料を一定期間固定する方法や、複数物件をまとめて契約する「一括契約割引」を活用するのも有効です。さらに、保険会社によっては、ホームセキュリティや火災警報器の設置によって割引が適用される場合もあります。火災リスク低減と保険料節約を両立できる環境整備を検討しましょう。
補償範囲を限定して保険料を節約する方法
空き家火災保険の補償範囲を厳選することで、保険料を抑えることが可能です。たとえば、水災の危険性が低い地域なら水災補償を外す、家財が何も置かれていないなら家財補償を外すなど、建物や地域のリスク実態に応じた補償選定が効果的です。ただし、補償を限定することで将来的な事故に対応できないリスクもあるため、立地や空き家の利用状況をよく考慮して決定する必要があります。
保険料値上げに備えるポイント
火災保険料は、台風や豪雨などの自然災害の多発化や、保険会社のリスク評価基準の見直しなどにより、上昇傾向が続いています。長期契約を結ぶことで一定期間の保険料を固定化できるタイプのプランもあり、将来的な値上げリスクを軽減できるメリットがあります。また、火災保険を他の保険(例:地震保険、個人賠償責任保険など)とパッケージ契約することで割引が適用されることもあるため、総合的なプランニングを行って家計への負担を抑えることが可能です。
空き家に火災保険をかける際の注意点と選び方

空き家は一般的な住宅物件ほど火災保険の引き受け条件が緩くない場合もあります。加入を検討する際には、チェックすべきポイントを整理しましょう。
空き家に火災保険をかける場合は、通常の住宅物件よりも厳しい引き受け条件になることがあります。特に、築年数が古すぎる物件や、修繕が長年行われていない物件だと、保険会社が契約を受け付けてくれないケースもあるため注意が必要です。定期的な管理や修繕によって空き家の状態を良好に保つことは、契約時の審査をスムーズに進め、より条件の良い内容で契約できる可能性を高めます。
また、火災リスク以外にも隣家への延焼リスクや、経年劣化による倒壊リスクなどが懸念されます。こうした周辺トラブルに備えるには、個人賠償責任特約や破損・汚損等の特約、電気設備の補償などをカバーできる保険商品を選ぶことが大切です。特約の有無や補償範囲は保険会社ごとに異なるため、複数の保険プランを比べながら自分の物件に最適なものを見極めましょう。
加入条件や保険会社の引受基準を確認
保険会社によっては空き家特有のリスクを厳しく見積もり、契約を断られる場合があります。特に、築年数が数十年を超える物件や、雨漏りなどの重大な損傷が放置されている場合は引き受け不可となる事例も少なくありません。契約前に建物の状態を把握し、修繕や点検を行っておくことで、引受基準を満たしやすくなるでしょう。
共済・団体保険は空き家に適用できる?
一部の共済や団体保険では、空き家そのものを補償対象としていないことがあります。空き家の補償可否は加入条件(組合員・会員の属性)や建物の状況によって変わるため、補償対象として認められるかを事前に確認することが重要です。共済ならではの手頃な掛金を期待できる場合もあるため、空き家であっても利用できる商品がないか複数の選択肢を比較しながら情報収集をしてみましょう。
賠償責任特約の付帯の重要性
火災が発生し近隣住民や建物に被害が及んだ場合、その賠償費用は極めて大きな負担となります。特に空き家の火災は被害範囲が拡大しやすく、万が一の際には高額の賠償責任を負うリスクもあります。賠償責任特約を付帯しておけば、こうしたトラブルに対応しやすくなるため、火災保険加入時の重要な検討ポイントといえます。なお、賠償責任が法的に発生するかどうかは過失の有無など個別の事情により異なるため、補償内容の詳細は契約前に確認が必要です。
空き家でも加入できるおすすめ火災保険5選

空き家であっても引き受け対象として明示されている火災保険商品を提供している保険会社はいくつか存在します。代表的な保険会社を挙げ、それぞれの特徴を紹介します。
大手損害保険会社を中心に、空き家でも引き受け可能な火災保険商品を提供している事例があります。保険料はもちろん、補償内容や特約の充実度、サポートの体制などを総合的に比較して選ぶことが大切です。大手企業は代理店数が多いため相談しやすく、商品バリエーションも豊富な点が魅力と言えます。
ただし、空き家の状態や築年数によっては保険料が高額になることもあるため、それぞれの見積もりをよく確認しましょう。保険会社によっては空き家の条件を満たさない場合、引き受け不可となることもあります。必要に応じてオプションを切り分けたり、セキュリティ対策や建物の修繕を施して保険料を抑える方法も検討することをおすすめします。
東京海上日動火災保険
大手損保として長い歴史を持ち、カスタマイズ性の高さが大きな強みです。空き家でも必要な補償を追加しやすいため、建物の老朽度合いや地域リスクに応じた保険プランを組み立てやすいのが魅力でしょう。サポート体制や事故対応も充実しているため、空き家での保険加入に不安がある場合でも安心度が高いと言えます。
損保ジャパン
代理店ネットワークが国内最大級とされ、相談窓口の多さや対応力に定評があります。長期契約や団体割引など多彩な商品ラインナップを揃えており、空き家向けにリスクをカバーするプラン設定が可能です。築年数や構造、立地条件などに応じて柔軟に対応してくれるため、比較検討の候補に入れやすい保険会社の一つです。
あいおいニッセイ同和損保
代理店での対面相談とダイレクトネット契約を両立させており、様々な顧客ニーズに合致した商品提供が可能です。空き家特有の放火リスクや自然災害リスクについても、個別に補償を選べるケースが多いため、余分な保険料をかけずに必要な範囲を手厚くすることができます。また、空き家の状態に応じたリスク調査や契約提案が可能な点も好評です。
三井住友海上保険
火災や風水害に加えて、地震リスクにも対応しやすいプランを展開しているのが特長です。通常の火災保険でも空き家対応が相談可能な場合があり、複雑な条件でも解決策を提案してくれる柔軟性があります。住宅物件か一般物件かによって引き受け条件が変わるため、事前確認が必要です。幅広い補償範囲と充実した事故対応サービスの組み合わせにより、安心して契約を任せられる点が魅力です。
ソニー損保
ネット完結型のサービスが充実しており、見積もりから契約までスムーズに行える利便性が特徴です。空き家であっても比較的リーズナブルなプランを選べる場合があり、短時間で複数パターンのシミュレーションが可能です。ただし、完全な無人・無家財の空き家には非対応の場合もあるため、利用目的に応じた可否の確認が必要です。コストパフォーマンスを重視する方には一考の価値があると言えるでしょう。
空き家保有でかかる費用|火災保険以外のコスト

保険料以外にも、空き家を所有する上ではさまざまな費用が発生します。代表的なコストには税金や管理費などがあります。
空き家を所有していると、固定資産税や都市計画税などの税負担は居住の有無に関係なく続きます。さらに、空き家がおかれている場所によっては住宅が使われていないことで減税措置の対象から外れてしまうケースもあり、結果的に税金の負担が増えることがあります。具体的には、住宅用地に対する「固定資産税の課税標準の特例措置(小規模住宅用地の軽減)」が適用除外となる場合があります。こうしたコストを軽減するためにも、空き家の用途や活用方法を見直すことが大切です。
空き家管理のための清掃や設備点検、庭木の剪定なども定期的に行わなければ、周囲に迷惑をかける恐れがあります。適切なメンテナンスを怠ると雨漏りやシロアリ被害などが深刻化し、修繕費が膨大になることもあるでしょう。また、第三者の侵入や不法投棄といった防犯リスクも高まります。とりわけ、自治体から特定空き家に指定されると強制的な措置や罰則につながる場合があるため、早めの対策や管理体制を整えておくことが望まれます。
固定資産税・都市計画税などの税金
土地や建物を持っている以上、賃貸や居住の有無にかかわらず税金は毎年課されます。空き家が長期間放置されると住宅用地特例が外れ、税率が上がる可能性があるため注意が必要です。この場合、固定資産税が最大で6倍程度に増額することもあります(※小規模住宅用地:1/6→通常課税)。地域によっては独自の税減免制度もあるため、自治体の案内をよく確認して資金計画を立てましょう。
管理費・維持費と定期点検の重要性
空き家の維持管理は、火災保険だけではカバーしきれない部分のリスク管理にもつながります。建物内部の水漏れや電気設備の不具合、外壁の亀裂などは日常的な点検が欠かせません。加えて、外構や植栽の管理不備は近隣から苦情につながることもあります。適切なメンテナンスを行うことで、保険の引き受け条件を有利にしたり万が一の損害を最小限に抑えられます。
特定空き家指定のリスクと対策
特定空き家に指定されると、自治体から「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき修繕や解体の勧告・命令を受け、従わない場合は行政代執行などの強制措置が取られることもあります。さらに、勧告を受けると住宅用地特例(固定資産税軽減措置)も外されるため、税負担も増す可能性があります。大幅な費用負担が発生するため、早めに建物の状況を把握して危険性を排除する必要があります。地域によっては補助金や支援制度がある場合もあるため、活用しながら適切に対処していくことが望ましいです。
空き家の売却・活用を検討するメリット

火災保険料や維持費を支払い続けるよりも、売却や賃貸などで資産を活用した方が、長期的に見て経済的メリットが大きくなるケースがあります。
空き家を所有したままでは、毎年の固定資産税や管理費用、火災保険料などがかかり、特に利用予定のないまま長期間保有し続けると、負担が累積していきます。もし需要があるエリアであれば、仲介売却によって思いのほか高値で取引されることも珍しくないため、所有コスト以上の利益を得られる可能性があります。物件の老朽度合いを考慮し、最低限の修繕やリフォームを行ってから売却することで、さらに高額が期待できる場合もあります。
一方、需要が低い地域で空き家を売却したい場合は、買取専門業者に相談するのも一案です。仲介での売却が難しくても、ある程度の条件を満たしていれば一括で買い取ってもらえる可能性があります。空き家の立地や築年数、法的な権利関係(共有名義など)を整理したうえで、早めに出口戦略を立てておくことが大切です。売却以外にも、リフォームや改装をして賃貸物件として運用する選択肢もあるため、立地や資金計画に応じて柔軟に検討しましょう。
需要が高い地域なら仲介での売却を検討
人気エリアや駅近物件などは不動産市場での需要が高いため、通常の仲介売却でも買い手がつきやすい傾向があります。空き家でも魅力的な条件を備えていれば、リフォーム物件として再活用を考える投資家や個人需要が見つかりやすいでしょう。不動産会社の査定を複数取り、想定売却益を明確にすることで、火災保険料や維持管理費の負担を一気に解消できる可能性があります。
需要が低い場合は買取業者を利用
需要の低い地域や築年数の古い空き家は、仲介売却では時間がかかり過ぎたり希望価格で売れない場合があります。買取業者ならスピーディーに商談を進めることができ、ある程度の価格でまとめて売却できる可能性が高いです。ただし、仲介より売却価格が相場より低くなることが一般的なため、緊急性や保有リスクとのバランスを見極めることが重要です。現金化を急ぐ場合や修繕資金を確保したい場合にも有効な選択肢となります。
空き家の火災保険に関するFAQ

よくある疑問や不安点に対して、ポイントを絞って解説します。保険選びの参考にしてください。
空き家特有の保険の疑問として多いのが、保険料が通常の住宅より高くなる理由や地震保険・共済などを付帯できるかどうかです。空き家の状態を保険会社に正確に申告し、他社との比較を行うことが、保険料や補償内容を最適化する鍵となります。
また、火災以外のリスクもしっかりと認識し、長期的な視点で自分の空き家をどう活用するかを見極めることも重要です。短期的にはコストがかかっても、適切なタイミングや方法で処分・活用を考えれば、総合的にリスクと費用を抑えることができるでしょう。
空き家の火災保険、保険料相場はどれくらい?
空き家は常時管理されていない分、火災リスクが高いと見なされ、一般住宅よりも保険料が高くなる傾向があります。建物の構造や築年数、立地条件などによって保険料に差が出るため、複数社で見積もりを取り比較することが大切です。目安としては、通常の住宅物件より2~5割程度高くなるケースが一般的とされていますが、これは補償範囲や加入条件によっても大きく異なります。
空き家でも地震保険や共済に加入できる?
地震保険や共済は、商品種別や運営団体の規定次第で空き家でも加入可能な場合があります。ただし、居住実態を要求するケースや築古物件を受け付けないケースもあるため、事前に加入条件を確認することが必須です。とくに地震保険は、住宅物件として認められないと付帯できないケースがあるため、空き家の用途区分や家財の有無が審査対象になることがあります。契約時には建物の構造や耐震性が審査に影響を与える場合もあるので注意しましょう。
保険料を抑えるための具体的なポイントは?
長期契約による保険料の固定化や、不必要な補償を省いて範囲を限定する方法が代表的です。また、老朽化した部分を修繕したり、防犯カメラなどのセキュリティ設備を導入して火災や犯罪リスクを下げることも有効な手段となります。さらに、ホームセキュリティ導入割引、建物の構造区分(例:省令準耐火)に応じた料率割引が適用される場合もあります。複数の割引制度を併用することで、トータルの保険料を大幅に縮小できる可能性があります。
まとめ

空き家は火災や自然災害のリスクを抱えるため、保険で十分に備えることが欠かせません。必要な補償を見極めて、安心できる備えを整えましょう。
空き家でも火災保険が必要な理由は明確で、人がいないからこそ火災や損壊を早期に発見できず、被害が大きくなりやすい点にあります。住居用から一般物件扱いになる場合の保険料の違いや、地震保険の付帯条件など、通常と異なる点をしっかり理解した上で検討することが重要です。特に、保険会社ごとに引受条件が異なるため、空き家の状態や契約条件によっては、加入が難しかったり保険料が高額になったりするケースもあるため、複数の保険会社から見積もりを取得して比較するのがおすすめです。
一方で、空き家に火災保険をかけるだけでなく、今後の活用や売却の可能性も視野に入れることで費用を抑えられる場合があります。特に、空き家が「特定空き家」に指定された場合は固定資産税の軽減措置が打ち切られるなど、金銭的負担が増すリスクもあります。維持費の負担や将来的な資産価値を考慮し、「アキサポ」のような空き家活用の専門サービスや、必要に応じて弁護士、司法書士、税理士といった専門家にも早めに相談するなど、総合的に最善の対策を選ぶことが大切です。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。