公開日:2025.08.04 更新日:2025.09.16
【徹底解説】登録免許税の軽減措置:相続登記・新築・中古物件への適用条件と注意点
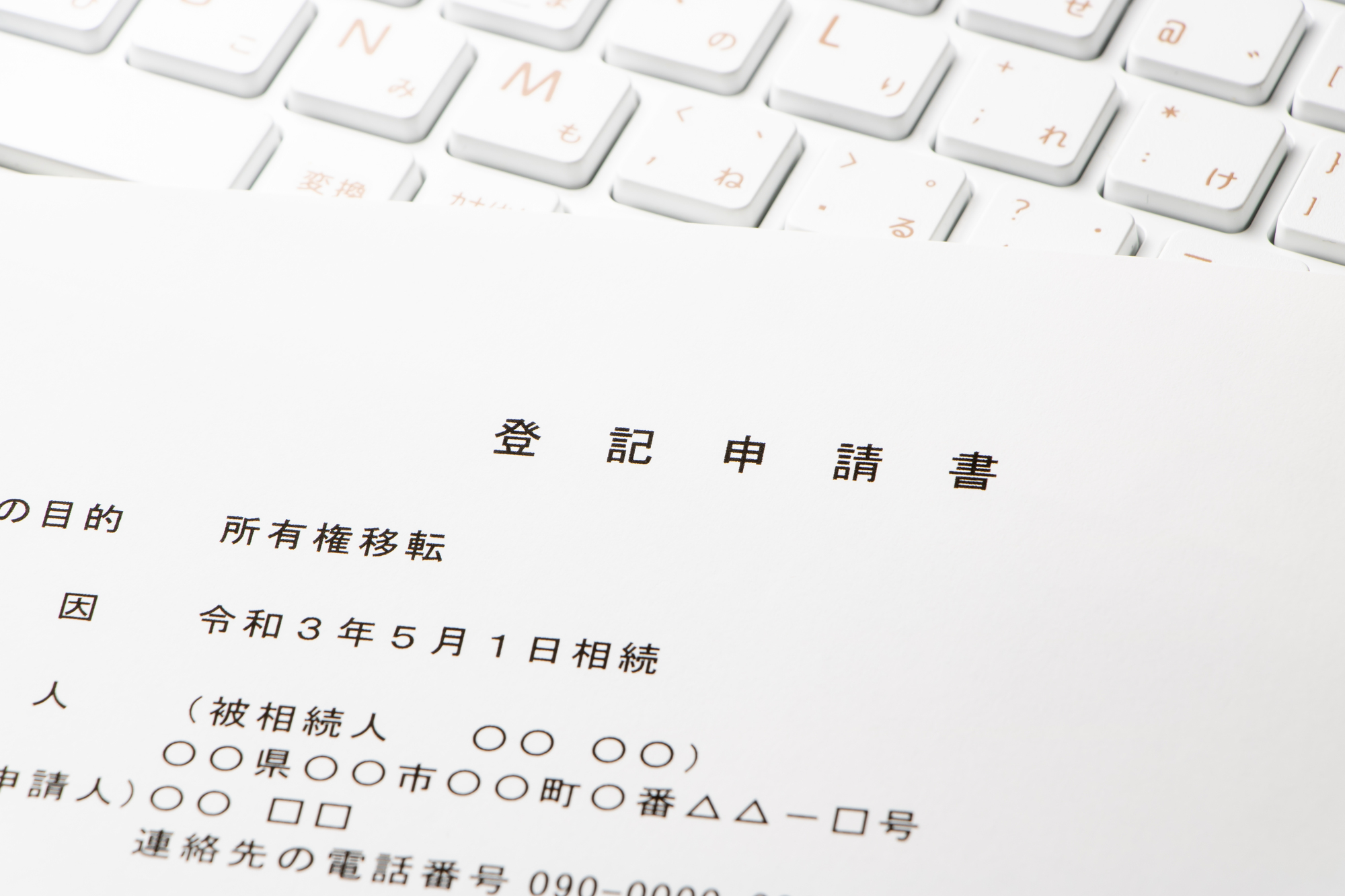
各種登記手続きの際に発生する「登録免許税」。実は軽減措置や免税措置が設けられていることをご存じでしょうか?
本記事では、相続登記や住宅の新築・中古物件などに適用される登録免許税の軽減措置や免税措置について、基本知識から具体的な手続き上のポイントまで徹底解説します。これらの制度を正しく理解して、節税につなげましょう。
目次
登録免許税とは?基礎知識と発生する場面

まずは登録免許税がどのように発生するのか、その概要と課税対象を理解しておきましょう。
登録免許税がかかる登記の種類とケース
各種登記を行う際に課される登録免許税。必要なケースとしては、主に以下のケースが挙げられます。
- 不動産の所有権保存登記・移転登記
- 抵当権設定登記
- 商業登記
- 合併登記
- 産業財産権の登録
特に不動産関係の登記では、購入時だけでなく相続や贈与、共有者間での持分移転などの細かなシーンごとに登録免許税がかかります。通常は登記を申請する側が納税義務者となり、手続き時にまとめて支払うのが一般的な流れです。
登録免許税の計算方法と税率の基本
登録免許税を計算する際、まず課税標準となる金額を確認しておきましょう。不動産登記であれば固定資産税評価額が基準となり、商業登記などは資本金の額が課税標準となります。この金額に法令で定められた税率を乗じたものが、最終的な納税額です。
税率については、一般的な不動産の所有権移転登記では、評価額の1,000分の20(2%)が基本ですが、住宅用家屋や特定の要件を満たす場合には軽減税率が適用されるケースがあります。具体的な税率は各制度やその延長状況によって変動するため、登記申請時期と適用要件を正確に確認することが不可欠です。
住宅取得や相続など、主な対象となるシーン
登録免許税を支払わなくてはいけない主なシーンが、住宅を新築または購入するときと、相続によって不動産を取得するときです。
どちらも個人で発生することが多く大きな負担になることから、一定の要件下で軽減措置や免税措置が適用されることがあります。家族構成や評価額など、複数の条件が関係するため、該当するかどうかを早めに調べておくことが重要です。
登録免許税の軽減措置とは?概要と適用条件・期限

では、登録免許税の軽減措置とは具体的にどのようなものがあるのか、詳しく確認していきましょう。
住宅用家屋の軽減措置と必要要件
住宅家屋の登記は、一般家庭の家計負担を抑えることを目的に、軽減措置が設けられています。住宅用家屋の登録免許税軽減措置を受けるためには、床面積が50平方メートル以上であること、専ら居住の用に供されること、新築または取得後1年以内に登記すること(中古住宅の場合、築年数や耐震基準適合証明の取得など一定の要件を満たすこと)などが主な条件となります。
また登記申請の際には、市区町村から発行される住宅用家屋証明書、建築確認済証や検査済証(新築の場合)、耐震基準適合証明書(中古住宅の場合)など複数の書類の提出が必要です。これらはそろえるのに時間がかかる可能性もあるので、あらかじめ確認しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
軽減措置の適用期限と延長の有無
登録免許税の軽減措置には、適用される施行期間が設定されている場合があり、注意が必要です。例えば、土地の売買による所有権移転登記の軽減税率は、2026年(令和8年)3月31日までの適用が予定されており、この期限を過ぎると通常の税率に戻ることが見込まれています。
また、住宅用家屋については2027年(令和9年)3月31日までの軽減措置が適用対象になるケースが多いなど、期限や延長の有無が随時見直される点にも留意しなくてはなりません。延長措置が決定される場合もあるため、申請時期と最新の法改正情報をしっかりチェックしておくようにしましょう。
軽減措置を受けるための申請時のポイント
スムーズに登録免許税の軽減措置を受けるためには、事前に必要書類を正確にそろえておくことが非常に重要。特に住宅用家屋証明書は、税率軽減の根拠となる大切な証明書です。市区町村役場での発行手続きに時間がかかるケースも想定して、早めに手配しておきましょう。
また、提出書類の内容に不備があると再提出が必要となり、手続きが遅れる原因にもなります。取得した証明書の記載漏れや申請書類との食い違いがないか、細部まで確認することが重要です。もし手続きに不安がある場合は、司法書士など専門家への相談を検討しましょう。
相続登記における登録免許税の免税措置

ここからは、シーンを相続登記に絞って、登録免許税の免税措置の詳細についてご紹介。相続登記では、一般的には固定資産税評価額に一定の税率を掛け合わせた登録免許税がかかりますが、特定の要件を満たせば免税措置が適用される場合があります。
相続人が死亡した場合の免税特例と適用要件
登録免許税の免税措置が適用されるケースのひとつが、相続による所有権移転登記等が未了の間に、当該相続に係る不動産を取得した者が死亡した場合。これは、いわゆる二次相続や数次相続が発生し、登記手続きが複雑になることから、負担軽減を目的に登録免許税が免除されるという制度です。
この特例は相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行)に伴い創設されたものであり、2025年(令和7年)3月31日までの時限措置として、以下のいずれかの要件を満たす場合に適用されます。
(1)表題部所有者の相続人が、相続登記をしないまま死亡した場合
(2)不動産の価額が100万円以下の土地について、相続により所有権を取得した者が死亡した場合。
ただし、提出書類や期間など細かい要件が定められているため、法務局のサイトや司法書士など専門家の見解を参照し、該当するかどうか確認するようにしましょう。
100万円以下の土地を相続した場合の免税特例
相続した土地の評価額が100万円以下の場合も、登録免許税免除の特例が適用される可能性があります。これは主に、都市部以外の地域や利用価値が低い土地などを相続した際に適用されるケースが多く見られますが、評価額が100万円以下かどうかの判断は、固定資産税評価額で決まります。不動産会社による査定価格や売却見込み価格は登録免許税の計算とは無関係となる点に注意が必要です。なお、評価額は自治体から送付される固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書などで確認できます。
相続登記で注意すべき書類・手続きの流れ
相続登記を行うには、被相続人の戸籍謄本や住民票除票、相続人全員の戸籍謄本や住民票、さらに遺産分割協議書など複数の書類を用意し、相続関係説明図とあわせて法務局へ提出するのが一般的な流れです。
書類が不足していたり不備があったりすると再提出を求められ、余計な手間がかかるので、不明点は専門家にアドバイスを求めるなどして慎重に手続きを進めましょう。
新築・中古・リノベーション別:登録免許税の軽減措置とシミュレーション

登録免許税の軽減措置が受けられるかどうかは、物件の種類によっても変わります。今回は、「新築」「中古」「リノベーション」に分けてそれぞれの概要をまとめました。
新築一戸建てと新築マンションの場合
新築一戸建ての場合、固定資産税評価額は完成後に自治体が評価を行い、翌年度以降に評価額が確定します。そのため、タイミングによっては概算評価額をもとに登録免許税を納めるケースがあるため、実際の金額と異なることがある点に注意が必要です。
一方で新築マンションでは、敷地と建物の共有部分があるため、それぞれの持分に応じた評価額と税率で計算されます。購入時にデベロッパーや管理組合から税金計算の概算資料が提供されることが多いので、手続きの際はその数値を確認しながら進めるとスムーズです。
中古物件の場合
中古住宅では、築年数や耐震基準の適合状況などが軽減措置の可否を決めるポイントになります。例えば、一定築年数以内の住宅や、リフォームで耐震基準をクリアした物件などは、税率が優遇されることが多いです。
さらに、築年数によっては長期優良住宅や認定低炭素住宅として認定を受けられるケースもあり、その場合は追加の減税措置が上乗せされることがあります。確実に措置を受けるためにも、購入を検討している物件がどのような要件を満たしているか、事前に確認しておくようにしましょう。
リノベーション住宅の場合
大規模なリノベーションを行い、耐震基準適合証明書を取得した場合も、登録免許税を抑えられる可能性があります。特に、基礎や柱・梁などの構造部分を強化し、現行の耐震基準に合致するように改修すれば、税率軽減が受けやすくなるでしょう。
リノベーション後の住宅で軽減措置を受けるには、リフォーム工事証明書や耐震基準適合証明書などをあらかじめ用意し、登記申請の際に提出しなくてはなりません。さらに、工事請負契約書や設計図面なども要求されるケースがあるため、リノベーションの計画段階から証明書類の発行手続きについても確認しておくことが大切です。
登記手続きと登録免許税納付の流れ

ここからは、登記手続きと登録免許税納付の実際の流れをご紹介。書類不備を防ぐためのポイントもまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
登記の準備から申請までのプロセス
まずは、税額を確認して必要書類を用意しましょう。その後、登記書類を作成し、最寄りの法務局やオンラインシステムを利用して申請を行います。
登録免許税は、登記申請と同時に納付します。支払方法は収入印紙が一般的です。登記完了後は登記識別情報や登記完了証を受け取ることができるので、今後の手続きに備えて必ず保管しておきましょう。
書類不備を防ぐためのチェックポイント
書類に不備があると、再度作成・提出の手間がかかるため、チェックリストを作成しておくのがおすすめ。申請書の記載事項と添付書類が正しく対応しているか、ひとつずつ確認しながら作業することで、不備のリスクを減らすことができます。
特に、住宅の床面積や建築年月日、申請人の住所や相続関係などは記述ミスが多いため、念入りにチェックしておきましょう。
また印鑑を使用する場合は、実印と認印の使い分けにおいて誤りがないか、法定の押印要件を満たしているかも重要なポイントです。
まとめ:正しい知識と手続きで登録免許税を軽減しよう
登録免許税は、相続や不動産購入、会社設立など幅広い場面で発生しますが、本記事で解説した各種の軽減措置や免税措置を適切に活用することで、大きな節税効果を得られます。そのためにも、住宅用家屋証明書や耐震基準適合証明書など、条件を証明する書類を早めに準備することが重要です。
もし自力での手続きに不安がある方は、ぜひ「アキサポ」にご相談ください。空き家活用のプロとして、登録免許税の手続きなど、法律関連についても手厚くフォロー。特に、不動産の購入・相続後の活用や売買を検討している方は、物件のさまざまな可能性を加味してトータル的にサポートいたします。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。








