公開日:2025.09.23 更新日:2025.08.13
不動産にかかる税金を網羅解説|種類・計算・節税まで徹底ガイド

不動産を取得・保有・売却する各段階では、さまざまな税金が課されます。各段階でどのような税金がかかるか把握していないと、思わぬ税負担や手続きの不備につながる可能性があります。
この記事では、不動産にかかる主な税金を「取得」「保有」「売却」の3つの場面に分けて解説し、それぞれの課税内容や計算方法、適用可能な特例措置(軽減措置)などを幅広く紹介します。関連する法律や税制(所得税法、地方税法、登録免許税法など)を踏まえつつ、正確な手続きと節税のポイントを押さえることで、不要な支出を防ぎ、不動産の有効活用や安定した資産形成が可能になります。
初心者の方でも理解しやすいように構成しつつ、実務上押さえておくべき専門知識や注意点も適宜盛り込んでいます。ぜひ最後までご覧いただき、ご自身のライフプランや投資戦略に応じた税務対策に役立ててください。
目次
1. 不動産の税金とは?基本の種類と概要

まずは、不動産にかかる税金の全体像を押さえ、それぞれの要点を理解しておきましょう。
不動産に関わる税金は、「取得時」「保有時」「売却時(譲渡時)」の3つの局面で発生します。購入や投資を検討する際は、初期費用だけでなく、毎年かかる固定資産税などのランニングコストも考慮が必要です。
さらに、購入した不動産から家賃収入を得る場合、所得税や住民税の負担が増減する点にも注意が必要です。こうした視点を持つことで、不動産投資や資産管理の計画をよりスムーズに立てられます。
また、国や自治体には住宅用不動産を支援する減税制度や特例措置もあり、条件を満たせば税負担を軽減できる可能性があります。制度を活用することで、資金計画に余裕を持たせることができます。
2. 不動産取得時にかかる主な税金

不動産を取得した際に必要となる税金は多岐にわたります。それぞれの税金の概要とポイントを確認しましょう。
不動産を購入するときには契約書の作成、登記、納税通知書の受領など各段階で税負担が発生するため、事前に全体像を把握しておくと、計画的な資金準備が可能です。
たとえば、新築住宅では消費税が発生し、個人間売買では原則として非課税になるなど、取引相手や物件種別により税制の扱いが異なります。初期費用に影響するため、軽減措置の有無も確認しておきましょう。
2-1. 不動産取得税
不動産取得税は、都道府県が課税する地方税で、不動産取得時に一度だけ課されます。課税標準額×税率で算出され、住宅用地や住宅には減税措置が設けられています。
たとえば新築や要件を満たす中古住宅は軽減税率の対象となることもあるため、事前確認が重要です。納付は納税通知書によって通知され、期限内に行います。
物件の評価額や用途によって税額は大きく変わるので、購入前の試算が不可欠です。特に投資用物件であっても軽減措置を受けられる場合があるため、忘れずに確認しましょう。
2-2. 印紙税
印紙税は、契約書や領収書などの課税文書に課される国税です。不動産売買契約書の契約金額に応じて、貼付すべき印紙の金額が変わります。
建築請負契約書やローン契約書にも印紙税が必要な場合があり、事前に一覧で確認しておくと安心です。
また、印紙税には軽減措置があり、契約時期によって税額が異なる可能性があるため注意が必要です。契約書が2通ある場合、原則として双方に課税されますが、電子契約では印紙税が非課税となるため、導入が進んでいます。
2-3. 登録免許税
登録免許税は、法務局で不動産登記を行う際に必要となる国税です。登記の種類(所有権移転登記、保存登記など)や不動産の固定資産税評価額に応じて税率が変わります。
住宅用として利用する場合は税率が軽減されることがあるため、購入前に対象となるか確認すると良いでしょう。特に住宅ローンを組む際には抵当権設定登記が必要となるため、その分の登録免許税も計算に入れておく必要があります。
登記手続きは不動産購入の際に必須で、書類や手続きも多岐にわたります。不備を避けるためには司法書士に依頼するのが一般的ですが、その際の報酬も含めて総費用を計算しておくことが大切です。
2-4. 消費税
不動産の売買では個人間取引が多い場合、消費税は課税されません。一方で、不動産会社が売主の場合、新築の建売や投資用マンションの販売などには消費税が課されます。
また、建築請負契約や業者仲介のリフォーム工事費などにも原則消費税がかかるため、物件価格以外にも税負担が発生する点に留意しましょう。
売買契約の内容や相手によって非課税・課税の区分が異なるため、契約時に消費税の適用関係を明確にしておくことがジョイントコストの見落としを防ぐポイントです。
2-5. 相続税・贈与税
相続や贈与によって不動産を取得した場合には、相続税や贈与税が課される可能性があります。評価額や相続人・受贈者の人数により、課税額は大きく変わります。
相続税においては小規模宅地等の特例をはじめ、適用可能な各種特例が充実しているため、要件を満たしていれば大幅に税負担を下げることができます。
贈与税に関しても、配偶者控除や住宅取得資金の特例など、一定の条件を満たせば税額を減らせる制度もあります。それぞれの手続き期限や申告時期を逃さないよう準備しましょう。
3. 不動産を保有しているときにかかる税金

不動産を持ち続けている間にかかる税金には、毎年定期的に発生する税や、収入に応じて変動する税があります。
保有期間中には、毎年納める固定資産税や都市計画税が代表的です。自宅だけでなく、投資用物件を複数所有している場合には物件数の増加に伴って保有コストが増える点に注意が必要です。
また、賃貸経営をしていると家賃収入に応じた所得税や住民税が課税されます。賃貸規模が拡大すると、個人でも事業税の課税対象になる場合があります。どの程度の規模で運用するかをあらかじめ検討しておくと良いでしょう。
こうした保有時の税金は、長期的なキャッシュフロー計画に大きく影響します。購入時の資金計画だけでなく、継続的な維持費や税負担も見込んでおくことが、安定した不動産運営の鍵となります。
3-1. 固定資産税・都市計画税
固定資産税は毎年、市町村から送付される納税通知書に従って支払う地方税です。土地と建物それぞれに評価額が設定され、その評価額に対して1.4%(標準税率)を基本とする税率で計算されます。
都市計画税は、主に市街化区域内の土地や建物に対して課税され、標準税率は0.3%ですが、自治体によって異なることがあります。
住宅用地や小規模住宅用地の場合には、税軽減措置が受けられることも多いため、物件の用途や規模を把握しておくことが大切です。特に、建物の構造や築年数によっても評価額は変動します。
3-2. 所得税・住民税
不動産の賃貸から得られる家賃収入は不動産所得に分類され、所得税や住民税の計算に影響します。必要経費として管理費や減価償却費などを差し引くことは可能ですが、利益が出れば納税が必要になります。
また、不動産の売却によって得られた譲渡所得も課税対象です。所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、税率が高くなるため、売却時期の判断が重要です。
確定申告を行う際は、収入と経費の記録を正確に行う必要があります。物件数が多い場合は、税理士のサポートや会計ソフトの導入を検討し、申告漏れや計算ミスを防ぎましょう。
3-3. 事業税
事業税は、個人で不動産賃貸を事業的規模税率は都道府県により異なりますが、所得に応じて概ね3〜5%で課されます。事業として認定されると、青色申告特別控除や専従者給与の適用など節税手段も広がります。
一方で、事業税の負担が想定より大きくなる可能性もあるため、事前に収支シミュレーションを行っておくことが大切です。
4. 不動産売却時にかかる税金

不動産を売却する際に課される税金は、譲渡所得に関連する税金と、契約書に付随する税金の2つに大別されます。
なかでも、譲渡所得にかかる所得税・住民税は、売却時の支出の中で最も大きな負担になることが一般的です。
譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて算出されます。購入時の売買価格だけでなく、仲介手数料やリフォーム費用なども取得費に含めることができるため、領収書類の保管が重要です。
また、売買契約書には再度印紙税が必要となり、売主が不動産会社など課税事業者の場合は、建物部分に対して消費税が発生するケースもあります。
特に居住用不動産を売却する場合は、3,000万円特別控除や軽減税率の特例などを活用できれば、実際の納税額を大幅に抑えられる可能性があります。売却前に要件や適用条件をよく確認しておきましょう。
4-1. 譲渡所得税(所得税・住民税)
不動産を売却して得た譲渡所得は、所有期間が5年を超えるかどうかで課税区分が変わります。
5年以下の短期譲渡所得は、所得税30%・住民税9%(合計39.63%:復興特別所得税を含む)の税率が適用されるのに対し、5年超の長期譲渡所得では所得税15%・住民税5%(合計20.315%:復興特別所得税を含む)と、大きな差があります。
譲渡所得の計算式は以下の通りです:
譲渡所得 = 譲渡価格 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費には、購入時の売買代金、仲介手数料、登記費用、リフォーム費などが含まれます。ただし、取得費に関する書類を紛失している場合、「概算取得費(売却額の5%)」しか計上できないことがあるため注意が必要です。
また、居住用財産を売却する場合、一定条件を満たせば「3,000万円の特別控除」や「所有期間10年超の軽減税率(10%+4%)」などの特例が適用可能です。
これらの特例を活用すれば、譲渡所得が出た場合でも税負担を最小限に抑えることができます。ただし、要件には「過去2年以内に適用していないこと」などの制限があるため、事前確認が不可欠です。
4-2. 印紙税
不動産売却時の契約書にも、買主側と同様に印紙税を貼付する必要があります。売買金額によって印紙税額が異なる点は、購入時と同じです。
印紙の貼付を忘れると契約書が無効になるわけではありませんが、本来納めるべき税金を支払っていないとして追徴金を課される可能性があります。契約締結の際には必ず印紙を用意しましょう。
また、売買契約の様式や時期によっては軽減措置が存在する場合もあります。適用期限が設けられていることが多いため、タイミングを見極めて節税を図ることが大切です。
4-3. 消費税
不動産売却において、個人間で行う売買の場合、原則として土地・建物ともに消費税は課されません。ただし、売主が不動産会社や個人事業主(課税事業者)の場合、建物部分に対して10%の消費税が課税されます。
特に、賃貸物件や事業用物件などを扱っている法人や課税事業者が売主である場合には、売却益だけでなく消費税の納税義務が発生するため、消費税の仕入税額控除も含めた精密な計算が求められます。
また、消費税は建物の評価額や取得形態によって算出方法が異なります。土地部分は非課税ですが、仲介手数料・司法書士報酬などの一部業務費には消費税が含まれるため、実務上の総費用計算に注意が必要です。
5. 不動産税金の計算方法と申告の流れ

不動産にかかる税金は、取得・保有・売却の各段階で異なる手続きが必要です。あらかじめ流れを把握し、期限や書類を整理しておくことが重要です。
5-1. 取得時の税金
印紙税や登録免許税は契約・登記のタイミングで納付し、不動産取得税は後日、納税通知書で請求されます。各税金の支払時期や必要書類は事前に確認しておきましょう。
5-2. 保有中の税金と申告
保有期間中は、固定資産税や都市計画税が毎年課税されます。また、家賃収入がある場合は確定申告が必要です。青色申告を選択すれば、帳簿管理によって節税効果が得られます。
5-3. 売却時の税金
売却時には譲渡所得税が発生します。取得費や譲渡費用を差し引いて計算し、適用できる特例がないか確認することが大切です。
確定申告の期限に間に合うよう、書類や納税額を早めにチェックしましょう。
6. 賢く活用!不動産の節税・軽減措置

各種の税金に対しては、一定の要件を満たすことで軽減措置や特例が適用される場合があります。
不動産にかかる税額は、購入形態や用途、所有期間などの条件によって大きく異なります。こうした条件を正確に確認し、該当する制度を最大限に活用することが、資産形成や資金効率向上の鍵となります。
税制の変更は頻繁に行われるため、最新の法改正情報を定期的に確認し、時限的な特例を見逃さないよう注意が必要です。とくに家族構成やライフスタイルの変化に応じて制度を見直すことで、より効果的な節税が可能になります。
適用可能な控除や特例を正しく使えば、長期的に見て税負担に大きな差が出ます。ただし誤って制度を適用すると追徴課税や加算税のリスクもあるため、専門家や税務署に確認しながら進めることが安全です。
6-1. 取得時の軽減制度:不動産取得税など
新築住宅や省エネルギー性能を備えた住宅を購入・建築した場合、不動産取得税の税率が軽減されたり、床面積などの要件を満たすことで一定額の減額措置が適用されることがあります。
制度の適用には物件や契約内容に応じた細かい条件があるため、購入前に対象となるかどうかを確認し、必要書類を整えた上で申請を行うことが重要です。
とくに、初めて住宅を取得する方や若年層に向けた支援措置が充実していることが多いため、自治体の公式サイトやパンフレットで最新情報を収集しましょう。
6-2. 保有時の減免制度:固定資産税・都市計画税
住宅用地や、一定の要件を満たす新築住宅に対しては、固定資産税や都市計画税の課税標準を一時的または継続的に軽減する制度があります。これにより、所有期間中の税負担を軽くし、長期保有における資産の維持コストを抑えることが可能です。
固定資産税の評価替え(3年に1度)や土地評価額の見直しも、保有コストの変動要因となるため、評価額に疑問があれば自治体に再評価の申し出を行うことも選択肢となります。
また、耐震改修や省エネ改修などを行った場合には、追加的な減税制度が適用されることもあります。手続きには工事証明書類などが必要なため、あわせて準備しておきましょう。
6-3. 売却時の特例:譲渡所得控除など
居住用不動産を売却する際には、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「居住用財産の特別控除」が適用される制度があります。これはマイホームを売却して住み替える場合などに活用でき、譲渡所得に対する課税額を大幅に軽減することが可能です。
また、所有期間が10年を超える場合には、長期譲渡所得に係る軽減税率(14.21%など)が適用されるケースもあります。売却時には他にも「買換えの特例」や「相続財産の譲渡特例」などがあるため、事前に制度の選択肢と適用条件を比較検討することが有効です。
ただし、過去に同じ控除を利用していた場合や、投資用として保有していた期間があると対象外となることもあるため、詳細な要件を確認のうえ進めましょう。
7. 不動産の税金に関するQ&A
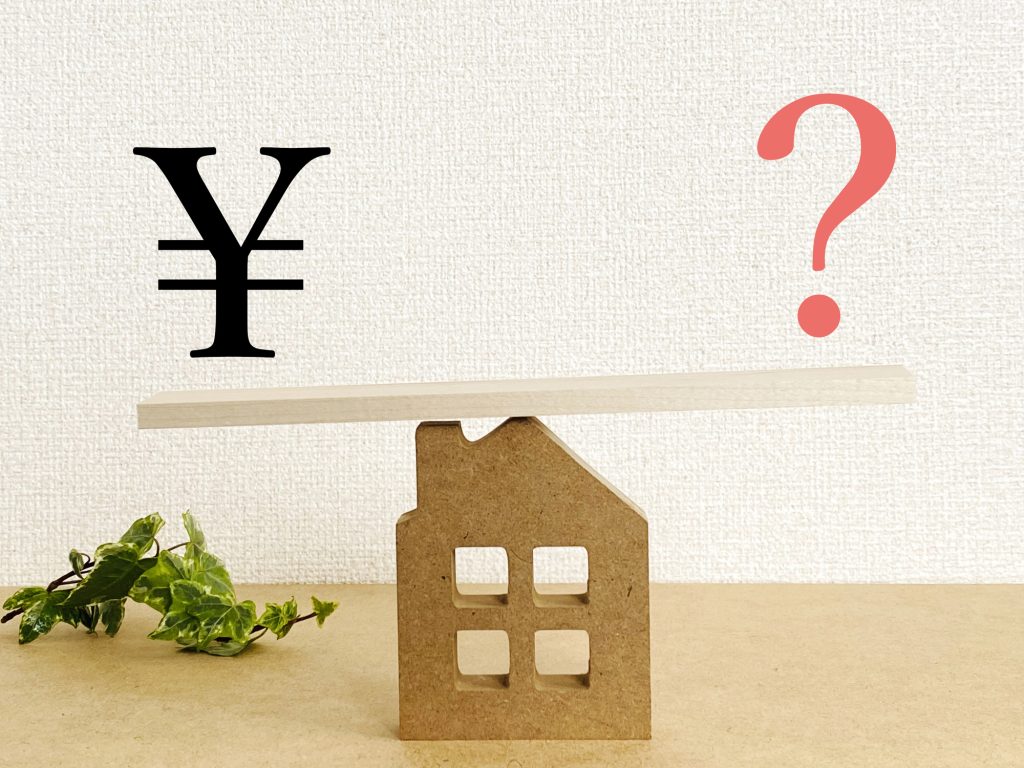
不動産の税金について、よくある質問や迷いやすいポイントをあらかじめ把握しておきましょう。
Q. 住宅ローン控除はどの税金を減らせるの?
A. 住宅ローン控除は原則として所得税から控除されます。控除しきれなかった分については、一定の上限のもとで翌年度分の住民税からも控除が可能です(最大13.65万円/年)。そのため、住宅購入時には大きな節税効果が期待できる制度です。
※住宅ローン控除の適用には、借入期間や床面積、耐震基準などの条件があります。
Q. 相続した空き家を売却するときに何か特例はある?
A. 「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」があります。一定の条件を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる可能性があります。
主な要件として、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅であることや、相続後に耐震改修または解体を行って売却することなどが挙げられます。制度の適用には複雑な要件確認と期限の管理が必要なので、専門家への相談を推奨します。
Q. 結局どの税金から手続きすればいいの?
A. 不動産に関わる税金は、取引のタイミングごとに発生する税目が異なります。
- 取得時には、印紙税・登録免許税・不動産取得税などがかかります。
- 保有中は、固定資産税・都市計画税が毎年課税されます。
- 売却時には、譲渡所得税(所得税+住民税+復興特別所得税)が発生する場合があります。
手続きの時期や管轄窓口(税務署・都道府県・市町村など)も異なるため、全体のスケジュール感と役割分担を事前に把握しておくことが重要です。
まとめ・総括
不動産にかかる税金は取得から売却まで多岐にわたるため、各段階ごとの税負担と軽減措置を正しく把握することが不可欠です。
不動産は、取得・保有・売却というライフサイクルの中でそれぞれ異なる税金が課されますが、それぞれに応じた特例や軽減制度が用意されています。これらの制度を的確に活用すれば、数十万円から場合によっては数百万円規模のコスト削減につながることもあります。
また、税制や関連手続きは法改正や政策変更により見直されることがあるため、常に最新情報の確認が必要です。
不動産は一度取得すれば終わりではなく、保有中や売却時にも適切なタイミングで制度を活用し、状況に応じた対応を取ることが求められます。専門家のサポートを受けるだけでなく、自分自身でも基本的な制度を学び、情報を継続的にアップデートしておくことが、将来の資産形成や無理のない不動産投資を実現するための大きな助けとなるでしょう。
この記事の監修者

白崎 達也 アキサポ 空き家プランナー
一級建築士
中古住宅や使われなくなった建物の再活用に、20年以上携わってきました。
空き家には、建物や不動産の問題だけでなく、心の整理が難しいことも多くあります。あなたが前向きな一歩を踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。








